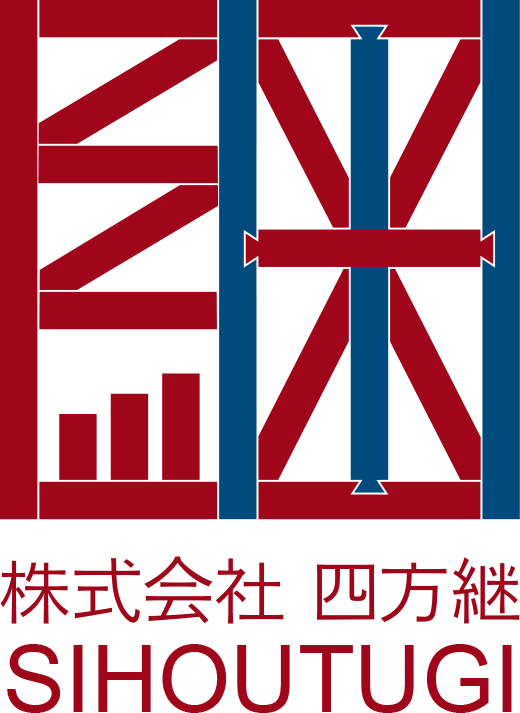はじめに:建築業界が抱える課題と私たちの挑戦
神戸市西区で「つむぎ建築舎」という工務店を運営している私たち株式会社四方継は、2013年から「職人起業塾」という独自の教育プログラムを展開しています。
建設業界では深刻な職人不足が叫ばれて久しいですが、私たちが直面している課題は単なる人手不足だけではありません。技術を持った職人がいても、その能力を十分に発揮できる環境や、長期的に成長できるキャリアパスが整っていないという問題があります。
多くの職人さんは「いずれは独立したい」という夢を持っていますが、実際に独立して成功するのは簡単ではありません。経営の知識や資金繰り、営業活動など、技術以外にも様々なスキルが必要になるからです。
そこで私たちは考えました。職人が独立しなくても、組織の中で最大限の力を発揮し、やりがいと適切な報酬を得られる仕組みを作れないだろうか、と。その答えが「イントラプレナーシップ」という考え方でした。
私たちの企業理念は「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」というものです。この「四方良し」とは、お客様、地域社会、そして作り手である私たち自身、すべてが良い状態になることを目指すという意味です。職人起業塾は、この理念における「作り手良し」を実現するための中核的な取り組みなのです。
職人起業塾とは何か:明確な目的を持った教育プログラム
職人起業塾は、一般的な技術研修や独立支援とは全く異なるアプローチを取っています。最も重要なポイントは、このプログラムが「独立開業を支援するものではない」という点です。
よく誤解されるのですが、私たちは職人を独立させることを目標にしていません。むしろ逆です。組織の中にいながら、起業家のような高い意識と創造性を持って働ける人材を育てることが目的なのです。
この「組織内起業家精神」のことを、専門用語で「イントラプレナーシップ」と呼びます。イントラプレナーシップとは、会社員でありながら、まるで自分が経営者であるかのような当事者意識を持ち、積極的に課題解決や改善提案を行う姿勢のことです。
2013年に職人起業塾を開講した当初から、私たちは「社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化」を明確な目的として掲げてきました。そしてこの取り組みは次第に評価され、2016年には一般社団法人として法人化し、全国展開するまでに成長しました。
さらに2015年には、JBN京阪神木造住宅協議会という業界団体の研修事業として、半年間にわたる本格的なカリキュラムを実施する機会もいただきました。これは私たちのプログラムが、業界全体から専門性と効果を認められた証だと自負しています。
なぜ独立支援ではないのか。それは、独立には大きなリスクが伴うからです。技術は優れていても、経営がうまくいかずに廃業してしまう職人を何人も見てきました。それは本人にとっても、業界にとっても大きな損失です。
組織という安定した基盤があれば、職人は経営リスクを負うことなく、技術の向上とお客様への価値提供に集中できます。そして適切に評価され、報酬を得ることができる。これこそが、持続可能な職人のキャリアパスだと私たちは考えています。
イントラプレナーシップが生み出す高い技術力
イントラプレナーシップを持った職人は、単に言われたことをこなすだけの作業者ではありません。自分の仕事が最終的にお客様の暮らしにどう影響するのかを深く理解し、常に最高の品質を追求します。
たとえば断熱気密工事という作業があります。これは住宅の快適性を左右する非常に重要な工程ですが、壁の中に隠れてしまうため、完成後には見えなくなってしまいます。
ここで差が出るのです。ただ仕様書通りに作業する職人と、イントラプレナーシップを持つ職人では、仕上がりに大きな違いが生まれます。私たちの職人は「すき間から空気が漏れないようにしっかり丁寧に施工する」ことを徹底しています。なぜなら、その作業が住み手の快適性に直結すると理解しているからです。
以前、愛知の歯科クリニックの現場で印象的な場面がありました。左官工事の下地となる「木摺り」という作業を見たとき、思わず感嘆の声が漏れました。柱の両側に細い木材を細かいピッチで留めていく地道な作業なのですが、その仕上がりの美しさは芸術的でした。
最終的にはこの木摺りも土壁に覆われて見えなくなります。しかし職人は「隠れてしまうのがもったいない」と思えるほどの品質で仕上げていたのです。これがイントラプレナーシップです。誰も見ない部分でも、決して手を抜かない。それが私たちの職人の誇りなのです。
また、資源を無駄にしないという意識も重要です。あるワークデスクの製作では、3×6判の合板1枚から、できるだけ無駄が出ないように部材を切り出す「木取り」の技術が発揮されました。これは単なる技術ではなく、コスト効率と環境への配慮を両立させる、経営的な視点に基づいた専門的なノウハウです。
受け継がれる価値のある丁寧なものづくり。これが私たちのビジョンであり、イントラプレナーシップを持つ職人だからこそ実現できる品質なのです。
お客様との信頼関係を築く職人の姿勢
イントラプレナーシップは、技術面だけでなく、お客様とのコミュニケーションにも表れます。社内起業家精神を持つ職人は、会社を代表するプロフェッショナルとして、お客様に真摯に向き合います。
私たちの強みの一つは、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションです。家づくりでは、お客様自身もまだ気づいていない潜在的なニーズがたくさんあります。それを丁寧なヒアリングと対話を通じて引き出し、形にしていくのが私たちの仕事です。
ここで大切なのが「施工プロセスの見える化」です。家を建てる過程では、多くの工程が壁の中や床の下に隠れてしまいます。完成してからでは、どんな工事をしたのか確認できません。
だからこそ私たちは、工事の進捗や技術的な詳細について、お客様に丁寧に説明します。写真を撮って共有したり、現場を見学していただいたり。こうした透明性のある対応が、お客様の深い安心感につながるのです。
また、私たちは2009年から無料巡回メンテナンスサービスを本格化させています。神戸近郊のお客様に限られますが、建てた後も定期的に訪問し、住まいの状態をチェックしています。
このサービスは単なる営業活動ではありません。イントラプレナーシップを持つ職人は、自分が携わった建築物を長期的に守り、住み手との信頼関係を維持することに責任を感じているのです。「すべてのお客様に生活の安心・安全を」という合言葉のもと、建てた後もずっと寄り添い続ける。それが私たちの姿勢です。
お客様からは「安心して任せられる」「長く付き合える工務店だ」という声をいただきます。これこそが、イントラプレナーシップが生み出す信頼関係の証なのです。
未来を見据えた教育システムの構築
職人起業塾の取り組みは、単独で存在しているわけではありません。私たちは職人育成のための包括的なシステムを構築しています。
2023年4月、私たちは「マイスター高等学院」という通信制高校を開校しました。これは高校卒業の資格を取りながら、大工などの職人技術を身につけることができる画期的な教育機関です。
なぜこのような学校が必要なのか。それは、職人不足の根本的な原因が、若い世代にとって職人が魅力的な職業に見えていないという点にあるからです。
通常の高校では、大学進学が前提とされがちです。しかし実際には、ものづくりに向いている才能を持った若者がたくさんいます。そうした才能が埋もれてしまうのは、社会にとって大きな損失です。
マイスター高等学院は、そうした才能を早い段階で見つけ、開花させる場所です。ここで基礎を学んだ若者が、将来的に職人起業塾で更なる研鑽を積む。そうした一貫した育成の流れを作ることで、業界全体の質を高めていけると考えています。
私たちが掲げる大きなビジョンは「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にする」ことです。かつて大工は尊敬される職業でした。その地位を取り戻し、優秀な人材が継続的に業界に入ってくる流れを作りたいのです。
また、経営者や専門家向けには「継塾」という研修会を偶数月に開催しています。ここではホットシート形式で、参加者のビジネスモデルをブラッシュアップしていきます。
たとえば今年6月の継塾では、ゴミの収集運搬業を営む企業の事例を通じて、社会課題解決型ビジネス、いわゆるCSVモデルについて深く議論しました。また3月には、持続可能なビジネスモデルの根幹にある「常態」について、哲学的な視点から考察しました。
こうした高度な経営研修を通じて、職人起業塾の卒業生や社内のイントラプレナーたちが、常に最新の知見と倫理観を持って組織運営に貢献できる環境を整えています。
さらに、私たちの専門性は国際的な活動経験によっても裏付けられています。2014年には台北に現地法人を設立し、職人支援事業を開始しました。海外での事業展開を通じて、日本の建設業界の課題をより広い視野で捉え、効果的な育成プログラムを構築する知見を得ることができました。
四方良しを実現する組織の信頼性
私たちは2020年に社名を四方継に変更しました。これは「地域を守り次世代に継なげる事業を目指す」という決意の表れです。
そしてこの理念に基づいた事業運営が評価され、2022年には一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されました。これは職人育成を含む全ての事業において、持続可能で社会的な意義を持つ運営を行っていることが認められた証です。
イントラプレナーシップを持つ組織全体で取り組むことで、私たちは地域社会から高い信頼を得ています。それは単に良い家を建てるということだけでなく、地域の雇用を守り、技術を継承し、文化を育てるという、より大きな役割を果たしているからです。
無料巡回メンテナンスサービスの継続も、こうした信頼の基盤になっています。建てた後も責任を持ち続ける。この姿勢が、長期的な安心と信頼を生み出しているのです。
おわりに:イントラプレナーシップという選択
職人起業塾が推進する「イントラプレナーシップ」は、独立開業を進めるものではありません。むしろ、組織の中で最大限の能力を発揮できる環境を整えることで、職人が安定したキャリアを築けるようにするためのプログラムです。
私たちは職人を単なる労働力ではなく、企業の成長に不可欠な経営パートナーとして捉えています。だからこそ、技術だけでなく、経営的な視点や顧客対応力、そして高い倫理観を育てることに力を入れているのです。
全国展開の実績、マイスター高等学院との連携、継塾による継続的な学び。これらすべてが統合されることで、私たちは「四方良し」を実現できる組織を作り上げています。
お客様に最高の価値を提供し、地域社会に貢献し、そして作り手である職人が誇りとやりがいを持って働ける環境。それが私たちの目指す姿です。
これからも職人起業塾を通じて、技術と情熱を持った作り手を育て、彼らが活躍できる環境を整備していきます。そして日本の建築業界の未来を、地域社会とともに創っていきたいと考えています。