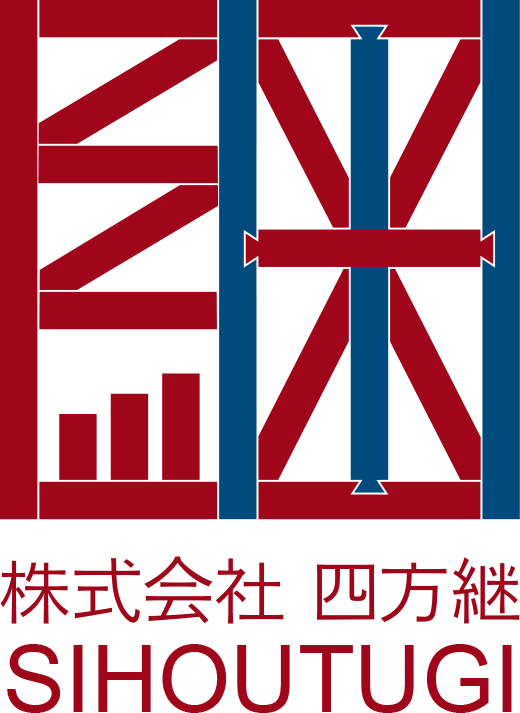こんにちは、株式会社四方継です。今日は私たちが大切にしている理念と、それを実現するための具体的な取り組みについてお話しします。
「四方継って何をしている会社なの?」と聞かれることがよくあります。確かに、建設業界には珍しい社名ですよね。実は私たちの社名には、深い想いが込められているのです。
四方継が目指す「四方良し」の世界とは
私たちのミッションは「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」ことです。この「四方」とは、作り手(職人)、住み手(お客様)、協力会社、そして地域社会の4つを指しています。
近江商人の「三方良し」という言葉をご存知でしょうか。売り手良し、買い手良し、世間良しという考え方ですが、私たちはこれをさらに発展させました。建築業界において、この4つの立場すべてが幸せになることを目指しているのです。
例えば、美しい家を建てたとしても、その地域が衰退してしまったら、住み手の方は本当に幸せでしょうか。また、職人さんたちが技術を身につけても、それを活かす場がなければ意味がありません。すべてが繋がり合って、初めて本当の価値が生まれると私たちは考えています。
2020年に創立20周年を機に社名を「株式会社四方継」に変更したのも、この理念を明確にするためでした。それまでは別の社名でしたが、地域を守り次世代に継ぐ事業を目指すという強い決意を込めて、新たなスタートを切ったのです。
実際に、私たちのお客様からは「建てた後のフォローがしっかりしている」「地域のことを本当に考えてくれている」という声をいただくことが多く、この理念が実を結んでいることを実感しています。
「つない堂」が創る、検索不要の安心な地域社会
現代社会では何か困ったことがあると、すぐにインターネットで検索しますよね。でも、検索結果に出てくる業者が本当に信頼できるのか、不安に思ったことはありませんか。
そこで私たちが立ち上げたのが「つない堂」という事業です。つない堂のビジョンは「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
つない堂では、以下の3つの活動を行っています。
まず、卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘します。これは単に業者を集めるのではなく、本当に質の高い、信頼に足る専門家やサービスを厳選することを意味します。例えば、電気工事を依頼したいとき、技術力はもちろん、お客様への対応やアフターフォローまで含めて評価し、推薦できる業者さんを見つけるのです。
次に、発掘された要素を基に、リアルなネットワークを構築します。インターネット上の情報だけでなく、実際に顔を合わせ、信頼関係を築いていくのです。先日も、つない堂を通じて紹介した電気工事業者さんとお客様が、工事後も定期的に点検をお願いする関係になったという報告をいただきました。
最後に、積極的な情報発信と共有を行うメディアとして機能します。SNSやブログを通じて、地域の良い事業者さんの情報や、暮らしに役立つ情報を発信しています。
つない堂が目指すのは、インターネット検索を必要としない安心な循環地域型社会のハブとなることです。地域内でお金が循環し、情報格差がなくなり、住民の安全性が向上する、そんな社会を実現したいのです。
私たちは2009年から、神戸近郊のお客様に対して無料巡回メンテナンスサービスを提供しています。建築後も長期にわたって住まい手の安全を支え続けるこのサービスは、つない堂の理念を体現するものでもあります。「建てて終わり」ではなく、ずっと寄り添い続ける姿勢が、地域社会との信頼関係を築く基盤となっているのです。
また、社名を四方継に変更したことを機に、私たちは「すみれ暮らしの学校」の活動をつない堂へと移行させました。住環境に食、学びを通して日々の暮らしを豊かにするという理念は、料理教室、ガーデニング講座、整理収納セミナー、子育て相談会など、暮らしに密着した様々な講座として今も続いています。つない堂の枠組みの中で、住まい手の皆さんが単に「家」を持つだけでなく、豊かな「暮らし」を営めるようサポートし続けているのです。
「継塾」で育む、持続可能な経営文化
「いい街を継ぐ」ためには、建物だけでなく、持続可能な経営の文化も継承していく必要があります。そこで私たちが運営しているのが「継塾」というプラットフォームです。
継塾では、社会課題の解決とビジネスの両立を目指すCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)について議論を行っています。CSVとは「Creating Shared Value」の略で、企業が利益を追求しながら社会課題も解決する経営手法のことです。
偶数月には、参加者のビジネスモデルを刷新・ブラッシュアップさせる「ホットシート」という時間を設けています。これは、参加者の一人が自分のビジネスについてプレゼンテーションを行い、他の参加者全員でそのビジネスモデルをより良いものにするために議論する場です。
例えば、令和7年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏がプレゼンを行いました。一見、建築とは関係ないように思える分野ですが、地域社会の清潔さを保つという重要な役割を担っています。
川内氏からは「ゴミ収集業界の人手不足をどう解決するか」「地域住民との信頼関係をどう築くか」といった課題について発表がありました。参加者からは「ITを活用した効率化」「教育制度の充実」「地域イベントへの参加」などの提案が出され、活発な議論が行われました。
このように継塾では、業界を問わず、地域社会に貢献する事業者が集まり、お互いの経験や知識を共有しています。建築、IT、飲食、教育、環境など、さまざまな分野の専門家が一堂に会することで、新しいアイデアや解決策が生まれるのです。
継塾の活動は、地域のリーダーや事業者が、理(ことわり)にじっくりと向き合い、全ての成果の元になる「常態」を理解し、改善していくための「学びの文化」を地域に根付かせる試みでもあります。単発のセミナーとは違い、継続的に学び合う場があることで、参加者同士の結束も深まり、地域全体の底上げにつながっています。
社内起業家精神を育む「職人起業塾」
建築業界が抱える最大の課題の一つが職人不足です。熟練の職人さんたちが高齢化し、若い世代の参入が少ない状況が続いています。この問題を解決しなければ、どんなに立派な設計図があっても、実際に建物を建てることができません。
私たちは2013年に「職人起業塾」を開講しました。これは、社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的とした取り組みです。ここで重要なのは、職人起業塾は独立開業を促進するものではなく、イントラプレナーシップ、つまり社内起業家精神を醸成する研修であるということです。
組織の中で主体的に動き、新しい価値を創造できる人材を育てることで、会社全体の競争力を高めることを目指しています。社員一人ひとりが経営者のような視点を持ち、自分の仕事に責任と誇りを持って取り組む。そんな文化を作り上げたいと考えているのです。
職人起業塾では、以下のようなカリキュラムを提供しています。
技術面では最新の建築技法や安全管理について学びます。例えば、省エネ住宅の施工方法や、新しい建材の特性などです。また、実際の現場での作業を通じて、理論だけでなく実践的なスキルも身につけます。
経営面では、事業計画の立て方、コスト管理の方法、顧客との関係構築など、ビジネスに必要な知識を教えます。多くの職人さんは技術には長けていても、経営的な視点については学ぶ機会が少なかったのです。そこで、わかりやすい言葉で丁寧に説明し、実際のプロジェクトに活かせる知識を提供しています。
マインド面では、職人としての誇りや使命感を育みます。「単に作業をする人」ではなく、「社会に貢献する技術者」としての意識を持ってもらうのです。自分の仕事が地域社会にどのような価値を提供しているのかを理解することで、仕事へのモチベーションも高まります。
職人起業塾を受講した社員からは「仕事の見方が変わった」「お客様とのコミュニケーションが改善した」「会社全体の利益を考えるようになった」という声をいただいています。また、若手社員にとっては、先輩職人から直接学べる貴重な機会となっており、技術の継承にも大きく貢献しています。
この職人起業塾のノウハウは後に一般社団法人として全国展開されました。私たちの取り組みが他の地域にも広がり、全国の職人育成に貢献していることを誇りに思っています。
マイスター高等学院による次世代の人材育成
職人不足の根本的な解決には、若い世代の参入を促すことが不可欠です。そこで私たちが2023年4月に開校したのが「マイスター高等学院」という通信制高校です。
この学校の最大の特徴は、高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における「職人」としての技術を身につけることができることです。通常の高校では学べない実技を中心としたカリキュラムで、卒業時には即戦力として活躍できる技術を習得できます。
なぜこのような学校を設立したのでしょうか。それは、現在の教育システムでは、手を動かしてモノを作ることが得意な子どもたちの才能が見過ごされがちだからです。
私たちの代表である高橋剛志は、「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にしたい」という強い想いを持っています。現在、多くの子どもたちはYouTuberやプロスポーツ選手に憧れを抱きますが、職人への憧れは薄れています。しかし、職人の仕事は社会にとって不可欠であり、やりがいに満ちた素晴らしい職業なのです。
マイスター高等学院では、以下のような教育を行っています。
基礎学習では高校卒業に必要な一般教養を学びます。ただし、座学だけでなく、実際の建築現場や職人の仕事と関連付けながら学ぶことで、より理解しやすくしています。
実技学習では、木工、左官、電気工事、配管工事など、建築に関わる様々な技術を体験します。最初は簡単な作業から始めて、徐々に複雑な技術を身につけていきます。
キャリア教育では、職人としての働き方や将来設計について学びます。独立開業を目指す道もあれば、大きな建設会社で専門技術を磨く道もあることを説明し、一人ひとりの適性や希望に応じたキャリアプランを一緒に考えます。
開校から1年余りが経過しましたが、生徒たちの成長は目覚ましいものがあります。入学当初は「将来何をしたいかわからない」と言っていた生徒が、今では「一人前の大工になりたい」と目を輝かせて話すようになりました。
また、保護者の方からも「子どもが生き生きと学校に通うようになった」「手に職をつけられるので将来が安心」という感想をいただいています。私たちにとって、これほど嬉しいことはありません。
技術者集団「つむぎ建築舎」の挑戦
私たちの技術者集団である「つむぎ建築舎」は、「木と暮らしをデザイン、実現する技術者集団」として、常に最新の技術に挑戦しています。
その成果の一つが、高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」です。この住宅は国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されており、エネルギー効率の高さが公的に認められています。
ゼロエネルギー住宅とは、年間の1次エネルギー消費量が正味でゼロ以下になる住宅のことです。高断熱化と高効率設備により消費エネルギーを減らし、太陽光発電などでエネルギーを創ることで実現します。
SUMIKA-ZEROでは、外壁、屋根、床、窓など住宅全体の断熱性を高めることで、冷暖房に必要なエネルギーを大幅に削減しています。夏は涼しく、冬は暖かい、一年中快適な住環境を提供します。LED照明、高効率エアコン、エコキュートなど、消費電力の少ない設備を採用し、同じ性能でも消費エネルギーを抑えることで、光熱費の削減にもつながります。太陽光発電システムを設置し、住宅で使用する電力を自然エネルギーでまかなうことで、余った電力は電力会社に売電することも可能です。
また、つむぎ建築舎では電磁波への対策も開始しています。現代の住宅には多くの電気設備が使われていますが、これらから発生する電磁波が健康に与える影響を懸念する声もあります。そこで、電磁波を低減する建材や工法の研究を進めています。
住まい手の方の安全と快適性を最優先する姿勢は、私たちの地域社会への継続的なコミットメントを表しています。単に法律や基準をクリアするだけでなく、より高いレベルでの安全性を追求しているのです。
未来への責任を果たす総合的な取り組み
これまでご紹介してきた取り組みは、すべて「いい街を継ぐ」というビジョンの実現に向けたものです。私たちは、建築会社としての枠を超えて、地域社会全体の発展に貢献したいと考えています。
私たちのコミットメントは、以下の三つの柱で支えられています。
一つ目は、信頼のインフラ構築です。つない堂を核とし、インターネット検索に頼らない、安心安全な地域社会のリアルなネットワークを構築することです。顔の見える関係を大切にし、地域の人々が互いに支え合える環境を作っています。
二つ目は、経営文化の継承です。継塾を通じて、地域事業者が社会課題解決型ビジネス(CSVモデル)を探求し、持続可能な成長を実現する経営文化を育むことです。一企業の利益だけでなく、社会全体の利益を考える経営者を増やしていきたいのです。
三つ目は、人材と技術の供給です。マイスター高等学院や職人起業塾を通じて、将来の地域のインフラを支える、高い技術と誇りを持つ「作り手」を安定的に供給し続けることです。技術の継承と人材育成は、地域の持続可能性に直結する重要な取り組みです。
これらの活動は、地域経済、人材育成、そして暮らしの質のすべてに影響を与えます。私たちの目標は、地域社会全体が次世代に誇りを持って引き継げる「いい街」であり続けることを確約することです。
それは決して簡単なことではありません。多くの時間と労力、そして継続的な投資が必要です。しかし、私たちは未来への責任を果たすために、この挑戦を続けていきます。
私たち株式会社四方継は、これからも「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」という理念のもと、地域社会と共に歩んでまいります。一人ひとりができることは小さくても、みんなで力を合わせれば大きな変化を生み出すことができます。一緒に「いい街を継ぐ」取り組みを進めていきましょう。