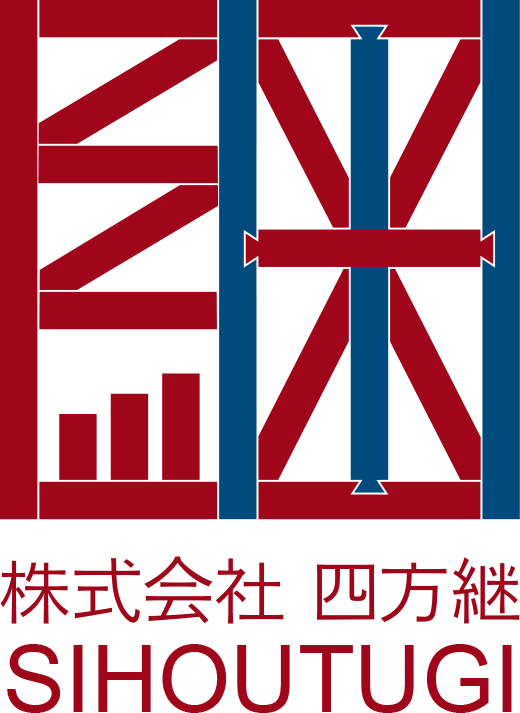はじめに:私たちが掲げる「四方良し」という理念
私たち株式会社四方継が事業活動の核として掲げる「四方良し」。これは単なる企業のスローガンではありません。「人、街、暮らし、文化を継ぎ」、持続可能な社会を実現するための強い信念です。
この「四方」とは、作り手、住み手、協力会社、そして地域社会の四者を指します。一般的な企業が自社の利益を最優先に考えるのに対し、私たちはこの四者すべてが幸せになり、利益を享受できる循環型のモデルを目指しています。
「でも、そんな理想論が本当に実現できるの?」そう思われる方もいらっしゃるでしょう。実際、私たちは2020年の社名変更時から本格的にこの理念の実現に取り組み、具体的な成果を上げてまいりました。
私たちが掲げる二つのビジョン、「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」と「人を繋ぎ、ご縁を紡ぎ、いい街を継ぐ」は、この四方良しの理念を実現するための具体的な行動指針となっています。
この理念を実現するために、私たちは建築事業(つむぎ建築舎)、地域ネットワーク事業(つない堂)、人材育成事業(職人起業塾、マイスター高等学院)という多岐にわたる事業を展開しています。これらの事業が有機的に連携することで、四つの主体を結びつけているのです。
本記事では、作り手、住み手、協力会社、地域社会それぞれに対する私たちの具体的な取り組みと、それらがどのように相互作用し、強固なネットワークを築いているかを詳しくご紹介します。
住み手の幸せを実現する「つむぎ建築舎」の取り組み
住み手、つまりお客様の価値創造は、四方良しの中心的な要素です。この役割を担うのが、木と暮らしをデザインし実現する技術者集団「つむぎ建築舎」です。
受け継がれる価値のある家づくり
つむぎ建築舎の最大の特徴は、世代を超えて受け継がれる価値ある建築を実現することです。「家は買い替えるものではなく、代々受け継ぐもの」という考え方のもと、設計段階から深い配慮を払っています。
具体的には、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションを通じて、住まい手の要望を丁寧に汲み取ります。ここで重要なのは、単にお客様の要望を聞くだけでなく、専門家として提案・計画から施工プロセスまでを「見える化」することです。
「見える化」とは、建築の専門知識がないお客様にも、どのような工事が行われているかを分かりやすく説明することを指します。これにより、お客様は安心して家づくりをお任せいただけるのです。
高性能住宅への先進的な取り組み
時代の要求に応じた先進的な住宅性能の提供も、住み手への価値創造の重要な要素です。2012年には、私たちの高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
ゼロエネルギー住宅とは、太陽光発電などで作り出すエネルギーと、家で消費するエネルギーがほぼ同じになる住宅のことです。これにより、光熱費を大幅に削減でき、環境にも優しい暮らしが実現できます。
また、同年には現代生活における重要な課題である電磁波対策にも取り組み始めました。スマートフォンやWi-Fi機器が普及する現代において、電磁波による健康への影響を心配される方も多いため、この取り組みは住み手の安心安全に直結します。
手の届く夢の実現
「すべての人に夢のマイホームを」を合言葉に、2007年には規格化注文住宅「sumika(スミカ)」の開発・販売事業をスタートしました。規格化注文住宅とは、ある程度決まった設計パターンから選択することで、コストを抑えながらも注文住宅の良さを味わえる住宅のことです。
これにより、手の届きやすい価格帯で高品質な住まいを提供し、より多くの方々の暮らしを豊かにしています。「家を建てたいけれど予算が心配」という方にとって、この取り組みは大変心強いものとなっています。
建てた後の安心も保証
住宅を建てることだけでなく、その後の生活の安心・安全を保証することも、住み手に対する四方良しの重要な要素です。
2009年には「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しました。このサービスは神戸近郊のエリアに限られますが、地域に根差した工務店として、建てた後の長期にわたる責任を果たす姿勢を示しています。
さらに、暮らしそのものを豊かにする取り組みとして開講した「すみれ暮らしの学校」は、私たちの社名変更を機に「つない堂」の活動へと移行し、より広範な地域活動として発展しています。これは単に箱物としての住宅を提供するのではなく、「暮らし」そのものを豊かにすることを目指す、文化を継ぐ取り組みの一環です。
作り手の誇りと技術を育む人材育成事業
建築技術を未来へ継承し、高品質なものづくりを可能にするためには、作り手である職人の育成と地位向上が不可欠です。四方良しの理念において、作り手が誇りとやりがいを持って働ける環境を整備することは、住み手の満足に直結します。
モノづくりの担い手を憧れの職業へ
私たちの代表である高橋剛志は、「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」を目標に掲げています。現在の日本では、職人という仕事に対するイメージが必ずしも良いとは言えません。「きつい、汚い、危険」といった3Kのイメージが強く、若者が敬遠する傾向があります。
しかし、職人は高い技術と誇りを持つ素晴らしい職業です。私たちは、この認識を変えるため、多角的な人材育成事業を展開しています。
職人起業塾による実践的な学び
2013年、社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的に「職人起業塾」を開講し、次世代を担う職人育成を本格的にスタートさせました。
職人起業塾の特徴は、単に技術を教えるだけでなく、イントラプレナーシップ(社内起業家精神)の醸成を重視していることです。これは職人の独立開業を進めるものではなく、組織の中で自律的に考え、行動できる人材を育成することを目指しています。従来の職人は技術は優秀でも、経営的視点や事業への参画意識が十分でないことがありました。しかし、この塾では「技術力」と「経営マインド」の両方を身につけることができます。
2016年には、職人、現場実務者向け研修事業を法人化し、一般社団法人職人起業塾として全国展開を果たしました。このカリキュラムは、2015年にJBN京阪神木造住宅協議会の研修事業として半年間の研修プログラムとして実施された実績を持ちます。
さらに2014年には、台北に菫菫室内装修設計工程有限公司を設立し、職人支援事業をスタートさせています。これは職人の活動領域を広げ、技術を国際的に継いでいくための取り組みです。
精神性と技術の両立
私たちの代表・高橋は技術だけでなく、仕事への向き合い方や生きる目的といった「常態」の理にじっくりと向き合うことの重要性を伝えています。「人生を変える体験が人生を変える」という言葉のとおり、職人として働くことの意味や価値を深く考えることを促しているのです。
また、ネパールに生きる日本人から投げられた問い「誰が為に生きるか」の考察を促すなど、単なる技術者ではなく、社会に貢献する人材としての成長を支援しています。
マイスター高等学院による未来の担い手育成
現代社会における加速する「職人不足」に歯止めをかけるため、2023年4月、私たちはマイスター高等学院を設立しました。
マイスター高等学院は通信制高校として、生徒が高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における「職人」としての技術を身につけることを可能にしています。通常の高校では隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる学校として、将来建築業界を担う人材の育成に貢献しています。
「勉強は苦手だけど、手を動かすことは得意」という生徒にとって、この学校は新たな可能性を開く場所となっています。作り手を育成し、その技術と精神を継承することは、「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」を持続可能にするための、四方良しの中核的な活動なのです。
地域の絆を深める「つない堂」と「継塾」の役割
私たちの理念「四方良し」を実現する上で、協力会社や地域社会との連携は最も重要な要素の一つです。この連携は単に工事を共に行う関係に留まらず、地域全体が安心で持続可能になるための「信頼のネットワーク」を築くことを意味します。
つない堂が目指す「検索不要の社会」
「つない堂」のビジョンは、「検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。現代社会では何か困ったことがあると、まずインターネットで検索することが当たり前になっています。しかし、検索結果には信頼できない情報も含まれており、時には詐欺や悪質な業者に引っかかってしまうこともあります。
つない堂が目指すのは、そんな検索に頼る必要がないほど、地域内の人、事業所、サービスが信頼でき、情報が共有されている社会です。「○○で困った時は△△さんに相談すれば大丈夫」といった、顔の見える関係性を大切にしています。
つない堂では、あらゆる分野で卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘し、それらを結びつけるリアルなネットワークを構築しています。また、信頼を軸に人と人を繋ぎ、ご縁を紡ぐために、積極的な情報発信、共有を行うメディアとしての機能も担っています。
継塾による社会課題解決型ビジネスの推進
「継塾」は、地域社会の課題解決とビジネスの持続可能性を追求する場で、協力会社や地域の事業所との連携を深める具体的な機会を提供しています。
継塾では、今日のビジネスにおいて重要とされるCSVモデル(社会課題解決ビジネス)に焦点を合わせ、地域ビジネスの刷新やブラッシュアップを行っています。CSVとは「Creating Shared Value」の略で、企業が利益を追求すると同時に、社会の課題も解決するビジネスモデルのことです。
偶数月の継塾では、「ホットシート」と呼ばれるダイアログ形式が採用されています。これは、熱い席に座った参加者のビジネスモデルを刷新、ブラッシュアップさせるためのものです。参加者全員が具体的な経営課題や社会貢献のあり方について深く関与し、共に解決策を考えます。
具体的な事例と成果
2025年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏がプレゼンターとして登壇することが予定されています。これは業種の壁を超えた地域連携と学びの場を提供する好例です。
また、2025年3月の継塾では、「持続可能なビジネスモデル探求」をテーマとし、「『常態』全ての成果の元になる理」にじっくりと向き合う機会を提供しました。これは理念や原理原則を共有し、協力会社を含めた全員が同じ質の高い基準で事業に取り組むことを促します。
このような継塾の活動を通じて、私たちは協力会社や地域の事業所を単なる取引先としてではなく、地域社会の価値を共創し、継承していくパートナーとして深く結びつけています。
私たちの歩みと理念の深化
私たちが現在の「四方良し」の理念に到達するまでには、地域に根差し、常に事業の質を高めてきた長い歴史があります。この歩みを振り返ることで、理念がどのように形成されてきたかをご理解いただけるでしょう。
創業から元請への転換
1994年、神戸市西区大津和にて大工集団「高橋組」として創業しました。当初は大手住宅メーカーの特約工務店として活動していました。特約工務店とは、特定の住宅メーカーと契約を結び、その会社の住宅を建設する工務店のことです。
2002年に有限会社すみれ建築工房を設立し、一般建設業の許可を取得、新築工事の受注を開始しました。そして2003年、リフォーム事業に進出した際、職人による直接施工が大きな反響を呼びました。
これまでは住宅メーカーからの依頼で工事を行うことが多かったのですが、この時期から元請中心の営業に転換し、職人の技術力を直接お客様の満足につなげる体制を確立しました。この転換は、「作り手」の価値を最大限に引き出す上で重要な一歩となりました。
専門性の向上と事業拡大
2005年に2級建築士設計事務所登録を行い、確認申請業務、設計業務の充実を図りました。確認申請業務とは、建築基準法に適合した建物かどうかを行政機関に確認してもらう手続きのことです。この業務を自社で行えることで、住み手に対してより専門的で包括的なサービスを提供できるようになりました。
2007年には店舗設計、マネジメント提案の研究を兼ねて飲食事業部を設立しています。これは一見、建築業とは関係ないように思えますが、実際に店舗を運営することで、店舗設計の実用性や使い勝手を身をもって体験し、より良い設計につなげるという狙いがありました。
さらに2012年にはマーケティング事業部を設立するなど、常に新しい視点から事業運営の知見を深めてきました。マーケティングとは、お客様のニーズを把握し、それに応える商品やサービスを提供する活動のことです。
理念の結実と社会的評価
2022年、私たちは一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されました。これは地域社会の課題解決と持続可能な未来に向けた取り組みが高く評価された結果です。
そして創立20周年を機に、2020年、社名を「株式会社四方継」に変更しました。この社名には、「人、街、暮らし、文化を継ぎ『四方良し』を実現する」という理念のもと、地域を守り次世代に継なげる事業を目指すという強い決意が込められています。
これらの歩みすべてが、現在の「四方良し」を実現するための強固な土台となっているのです。単なる建築会社から、地域社会の未来を創造する企業へと発展してきた私たちの歴史は、理念が単なる理想ではなく、実践に基づいて築かれてきたことを物語っています。
四方良しが創り出す持続可能な未来
私たちが目指す「四方良し」は、単なる建築サービスを超えた、信頼と連携の複合的なエコシステム(生態系)の構築にあります。これまで見てきたように、四つの主体がそれぞれに価値を受け取り、同時に他の主体にも価値を提供する循環型のモデルが実現されています。
四者の相互作用による価値創造
住み手には、つむぎ建築舎が高品質な建築技術と永続的な安心を提供し、世代を超えて受け継がれる暮らしの価値を保証しています。作り手には、マイスター高等学院と職人起業塾が、高い技術と誇りを持つ未来の担い手を育成し、技術と文化の継承を確実なものとしています。
協力会社と地域社会は、つない堂と継塾をハブとして、信頼を軸にご縁を紡ぎ合い、安心安全で持続可能な地域社会を共創しています。この四者が密接に結びつき、相互に価値を高め合うことで、私たちのビジョンである「いい街を継ぐ」ことが実現されています。
地域課題への具体的なソリューション
私たちが提示する「四方良し」のモデルは、現代の地域社会が直面する様々な課題に対する具体的なソリューションでもあります。
職人不足という課題に対しては、マイスター高等学院や職人起業塾を通じて、次世代の担い手を育成しています。地域経済の衰退という課題に対しては、つない堂や継塾を通じて地域内の経済循環を促進し、地域企業の活性化を図っています。
高齢化社会における住宅の維持管理という課題に対しては、無料巡回メンテナンスサービスを通じて長期的なサポートを提供しています。このように、四方良しの理念は現実的な課題解決力を持っているのです。
企業経営における新しいモデル
私たちの取り組みは、これからの企業経営における地域との共存共栄の理想的な形を示しています。従来の企業経営では、利益の最大化が最優先課題とされることが多くありました。しかし、私たちは利益も大切にしながら、同時に地域社会全体の価値向上を目指しています。
これは「三方良し」で有名な近江商人の理念を現代版にアップデートしたものと言えるでしょう。「売り手良し、買い手良し、世間良し」に「作り手良し」を加えることで、現代の社会課題により適応したモデルを構築しています。
私たちは神戸市西区に拠点を置き、定休日(水曜日)を除く9:00から18:00まで営業し、地域に深く根差しつつ、この理想の実現に向けて日々挑戦を続けています。その取り組みは、他の地域や企業にとっても参考となる貴重な事例となることを願っています。
まとめ:四方良しが示す未来への道筋
私たちの「四方良し」の理念とその実現方法について詳しくご紹介してまいりました。この取り組みが示すのは、企業が地域社会の一員として、単なる利益追求を超えた価値創造を行うことの可能性です。
作り手、住み手、協力会社、地域社会の四者すべてが幸せになる。これは理想論に聞こえるかもしれませんが、私たちの具体的な事業活動を通じて、現実のものとして実現されています。
建築という仕事を通じて、人と人とを繋ぎ、技術と文化を継承し、地域社会全体の持続可能性を高める。このような企業経営のあり方は、これからの時代により一層重要になってくるでしょう。
私たち四方継の挑戦は続いています。そしてその挑戦が成功すればするほど、「いい街を継ぐ」というビジョンの実現に近づいていくのです。私たちと共に、この「四方良し」の理念を実践し、持続可能な未来を創造していきませんか。