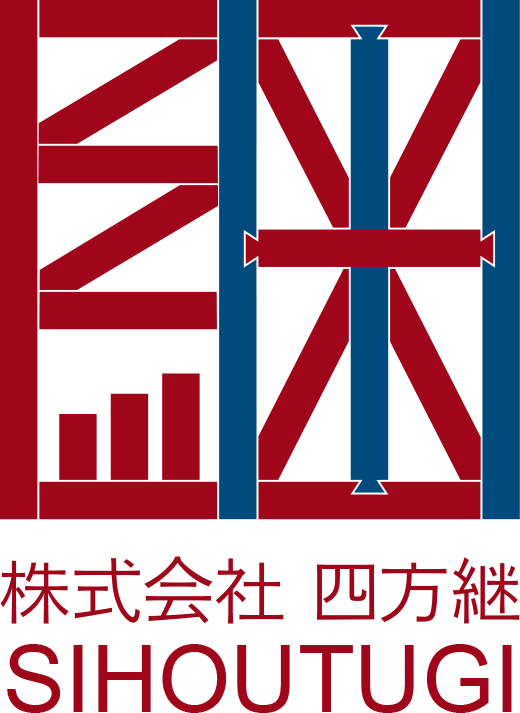はじめに:「継ぐ」という言葉に込められた深い意味
神戸市で建築業を営む私たち株式会社四方継(しほうつぎ)の社名には、単なる建設業を超えた壮大な理念が込められています。
「人、街、暮らし、文化を継ぎ『四方良し』を実現する」
この理念における「継ぐ」という行為は、ただ古いものを保存することではありません。現在において最善を尽くし、未来の世代が安心して豊かに生きられる基盤を築き上げ、確実に手渡していくという、強い責任感と未来志向を伴った挑戦なのです。
私たちが考える「四方良し」とは、作り手、住み手、協力会社、地域社会という四つの立場の人々すべてが満足し、恩恵を受け続けることです。この考え方により、「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」と「人を繋ぎ、ご縁を紡ぎ、いい街を継ぐ」という二つのビジョンを実現しようとしています。
本記事では、四方継の理念がどのように具体的な事業活動に反映されているのか、その全貌を詳しく解説していきます。建築業界の常識を覆す革新的な取り組みから、地域社会への貢献まで、私たちの挑戦を通じて、真の「継承」とは何かをお伝えします。
人と文化を継ぐ:未来の職人を育てる革新的な取り組み
職人起業塾:イントラプレナーシップの醸成
私たちが最も力を入れているのが、未来の「作り手」となる職人の育成です。どれほど優れた設計図や高品質な材料があっても、それらを形にする職人の技術と情熱がなければ、本当に価値のあるものづくりは実現しません。
2013年、四方継は「職人起業塾」を開講しました。この塾の特徴は、職人一人ひとりが社内起業家精神(イントラプレナーシップ)を持ち、自律的に価値を創造できるよう支援することにあります。
誤解されがちですが、職人起業塾は職人の独立開業を促進するものではありません。むしろ、組織の中で起業家のように考え、行動する人材を育成することを目的としています。従来の職人は、与えられた仕事を淡々とこなす「作業者」として位置づけられることが多くありました。しかし、私たちが目指すのは、自ら課題を発見し、解決策を提案し、価値を創造できる「プロフェッショナル」としての職人です。
職人起業塾では「技術×経営マインド」の両面から指導を行い、職人が自分の仕事の価値を正当に評価し、組織全体の成長に貢献できるよう育成しています。技術力だけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、コスト意識など、総合的なビジネススキルを習得することで、職人が単なる「手」ではなく、「頭脳」としても機能できるようになります。
この取り組みは大きな反響を呼び、2016年には一般社団法人職人起業塾として法人化され、全国展開されるまでに成長しました。代表者である高橋剛志は「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にする」という壮大な目標を掲げ、職人の社会的地位向上に取り組んでいます。
マイスター高等学院:教育から変える建築業界
建築業界が直面する最も深刻な問題の一つが「職人不足」です。若い世代の建設業離れが進み、熟練職人の高齢化により、技術の継承が困難になっています。
この構造的な問題に根本から取り組むため、私たちは2023年4月に「マイスター高等学院」を開校しました。これは、通信制高校の仕組みを活用し、高校卒業資格を取得しながら建設技術を学べる画期的な教育システムです。
一般的な高校教育では見過ごされがちな、ものづくりへの適性や情熱を持つ生徒たちに、早い段階から専門技術に触れる機会を提供します。学術的な基礎教育と実践的な技術習得を同時に行うことで、将来の建築業界を支える人材を質の高いレベルで育成することが可能になります。
この学院の設立は、私たちが掲げる「人と文化を継ぐ」という理念の具現化であり、建築業界の未来を変える重要な一歩といえるでしょう。
人生を変える体験の提供
私たちは「人生を変える体験が人生を変える」という信念を持っています。この考えに基づき、職人起業塾やマイスター高等学院では、単なる技術習得にとどまらず、参加者の人生観や価値観を変える体験を重視しています。
職人起業塾の参加者の中には、組織内で新しいプロジェクトを提案し実現させた事例や、従来のやり方を改善して生産性を大幅に向上させた事例が数多く報告されています。また、自分の技術に誇りを持ち、子どもたちに胸を張って職業を語れるようになったという声も寄せられています。
これらの成功事例は、職人という職業の社会的価値を高め、業界全体のイメージアップにも貢献しています。私たちの人材育成への投資は、個人の成長を支援するだけでなく、建築業界全体の文化的変革を推進しているのです。
暮らしを継ぐ:住み手の未来と安心への責任
つむぎ建築舎:丁寧なものづくりの実践
私たちのサービス部門である「つむぎ建築舎」は、「暮らしを継ぐ」という理念を具現化する中心的な役割を担っています。つむぎ建築舎は単なる設計・施工業者ではなく、「木と暮らしをデザイン、実現する技術者集団」として位置づけられています。
最も特徴的なのは、「住まい手がまだ気づいていない、知らない望みを形にする」ことを使命としている点です。これは、お客様の表面的な要望に応えるだけでなく、その奥にある本質的なニーズを見つけ出し、それを実現する技術力と洞察力を要求する高度なサービスです。
つむぎ建築舎では、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションを重視しています。女性ならではの生活感覚と、職人ならではの技術的な視点を組み合わせることで、住まい手の真のニーズを引き出すことができるのです。
SUMIKA-ZERO:未来を見据えた住宅性能
2012年、私たちは高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」を開発し、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
ゼロエネルギー住宅とは、住宅が消費するエネルギーと創るエネルギーの収支がゼロになる住宅のことです。つまり、光熱費がほぼかからない住宅を実現できるということです。SUMIKA-ZEROの特徴として、高断熱・高気密性能により冷暖房効率を最大化し、太陽光発電システムによる再生可能エネルギーを活用します。さらに、エネルギー管理システム(HEMS)による消費電力の見える化と、長期優良住宅の基準を満たす耐久性を確保しています。
これらの技術により、住み手は長期間にわたって快適で経済的な暮らしを営むことができます。また、環境負荷の低減にも貢献し、持続可能な社会の実現に寄与しています。
長期サポート体制:建てた後も続く安心
私たちが他社と大きく異なる点の一つが、建築後のサポート体制です。2009年から「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しています。
このサービスでは、定期的に専門スタッフが住宅を訪問し、建物の状態をチェックします。小さな不具合も早期に発見し、適切なメンテナンスを行うことで、住宅の価値と機能を長期間維持することができます。
ただし、地理的な制約により、無料巡回エリアは神戸近郊に限定されています。それでも、このような長期サポート体制を整備していることは、私たちが建物を単なる商品ではなく、未来に継承すべき資産として捉えていることを示しています。
街を継ぐ:地域社会との信頼関係構築
つない堂:検索不要の安心社会を目指して
現代社会では、何かサービスを探すときにインターネット検索に頼ることが当たり前になっています。しかし、検索結果の信頼性には限界があり、本当に良いサービスを見つけることは簡単ではありません。
私たちの「つない堂」は、この問題に対する革新的な解決策を提案しています。つない堂のビジョンは「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
具体的には、卓越した知見の発掘として、あらゆる分野で優れた技術や知識を持つ人、事業所、サービスを発掘します。次に、リアルなネットワーク構築として、発掘した要素を基に、実際の人間関係に基づくネットワークを構築します。そして、情報発信とメディア機能として、積極的な情報発信を行い、信頼を基盤として人と人を繋ぐメディアとしての役割を果たします。
2020年の社名変更を機に、「すみれ暮らしの学校」で展開していた住環境、食、学びを通じた暮らしの豊かさを追求する活動も、つない堂に統合されました。これにより、建物というハードウェアだけでなく、そこで営まれる生活そのものを豊かにする取り組みが、より体系的に展開されるようになりました。
循環型地域社会のハブ機能
つない堂が目指すのは、インターネット検索に依存しない、リアルな信頼関係に基づく地域社会の実現です。これは、地域の様々な事業者や専門家が相互に連携し、お客様のニーズに応じて最適なサービスを紹介しあう仕組みです。
例えば、住宅の建築を検討している方に対して、つない堂は単に四方継のサービスを紹介するだけでなく、お客様の具体的なニーズに応じて、最適な設計士、職人、インテリアコーディネーター、庭師などを紹介します。
このような仕組みにより、お客様は複数の業者を自分で探し回る必要がなく、最初から信頼できるプロフェッショナルのサービスを受けることができます。また、事業者同士も相互紹介により、新たなビジネスチャンスを得ることができます。
地域経済の活性化への貢献
つない堂の活動は、地域経済の活性化にも大きく貢献しています。大手チェーン店や全国規模の企業ではなく、地域に根ざした中小企業や個人事業主を積極的に紹介することで、地域内での経済循環を促進しています。
この取り組みにより、地域の雇用創出、税収増加、コミュニティの結束強化など、様々な効果が期待されます。私たちは、単に自社の利益を追求するのではなく、地域全体の発展に貢献することで、長期的な企業価値の向上を目指しているのです。
継塾:持続可能なビジネスモデルの探求
CSVモデルへの取り組み
私たちは定期的に「継塾」を開催し、持続可能なビジネスモデルの探求を続けています。継塾では、特にCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)モデルに焦点を当てた議論が行われています。
CSVとは、企業が社会課題の解決に取り組むことで、社会価値と経済価値の両方を創造するビジネスモデルのことです。従来のCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)が「慈善活動」的な側面が強かったのに対し、CSVは事業そのものが社会課題の解決に貢献する点で異なります。
実践的な事例研究
継塾では、実際の企業事例を通じてCSVモデルの可能性を探求しています。例えば、令和7年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏がプレゼンテーションを行いました。
この回では、「ホットシート」という手法を用いて、参加者全員で川内氏の事業モデルをブラッシュアップする議論が展開されました。ホットシートとは、一人の参加者が「熱い席」に座り、その人の事業課題について参加者全員で解決策を考える対話形式のセッションです。
このような実践的な議論を通じて、参加者は理論だけでなく、実際のビジネス現場で活用できる知識とノウハウを習得することができます。
継続的学習と改善の文化
継塾の開催は、四方継が学習し続ける組織であることを示しています。急速に変化する社会情勢の中で、従来のビジネスモデルが通用しなくなる可能性は常にあります。
継塾では、外部の専門家や異業種の経営者を招いて多様な視点を取り入れることで、固定観念にとらわれない柔軟な発想を促進しています。また、参加者同士の議論を通じて、新たなアイデアやビジネスチャンスを発見する場としても機能しています。
この継続的な学習と改善の取り組みにより、私たちは時代の変化に対応しながら、「四方良し」の理念を維持し続けることができているのです。
四方継の歩み:理念の確立に至るまで
創業から現在まで:挑戦と成長の軌跡
株式会社四方継の歴史を振り返ると、一貫して「継承」への思いが根底に流れていることがわかります。1994年、私たちは神戸市西区大津和にて「大工集団 高橋組」として創業しました。
当初は大手住宅メーカーの特約工務店として活動していましたが、2003年にリフォーム事業に進出したことが大きな転換点となりました。職人による直接施工が顧客から高い評価を受け、元請中心の営業スタイルへと移行することができました。
この成功体験により、私たちは職人の技術と信頼を核とする経営方針を確立しました。大手メーカーの下請けとして量をこなすのではなく、職人一人ひとりの技術を活かした質の高いサービスを提供することで、差別化を図ったのです。
事業拡大と専門性の向上
2005年には2級建築士設計事務所登録を行い、設計能力の向上を図りました。また、2007年には規格化注文住宅「sumika」の開発・販売を開始し、事業領域を拡大しました。
これらの取り組みにより、私たちは単なる施工業者から、設計から施工、アフターサービスまでを一貫して提供する総合的な住宅サービス企業へと成長しました。
社名変更:理念の体現
2020年、創立20周年を迎えた私たちは、「株式会社四方継」へと社名を変更しました。この社名変更は、単なるブランディングの変更ではなく、「人、街、暮らし、文化を継ぎ『四方良し』を実現する」という理念を明確に表明する重要な決断でした。
社名に込められた「四方継」という言葉には、作り手、住み手、協力会社、地域社会という四つの方向すべてに価値を継承していくという強い意志が表現されています。
この社名変更により、これまでの職人起業塾(2013年開講)、つない堂の活動などが、一つの明確な理念の下に統合され、より強力なメッセージとして発信されるようになりました。
まとめ:四方継が未来に託す価値
私たち株式会社四方継の取り組みを通じて見えてくるのは、建築業界における新しい価値創造の可能性です。私たちが実践する「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」は、目に見える建物だけでなく、それを支える人材、技術、地域コミュニティ、持続可能な経営モデルなど、多層的な要素を含んでいます。
私たちは四つの領域で未来への責任を果たしています。人の継承では、マイスター高等学院と職人起業塾を通じて、技術力と経営マインドを兼ね備えた次世代の職人を育成し、建築文化の継承を図っています。街の継承では、つない堂をハブとして地域の信頼ネットワークを構築し、検索に依存しない安心安全な循環型地域社会の実現を目指しています。暮らしの継承では、つむぎ建築舎がゼロエネルギー住宅SUMIKA-ZEROと長期メンテナンスサービスを通じて、住み手の豊かな暮らしを長期間保証しています。文化の継承では、継塾での継続的な学習と対話を通じて、社会課題解決型のビジネスモデルを探求し、「四方良し」の理念を次世代に引き継ごうとしています。
これらの取り組みは、建築業界だけでなく、あらゆる業界の企業が参考にできる価値創造のモデルといえるでしょう。私たちの挑戦は、企業が短期的な利益追求を超えて、長期的な社会価値の創造に貢献できることを示しています。
真の「継承」とは、過去の遺産を単に保存することではなく、現在の知恵と技術を総動員して、未来世代がより豊かに生きられる基盤を築くことです。四方継の理念と実践は、私たち一人ひとりが自分の仕事や生活において、どのような価値を未来に継承していくべきかを問いかけています。私たちはこれからも、「四方良し」の実現に向けて、地域の皆様とともに歩み続けてまいります。