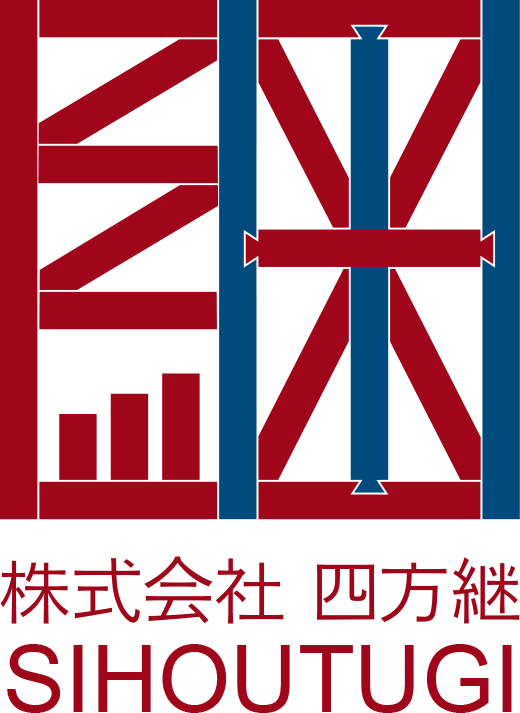はじめに:四方継という名前に込めた想い
株式会社四方継。私たちの社名を初めて聞かれた方は、少し不思議に思われるかもしれません。
「しほうつぎ」と読むこの名前には、私たちの事業に対する深い想いが込められています。「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」——これが私たちの理念です。
「四方良し」とは何か。作り手である私たち、住み手であるお客様、協力いただく関係会社の皆様、そして地域社会。この4つの要素すべてが満足し、幸せになれる状態を意味します。近江商人の「三方よし」をさらに発展させた考え方と言えるでしょう。
1994年、私たちは「大工集団 高橋組」として神戸でスタートしました。そして2020年、これまで培ってきた想いをより明確に表現するため、社名を「四方継」に変更いたしました。この変更は、単なる名称変更ではありません。私たちが本当に大切にしてきた「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」という理念を、社名として明示する決意の表れです。
建築という仕事は、ただ建物を造ることではありません。世代を超えて価値を持ち続け、関わるすべての人々に恩恵をもたらすものを創り出すこと。私たちはそう考えています。
つむぎ建築舎:住まい手の想いを紡ぐ
潜在的な願いを形にする対話
私たちのサービス部門である「つむぎ建築舎」では、お客様の潜在的な願いを形にすることを何より大切にしています。
「潜在的な願い」とは何でしょうか。
たとえば、お客様が「広いリビングが欲しい」とおっしゃったとします。もちろん、ご要望通りに広いリビングを設計することはできます。しかし私たちは、そこで立ち止まります。なぜ広いリビングが欲しいのか。そこでどんな時間を過ごしたいのか。10年後、20年後、ライフスタイルはどう変わっていくのか。
私たちが大切にしているのは、こうした深い部分まで掘り下げる対話です。
実際にあったお話をご紹介しましょう。
若いご夫婦が「子育てに適した家を建てたい」とご相談にいらっしゃいました。当初のご要望は、子ども部屋の配置や安全な動線など、まさに「子育て仕様」の住まいでした。
しかし、女性建築設計士が何度も丁寧にお話を伺う中で、本当の想いが見えてきました。
「子どもが巣立った後も、夫婦二人で豊かに暮らせる家にしたい」「将来、両親を迎え入れる可能性もある」「地域の方々との交流も大切にしたい」
こうした本音を引き出すことで、私たちは単なる子育て住宅ではなく、人生の変化に柔軟に対応できる「成長する家」をご提案できました。お引き渡しから数年が経ちましたが、今でも「あのとき深く話を聞いてもらえて本当に良かった」とおっしゃっていただけます。
見える化で生まれる安心と愛着
私たちは、施工プロセスの「見える化」も徹底しています。
建築工事は専門的で難しいもの。お客様には分からない世界——。そんな常識を、私たちは変えたいと考えています。
工事中、お客様には現場を自由に見学していただけます。大工が実際に木を刻む様子、使用する材料の一つひとつ、職人たちの仕事ぶり。すべてをご覧いただき、気になることがあればいつでもお尋ねください。
この透明性には大きな意味があります。住まい手であるお客様が建築の過程を理解し、安心して見守ることで、完成した家への愛着はより深まります。そして、どのような想いで作られた家なのかを知ることで、その価値をお子様やお孫様にも伝えやすくなるのです。
引き渡し後も続く関係
2009年から本格化した無料巡回メンテナンスサービスは、私たちの「継ぐ」理念を象徴する取り組みです。
神戸近郊のお客様には、定期的に無料巡回を実施し、小さな不具合も早期に発見・対応しています。「建物は完成がスタート」——これが私たちの考え方です。
人間の体と同じように、建物も時間とともに変化します。適切なケアを続けることで、本当に長く愛される住まいになる。だからこそ、引き渡し後の関係を私たちは大切にしています。
お客様からは「何かあったらすぐに相談できる安心感がある」「長く付き合える工務店を選んで良かった」といったお声をいただいています。
技術革新で実現する快適と持続可能性
SUMIKA-ZERO:未来を見据えた住まい
2012年、私たちが開発したSUMIKA-ZERO(スミカゼロ)が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。これは、私たちにとって大きな誇りです。
ゼロエネルギー住宅とは、年間のエネルギー消費量がゼロになる住宅のこと。高い断熱性能と省エネ設備、そして太陽光発電などの創エネ設備を組み合わせることで実現します。
私たちがSUMIKA-ZEROで目指したのは、単に省エネ性能が高いだけの家ではありません。住み心地の良さ、快適性も同時に追求しています。夏は涼しく、冬は暖かい。一年を通じて湿度も適切にコントロールされる。そんな環境が、電気代の節約とともに手に入ります。
快適な室内環境は、住む方の健康にも良い影響を与えます。特にお子様やご高齢の方がいらっしゃるご家庭では、その効果を実感していただくことが多いようです。
目に見えない配慮:電磁波対策
同じく2012年から、私たちは電磁波対策にも取り組んでいます。
現代の生活に電気製品は欠かせません。しかし、それに伴う電磁波の影響を気にされる方も増えています。特に長時間過ごす住まいでは、可能な限り電磁波を軽減したいとお考えになるのは自然なことです。
私たちは、配線計画の段階から電磁波の発生を抑える工夫を行います。また、必要に応じて電磁波をカットする建材の使用もご提案します。
これらは目に見えない部分への配慮かもしれません。しかし、ご家族の健康と安全を長期的に守るという意味で、「受け継がれる価値」の重要な要素だと私たちは考えています。
職人起業塾:建築業界の未来を創る
社内起業家精神を育む取り組み
2013年にスタートした「職人起業塾」は、私たちの先見性を示す取り組みとして、今も誇りを持って続けています。
建築業界では職人不足が深刻な問題です。若い世代が建築の職人を目指さなくなった理由の一つは、職人という仕事の将来性に対する不安があるからだと考えています。
職人起業塾は、技術者に独立開業を促すものではありません。私たちが目指しているのは「イントラプレナーシップ」——社内起業家精神の醸成です。
一人ひとりの職人が、単に指示された仕事をこなすのではなく、自ら考え、提案し、新しい価値を生み出す。そんな主体的な姿勢を持てるよう、経営的な視点やマーケティングの知識も含めた研修を行っています。
職人起業塾で学んだ仲間たちは、それぞれの現場で新しいアイデアを出し、お客様により良い提案ができるようになりました。自分の仕事に誇りを持ち、より高い品質を追求する姿勢も生まれています。
この取り組みが評価され、2016年には一般社団法人職人起業塾として法人化され、全国展開に至りました。私たちが蒔いた種が、日本全国で花開いていることを嬉しく思っています。
マイスター高等学院:新しい教育の形
2023年4月、私たちの教育への想いが形になったマイスター高等学院が開校しました。
この学院では、高校卒業の資格を取得しながら、大工をはじめとする建設業の職人技術を身につけることができます。勉強と実技の両方を学べる通信制高校です。
従来の教育システムでは、「勉強が得意な子は大学へ、手に職をつけたい子は専門学校や就職へ」という流れが一般的でした。しかし私たちは、「手に職をつけることも立派な学問」という新しい価値観を提示したいと考えています。
実際に入学した生徒さんからは、「勉強は苦手だったけど、木を扱う作業は本当に楽しい」「将来は自分の工務店を持ちたい」といった声を聞いています。
代表の高橋剛志が目指すのは「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」です。マイスター高等学院は、その実現に向けた重要な一歩なのです。
つない堂:地域社会との深いつながり
検索不要の安心安全な地域社会
私たちのもう一つの核となる事業が「つない堂」です。
現代社会では、何かサービスを探すときにインターネット検索を使うのが当たり前になっています。しかし、検索結果に出てくる情報が本当に信頼できるかどうかは、実際に利用してみないと分からないことが多いでしょう。
つない堂が目指すのは「検索不要の安心安全な地域社会」です。
具体的には、地域内で優れた技術や知識を持つ人、事業所、サービスを発掘し、リアルなネットワークでつなげます。そして、実際の体験に基づいた情報を共有することで、信頼できる情報が地域内で循環する仕組みを作ります。
「安心できる医院を探している」「信頼できる電気屋さんを知りたい」「美味しいパン屋さんはどこ?」——こうしたニーズに対して、実際にサービスを利用した地域の方々の声をお届けします。
実は、私たちは以前「すみれ暮らしの学校」という活動を行っていました。2020年の四方継への社名変更を機に、この活動はつない堂に移行し、より広範な地域活動として発展させています。
地域経済を支える循環の仕組み
この取り組みの背景には、「良い建物は良い地域があってこそ価値を持つ」という考えがあります。
いくら素晴らしい家を建てても、周りの地域が衰退してしまっては、その価値も失われてしまう。だからこそ、私たちは地域全体を豊かにする活動にも力を入れているのです。
つない堂の活動は、地域経済の活性化にも貢献しています。大手チェーンではなく、地域に根ざした事業者を積極的に紹介することで、地域内でお金が循環する仕組みを作っています。
たとえば、つない堂を通じてご紹介した地元の家具工房で家具をオーダーされたお客様がいらっしゃいます。その家具工房は地元の木材を使用し、地元の職人が手作りしています。お客様は愛着のある家具を手に入れ、工房は売上を得て、木材業者も潤う。この循環が地域全体を豊かにしているのです。
継塾:学び続ける組織であるために
私たちは「継塾」と呼ばれる学びの場を定期的に開催しています。
2025年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏にプレゼンテーションをしていただきました。テーマは「社会課題解決とビジネスの両立」でした。
一見すると建築とは関係のないテーマに思えるかもしれません。しかし、「社会課題を解決しながら事業として成り立たせる」という視点は、私たちの理念と深くつながっています。
継塾では、このような多様な視点からの学びを通じて、「丁寧なものづくり」の概念を常に時代に合わせて更新し続けています。業界の枠を越えた交流から得られる気づきが、私たちの事業をより豊かなものにしてくれるのです。
私たちが描く未来
四方良しの循環を生み出す
私たちの「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」は、単に長持ちする建物を作ることではありません。
それは、住む人が幸せになり、作る人が誇りを持ち、地域社会が豊かになり、その価値が次の世代にも受け継がれていく。そんな循環を生み出すことです。
建築技術の向上はもちろん、人材育成、地域ネットワーク構築、教育事業。これらすべての取り組みが「四方良し」という理念でつながっています。作り手である職人の地位向上、住み手の満足、協力会社との信頼関係、地域社会の発展。これらが好循環を生み出すことで、本当に持続可能な価値が生まれると私たちは信じています。
これからの挑戦
1994年に「大工集団 高橋組」として始まった私たちの挑戦は、今も続いています。
目先の利益や効率だけでなく、長期的な視点で物事を考える。自分たちだけでなく、関わるすべての人が幸せになる方法を探す。
これは簡単なことではありません。しかし、だからこそ追求する価値があると考えています。
住まいづくりを通じて、人々の暮らしを豊かにする。職人の育成を通じて、建築業界の未来を創る。地域のつながりを通じて、社会全体を元気にする。
私たち四方継は、これからも「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」を追求し続けます。そして、その想いに共感してくださるすべての方々とともに、より良い未来を築いていきたいと考えています。
住まいづくりをお考えの方、建築業界に興味をお持ちの方、地域での活動に関心がある方。どんな方でも構いません。私たち四方継の取り組みに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「人、街、暮らし、文化を継ぐ」——この理念を、一緒に実現していきましょう。