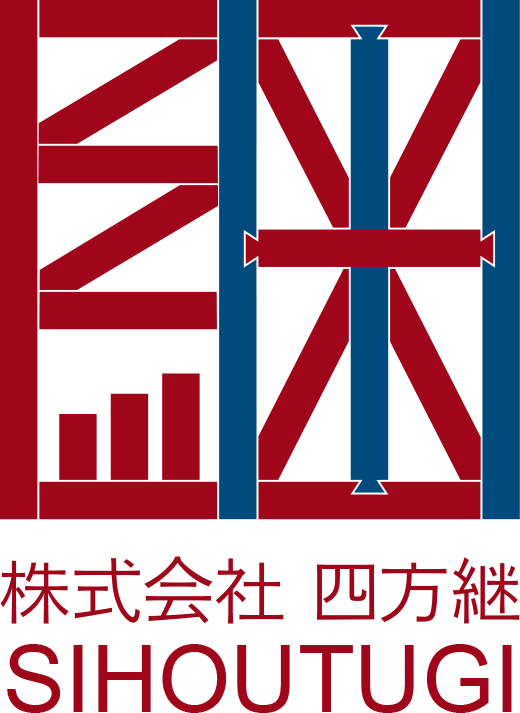はじめに:「継ぐ」という使命を胸に
私たち株式会社四方継は、「人、街、暮らし、文化を継ぎ四方良しを実現する」という理念のもと、日々事業に取り組んでいます。そんな私たちが最も重要視しているのは、モノづくりの担い手である職人を「子供たちの憧れの職業」にすることです。
なぜこのような目標を掲げるのでしょうか。それは、どれほど優れた設計図や技術があっても、それを形にする「人」がいなければ、未来に価値ある建物を残すことができないからです。
現在の建築業界では、職人不足が深刻な問題となっています。この問題は単なる労働力不足にとどまらず、世代を超えて受け継がれてきた貴重な技術と文化の断絶を意味しています。私たちはこの危機感を原動力として、革新的な教育事業にコミットし、職人という職業の地位向上に全力で取り組んでいます。
今回は、四方継がどのような取り組みを通じて「憧れの職業」化への挑戦を実現しようとしているのか、その詳細をお話しさせていただきます。
危機感から生まれた挑戦:建築業界が直面する現実
職人不足がもたらす深刻な影響
建築業界における職人不足は、もはや無視できない社会問題となっています。この問題の根底にあるのは、若者が建築関連の仕事を「きつい、汚い、危険」という3Kのイメージで捉えてしまい、進路として選択しなくなっていることです。
しかし、実際の建築現場では、最新の技術や安全対策が導入され、職人の技術力は以前にも増して高度になっています。にもかかわらず、社会的な評価や経済的な処遇が改善されていないため、優秀な若者が他の業界に流れてしまうという悪循環が続いているのです。
四方継の原点:大工集団高橋組時代から学んだこと
私たちの会社は、1994年に大工集団高橋組として創業しました。創業当初から、職人の高い技術力を事業の核として位置づけてきました。
特に印象深いのは、2003年にリフォーム事業に進出した際の経験です。職人による直接施工が顧客から大きな反響を呼び、元請中心の営業に転換することができました。この体験を通じて、職人の技術力と顧客との信頼関係こそが事業の生命線であることを深く実感したのです。
しかし、一企業の努力だけでは業界全体の構造的な課題を解決することはできません。そこで私たちは、職人という職業が社会的に尊敬され、経済的にも自立できる魅力的なキャリアパスであることを証明する必要があると考えました。これが、私たちの教育事業への本格的な取り組みの出発点となったのです。
職人起業塾:社内起業家精神を育む革新的プログラム
イントラプレナーシップの醸成を目指して
2013年、私たちは社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的として「職人起業塾」を開講しました。この取り組みは、次世代を担う職人育成の本格的なスタートを切る重要な一歩でした。
職人起業塾の最大の特徴は、単なる独立支援プログラムではなく、イントラプレナーシップ(社内起業家精神)の醸成を目的としている点です。私たちが目指したのは、職人一人ひとりが組織の中で主体的に価値を創造し、自らの仕事に誇りと責任を持つプロフェッショナルになることでした。
なぜこのようなアプローチを取ったのでしょうか。それは、職人が経営視点を持ち、顧客価値の創造を理解することで、自分の技術の社会的意義を認識し、より高い次元で仕事に取り組めるようになると考えたからです。独立を促すのではなく、組織の中で輝ける人材を育てることが、持続的な業界発展の鍵だと確信しています。
「人生を変える体験」の実現
私たちは「人生を変える体験が人生を変える」という信念を持っています。職人が自分のキャリアに対する主体性を持ち、経営的な視点から自分の仕事を捉え直すことで、技術に対する誇りと社会的な使命感が生まれます。
実際に職人起業塾を受講した社員からは、「自分の技術に対する見方が変わった」「経営の視点を持つことで、お客様との関係も良くなった」「仕事へのモチベーションが大きく向上した」といった声をいただいています。このような変化こそが、職人の地位向上につながり、結果として子供たちにとって「憧れの職業」となる道筋を開くのです。
全国展開への発展
職人起業塾の取り組みは地域社会で大きな反響を呼び、その重要性から職人育成事業は急速に拡大しました。
2015年には、JBN京阪神木造住宅協議会の研修事業として、半年間の研修カリキュラムを持つ職人起業塾を開講することになりました。業界団体との連携が深まったことで、私たちの教育ノウハウがより多くの職人に届くようになったのです。
さらに2016年には、職人・現場実務者向けの研修事業が法人化され、一般社団法人職人起業塾として全国展開に至りました。この全国展開は、四方継が持つ「人」を育成するノウハウと理念が、地域や業界を超えて共有されるべき普遍的な価値を持つことを証明する出来事でした。
マイスター高等学院:教育システムそのものを変革する挑戦
隠れた才能を開花させる新しい教育モデル
職人起業塾が現役職人のキャリアアップを担う一方で、私たちはより根本的な課題解決に向けた挑戦を始めました。それが、2023年4月に開校したマイスター高等学院の設立です。
マイスター高等学院は、「職人不足の世の中、通常の高校では隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる学校」として設立されました。
従来の教育システムでは、建築業界への参入は高校卒業後の進路選択の段階で、技術習得に特化するか学業を優先するかという二者択一を迫られることが多くありました。しかし、マイスター高等学院はこの障壁を取り払います。
学歴と専門技術の両立を実現
この通信制高校の最大の特徴は、生徒が高校卒業の資格を取得しながら、同時に大工など建設業における職人としての技術を身につけることができる点です。
これにより、若者は学歴と専門スキルを同時に手に入れることができ、社会的な選択肢を狭めることなく、誇りを持ってモノづくりの道に進むことができるようになります。
実際に、マイスター高等学院の生徒たちは、一般的な高校生と同じように大学受験の選択肢も残しながら、職人としての実践的なスキルも習得しています。このような柔軟性こそが、モノづくりの道を「将来性のある魅力的な選択肢」として位置づけることにつながっているのです。
未来創造企業としての責任の具現化
マイスター高等学院の設立は、建築業界の職人不足に歯止めをかけ、将来の建築業界を担う人材を育成することを目的としています。これは、私たちが2022年に認定された「未来創造企業」としての責任を具現化したものでもあります。
未来創造企業認定とは、革新的な技術やサービスによって社会課題の解決に取り組み、持続的な成長を目指す企業を認定する制度です。私たちは、未来の建築業界の担い手を育成し、世に送り出すという使命を負っているのです。
高校生という早い段階から職人としてのキャリアに高い価値を持たせることで、「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」という目標は、より現実味を帯びてきます。技術と学問、社会的な地位がバランスよく提供されるこの教育モデルこそが、未来への「人」の継承の鍵となるのです。
四方良しの実現:地域社会との連携による好循環の創出
つない堂:信頼の輪を広げる地域ハブ
私たちの「モノづくりの担い手」育成への挑戦は、「四方(作り手、住み手、協力会社、地域社会)良し」という理念に基づき、他の分野と密接に連動しています。質の高い職人が育っても、彼らが信頼され、適切に評価される地域社会がなければ、その努力は報われないからです。
四方継の事業部門の一つである「つない堂」は、この土壌を耕す重要な役割を担っています。つない堂のビジョンは、「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
つない堂では、あらゆる分野で卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築しています。このネットワークを通じて、インターネット検索を必要としない安心な循環地域型社会のハブとなり、良い街を次世代に継ぐことを目指しているのです。
また、私たちが以前展開していた「すみれ暮らしの学校」の活動は、2020年の社名変更を機にこのつない堂の活動に統合され、より広範な地域コミュニティづくりの取り組みとして発展しています。
職人が活躍できる環境の整備
つない堂の取り組みは、職人が匿名的な市場ではなく、信頼を軸にした地域社会の中で活動できる環境を整備することにつながります。技術力の高い職人は、この信頼の輪の中で正当に評価され、安心して事業を継続できるようになるのです。
例えば、つない堂を通じて紹介された職人は、お客様との間に既に信頼関係の基盤があるため、価格競争に巻き込まれることなく、適正な価格で質の高いサービスを提供することができます。これにより、職人の経済的な安定が図られ、職業としての魅力が向上するという好循環が生まれています。
つむぎ建築舎:技術力の証明と価値の可視化
世代を超えて受け継がれる価値ある建築
職人が手掛けたものが「受け継がれる価値」を持つことで、その職業の社会的評価はさらに高まります。四方継の建築部門である「つむぎ建築舎」は、「木と暮らしをデザイン、実現する技術者集団」として、職人の技術の到達点を示す重要な役割を果たしています。
つむぎ建築舎では、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションと、専門家としての提案・計画から施工プロセスの見える化を通じて、世代を超えて受け継がれる価値ある建築を実現しています。
高性能住宅への取り組み
私たちの技術力の証明として特筆すべきは、2012年に開発した高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されたことです。
この認定は、私たちの職人が持つ技術力が、単なる伝統的な手法にとどまらず、最新の環境技術や省エネ技術と融合した高度なものであることを示しています。職人の仕事が「人の人生と未来を守る崇高な仕事」であることを体現する実例と言えるでしょう。
長期保証とメンテナンス体制
また、2009年から本格化した無料巡回メンテナンスサービスは、職人が作り出すものが長期にわたって住まい手の安心・安全と未来の暮らしを保証することを示しています。
このようなアフターサービスの充実は、職人の仕事が「作って終わり」ではなく、お客様の人生に長期間にわたって寄り添う責任ある仕事であることを明確に示しています。こうした姿勢こそが、職人という職業を子供たちの憧れの対象にする重要な要素なのです。
社名変更に込めた決意:理念の結晶化
「継ぐ」という使命の明文化
四方継が「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」を目指す挑戦は、2020年の社名変更によって、企業の正式なミッションとして結晶化しました。
創立20周年を機に、有限会社すみれ建築工房から株式会社四方継に社名変更した際、私たちは「人、街、暮らし、文化を継ぎ『四方良し』を実現する」の理念のもと、地域を守り次世代に継ぐ事業を目指すという決意を新たにしました。
この「人」の継承を最前線で担うのが、まさに職人育成事業なのです。社名変更は、職人起業塾の成功、高性能住宅の実現、地域ネットワーク構築のビジョンといった、これまでの取り組みすべてを「継ぐ」という普遍的な価値観のもとに統合し、未来への誓いを立てた瞬間でした。
未来創造企業としての認定
2022年の未来創造企業認定は、これらの取り組みが単なる建築業の改善にとどまらず、社会全体の未来に貢献する革新的な経営であることの証です。
この認定を受けたことで、私たちの取り組みが社会的に評価され、より多くの方々に知っていただく機会が増えました。これにより、職人という職業に対する社会的な認識も徐々に変わってきていることを実感しています。
今後の展望:持続可能な好循環の実現に向けて
継塾での新たな挑戦
私たちの理念を実現するための重要な仕組みの一つとして「継塾」があります。継塾では、持続可能なビジネスモデルの探求をテーマとし、CSVモデル(社会課題解決型ビジネス)に焦点を合わせた議論を行っています。
CSVモデルとは、Creating Shared Value(共有価値の創造)の略で、企業が社会課題の解決に取り組みながら、同時に経済的な価値も創造するビジネスモデルのことです。私たちの職人育成事業は、まさにこのCSVモデルの実践例と言えるでしょう。
次世代への継承システムの完成
私たちが目指すのは、「人」の育成を通じて「文化」を継承し、それが「暮らし」を支え、最終的に「街」の持続的な繁栄を保証するという、壮大な循環システムの完成です。
この循環システムが機能することで、職人という職業は単なる労働力提供の仕事から、社会の持続的発展に欠かせない専門職へと位置づけが変わっていくはずです。
まとめ:憧れの職業への道筋は着実に
私たち株式会社四方継の挑戦は、職人の地位向上という一分野にとどまらず、四方すべてが満たされる「四方良し」の状態を目指す、未来を見据えた経営そのものです。
「人生を変える体験が人生を変える」という信念のもと、私たちはこれからも、モノづくりの担い手が誇りを持ち、未来の子供たちが目を輝かせて憧れる魅力的な職業文化を創造し、次世代に継承し続けます。
職人不足という社会課題の解決は一朝一夕にはいきませんが、私たちの取り組みを通じて、確実に変化の兆しが見えてきています。マイスター高等学院の生徒たちが将来的に地域の建築業界を支える担い手となり、職人起業塾で学んだ職人たちが組織の中核として活躍する。そんな未来を実現するために、私たちは歩みを止めることなく挑戦を続けてまいります。
この挑戦が成功すれば、日本のモノづくりの伝統と技術は確実に次世代に継承され、子供たちにとって職人は「憧れの職業」となることでしょう。その日が来ることを信じて、私たち四方継は今日も前進し続けています。