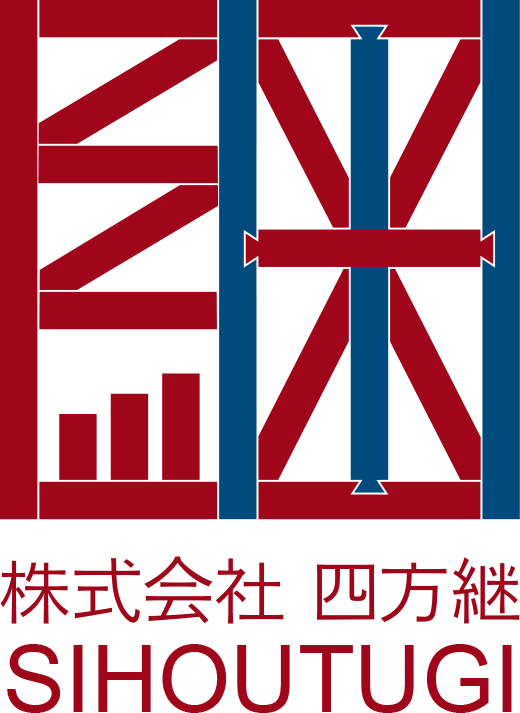こんにちは。株式会社四方継です。
1994年の創業から2025年で31年。私たちは神戸市西区大津和で「大工集団 高橋組」として産声を上げて以来、常にお客様と地域社会に支えられながら、成長を続けてまいりました。今日は、私たちがどのような想いで歩んできたのか、そして未来に向けてどんな夢を描いているのかをお話しさせていただきます。
1994年、職人としての誇りを胸に
神戸市西区大津和で始まった物語
1994年、神戸市西区大津和で「大工集団 高橋組」が誕生しました。文字通り「大工さんの集団」として、大手住宅メーカーの特約工務店として実績を積み重ねる日々。朝早くから現場に出て、一つひとつの家を丁寧に作り上げていく。私たちの原点は、そんな職人としての誇りに満ちた現場にあります。
当時の私たちが何より大切にしていたのは、「いいものを作る」という職人としての基本姿勢でした。手を抜かない、妥協しない、お客様に心から喜んでいただける家を建てる。シンプルですが、これこそが私たちの価値観の根幹です。
特約工務店として大手住宅メーカーと協力した時期は、技術力だけでなく、工期管理、安全性の確保、コミュニケーション能力など、様々なスキルを習得できた貴重な修行期間でした。この経験が、後に独立して事業を展開する際の確かな土台となりました。
2003年、革命的な転換:職人による直接施工
お客様と職人が直接つながる喜び
2002年に有限会社すみれ建築工房として法人化し、新築工事の受注を開始。そして2003年、私たちの運命を変える大きな決断をしました。リフォーム事業への進出です。
この挑戦で、私たちは驚くべき発見をしました。職人が直接お客様とコミュニケーションを取り、直接工事を行うスタイルが、予想以上に大きな反響をいただいたのです。
従来の建築業界では、お客様と職人の間に営業担当者や現場監督など複数の人が入ることが一般的でした。しかしこの方式では、中間マージンによるコストの増加や、伝言ゲームのようにお客様の想いが正確に伝わらないという課題がありました。
私たちの直接施工は、これらの問題を一気に解決しました。お客様の要望を直接伺い、専門家としてのアドバイスを直接お伝えし、責任を持って工事を完成させる。このシンプルで誠実なやり方に、多くのお客様から信頼をいただくことができました。
この経験から学んだのは、「作り手」と「住み手」が直接コミュニケーションを取ることで生まれる信頼関係の大きな価値です。これが、現在の私たちの理念である「四方良し」の考え方の出発点となりました。
技術革新への挑戦:環境と快適性の両立
SUMIKA-ZEROの開発
2012年、私たちが開発した高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」が、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
大工集団として始まった私たちが、最先端の住宅技術を開発し、国レベルで評価されたことは、本当に誇らしい出来事でした。SUMIKA-ZEROは、省エネルギーで地球環境に優しく、同時に住む人にとって快適で健康的な住環境を提供します。夏は涼しく、冬は暖かく、一年中快適に過ごせる住まいです。
同じく2012年から、私たちは電磁波対策にも本格的に取り組み始めました。現代社会では様々な電子機器に囲まれて生活しています。便利な機器が発する電磁波が人体に与える影響を真剣に考え、可能な限りその影響を軽減し、お客様とご家族の健康を守ることを心がけています。
お客様との長期的な関係を大切に
2009年からは、「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しました。(※無料巡回エリアは神戸近郊に限らせていただいています)
家は建てて終わりではありません。長い年月をかけて、お客様の暮らしを支え続ける存在です。定期的な点検とメンテナンスを通じて家の状態をチェックし、必要に応じて修繕や改良を行う。これが、私たち大工集団としての責任だと考えています。
職人起業塾:イントラプレナーシップの醸成
2013年、建築業界の未来を見据えて
2013年、私たちは新しい挑戦を始めました。「職人起業塾」の開講です。
このきっかけは、建築業界が抱える深刻な課題への危機感でした。職人の高齢化、若い人たちの職人離れ、技術の継承問題。このままでは、日本が誇る建築技術が失われてしまうかもしれません。
私たちの代表である高橋剛志が掲げたのは、「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にする」という壮大な目標でした。職人という仕事には、自分の手で美しいものを作り上げる喜び、お客様に心から感謝される満足感、技術を極めることで得られる成長実感、そして人々の暮らしを豊かにするという社会的意義があります。
社内起業家精神を育む研修
職人起業塾の特徴は、単に技術を教えるだけでなく、「イントラプレナーシップ」すなわち社内起業家精神を醸成する研修であることです。
従来の職人教育との大きな違いは、独立開業を促すのではなく、組織の中で主体的に考え、行動できる人材を育成することに重点を置いている点です。技術力に加えて、経営的な視点や問題解決能力を持った職人が育つことで、建築業界全体のレベルアップにつながります。
2016年には、この職人起業塾の活動が一般社団法人として法人化され、全国展開を開始しました。神戸で始めた小さな取り組みが、全国の職人さんたちの役に立つようになったことは、私たちにとって大きな喜びでした。
マイスター高等学院:次世代の職人を育てる
2023年、教育事業への本格参入
2023年4月、私たちはさらに大胆な挑戦を開始しました。「マイスター高等学院」の開校です。これは通信制高校でありながら、建設業における職人としての技術を身につけることができる、日本でも珍しい教育機関です。
現在の建築業界は、深刻な職人不足に直面しています。ベテランの職人さんたちが次々と引退していく一方で、新しく職人の道を選ぶ若い人たちが不足しているのです。この問題を解決するため、私たちは行動を起こす必要があると考えました。
隠れた才能を発見し、育てる
マイスター高等学院の最大の特徴は、従来の学校教育では見つけにくい「隠れた才能」を発見して育てることです。
手先が器用で、ものづくりが得意で、集中力があって、責任感が強い。そんな職人向きの才能を持った若者たちを早い段階で発見し、高校卒業と同時に一人前の職人として社会に送り出すことを目指しています。
この学院は単なる職業訓練校ではありません。高校という正式な教育機関で職人を育てることで、職人という職業の社会的地位を根本から変えることを目的とした、革命的な教育機関なのです。
つむぎ建築舎:職人精神の現代的進化
木と暮らしをデザインする技術者集団
現在の私たちのサービス部門である「つむぎ建築舎」は、1994年の大工集団としてのアイデンティティを現代に進化させた形です。
「木と暮らしをデザイン、実現する技術者集団」という表現には、単に家を建てるのではなく、お客様の人生に寄り添い、世代を超えて愛され続ける住まいを創造するという私たちの使命が込められています。
女性建築設計士と大工の協働
つむぎ建築舎の特徴の一つは、女性建築設計士と大工が密に連携して、お客様とコミュニケーションを取ることです。
女性の設計士は、暮らしに関する細やかな視点を持っています。子育て、家事、家族のコミュニケーションなど、日常生活の中で本当に大切なことを理解しています。一方、大工は実際の施工に関する専門知識を持っています。この二つの専門性が組み合わさることで、美しくて住みやすくて、長持ちする家を実現できるのです。
私たちは家づくりのプロセスを可能な限り「見える化」することを大切にしています。定期的な現場見学会の開催、工程ごとの詳細な報告、写真や動画による記録の共有など、様々な方法でお客様に安心していただける体制を整えています。
つない堂:信頼の輪を地域社会に広げる
検索不要の安心安全な地域社会を目指して
地域に根ざした大工集団として長年活動してきた私たちは、地域社会での信頼できる事業者やサービスを見つけることの難しさという課題に気づきました。
インターネットで検索すれば情報はたくさん出てきますが、その中から本当に信頼できる相手を見つけるのは簡単ではありません。そこで私たちが始めたのが「つない堂」という取り組みです。
2020年の社名変更を機に、それまでの「すみれ暮らしの学校」の活動を発展させ、つない堂として本格的に展開を開始しました。
リアルなネットワークによる信頼関係の構築
つない堂のコンセプトは、「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
私たちが長年の経験を通じて知り合った、本当に信頼できる事業者やサービス提供者をネットワーク化し、地域の皆様にご紹介する仕組みです。建築以外の分野でも、例えば医療、教育、介護、法律、金融など、様々な分野で優秀な専門家とのネットワークを構築しています。
良い街とは、住民同士が信頼し合い、支え合って暮らせる街です。困った時に頼れる人がいて、専門的なアドバイスが必要な時に相談できる相手がいる。そんな安心感のある地域社会を次世代に残すこと。これが、私たちの理念である「街を継ぐ」ことの具体的な実践なのです。
継塾:持続可能な未来を共に学ぶ
CSVモデルの探求
私たちは「継塾」という勉強会を定期的に開催しています。これは地域の事業者の皆様と一緒に、持続可能なビジネスモデルについて学び合う場です。
特に力を入れているのが、CSVモデル(社会課題解決型ビジネス)の研究です。CSVとは「Creating Shared Value」の略で、企業が利益を追求しながら同時に社会課題の解決にも貢献するビジネスモデルのことです。
2025年3月の継塾では、「『常態』全ての成果の元になる理にじっくりと向き合ってみませんか?」というテーマで議論しました。「常態」とは、継続可能な状態のこと。一時的な成功ではなく、長期にわたって安定して価値を提供し続けられる状態を指します。
異業種との協働
継塾の面白いところは、建築業以外の様々な業種の方々にも参加していただいていることです。令和7年6月には、ゴミ収集運搬業のCSVモデルについて議論しました。一見すると建築業とは関係ないように思えますが、地域社会にとって不可欠な事業という点では共通しています。
こうした異業種との交流を通じて、私たち自身も新しい発見や学びを得ることができます。
四方良しの理念:すべての関係者が幸せになる経営
2020年、新しい決意を込めた社名変更
2020年、私たちは創立20周年を機に、有限会社すみれ建築工房から株式会社四方継へと社名を変更しました。
「四方継」という社名には、「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」という私たちの理念が込められています。
「四方良し」とは、近江商人の「三方良し」(売り手良し、買い手良し、世間良し)をさらに発展させた考え方で、お客様、従業員、協力会社、地域社会のすべてが幸せになることを目指す経営哲学です。
作り手、住み手、協力会社、地域社会の調和
具体的には、以下の四つの「良し」を実現することを目標としています。
「作り手良し」:私たちスタッフが誇りを持って働き、技術を向上させ、経済的にも安定できること。
「住み手良し」:お客様が心から満足できる住まいを手に入れ、長期にわたって快適に暮らせること。
「協力会社良し」:一緒に仕事をする協力会社の皆様も適正な利益を得て、持続可能な経営ができること。
「地域社会良し」:私たちの活動が地域社会の発展に貢献し、次世代により良い環境を残せること。
2022年、私たちは「未来創造企業」として認定をいただきました。1994年に大工集団として始まった私たちが、未来を創造する企業として認められたことは、本当に感慨深い出来事でした。
原点から未来へ:変わらない想い
振り返ってみると、私たちの根本的な価値観は1994年の創業時から全く変わっていません。
「いいものを作りたい」「お客様に喜んでもらいたい」「技術を大切にしたい」「誠実でありたい」。これらの想いは、31年前も今も、そして未来も変わることはありません。
変わったのは、その想いを実現するための方法や規模です。最初は一つひとつの家を丁寧に建てることから始まり、今では業界全体や地域社会全体に影響を与える活動まで展開しています。
現在の私たちの事業は、住宅建築、リフォーム、職人育成、教育事業、地域ネットワーク構築、経営研究など非常に多岐にわたります。一見すると多様に見えますが、すべては1994年の大工集団としての職人精神から派生したものです。
「いいものを作る」→「技術を継承する」→「職人を育てる」→「業界全体を良くする」→「地域社会に貢献する」という風に、自然な流れで事業が拡大していきました。
次の30年に向けて
これから30年後、2055年の私たちはどうなっているでしょうか。
きっと今は想像もつかない新しい技術や社会情勢の変化があることでしょう。でも、私たちの根本的な価値観は変わらないはずです。
その時代その時代の人々が求める「いいもの」を作り、「喜び」を提供し、「技術」を大切にし、「誠実」であり続ける。そして、次の世代により良い社会を残すために努力し続ける。
これが、株式会社四方継の未来への約束です。
1994年に神戸市西区大津和で産声を上げた「大工集団 高橋組」は、31年の歳月を経て、多くの皆様に支えられながら株式会社四方継として成長してまいりました。
この間、様々な挑戦と困難がありましたが、常に私たちの心の中にあったのは、創業時の職人としての誇りと、お客様に喜んでいただきたいという純粋な想いでした。
これからも、この想いを大切にしながら、「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」という理念のもと、皆様とともに歩んでまいります。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。