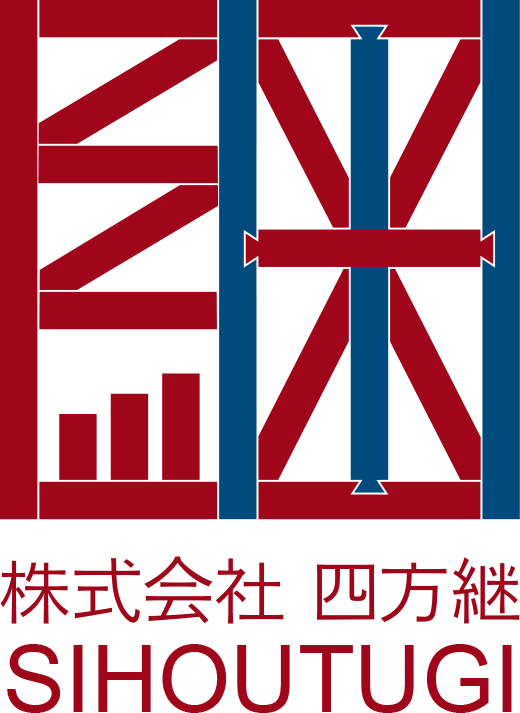はじめに
2020年、私たち株式会社四方継は創立20周年という大きな節目を迎えました。この年、私たちは「有限会社すみれ建築工房」から「株式会社四方継(しほうつぎ)」へと社名を変更する決断をいたしました。
この社名変更は、単なる名称の変更ではありません。私たちが目指す事業の方向性と、地域社会に対する責任を明確にするための、未来への約束でした。
新しい社名「四方継」には、「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という私たちの理念が込められています。この理念こそが、これからの私たちの事業活動すべての基盤となるものです。
本記事では、この社名変更に込めた想いと、「四方良し」という理念が私たちの事業活動にどのように反映されているのかを、具体的な事例を交えながらお伝えしていきます。
「四方良し」とは何か―近江商人の精神を現代に
「四方良し」という言葉を聞いて、「三方良し」を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。近江商人が大切にしていた「売り手良し、買い手良し、世間良し」という商売の精神です。
私たちは、この「三方良し」の精神を、現代の建設業と地域社会の持続可能性に適用し、さらに進化させた形として「四方良し」という考え方を打ち出しました。
具体的には、以下の四者が「良し」となることを目指しています。
まず一つ目は「作り手良し」です。これは私たち株式会社四方継と、共に働く職人たちのことを指します。職人が技術を磨き、誇りを持って仕事ができる環境を整えることが、良い建築を生み出す基盤となります。
二つ目は「住み手良し」です。私たちが建てる住まいに暮らすお客様、そして世代を超えてその住まいを受け継いでいくご家族のことです。長く安心して暮らせる住まいを提供することが、私たちの使命です。
三つ目は「協力会社良し」です。建築は決して一社だけでは成り立ちません。共に品質を支えるパートナー企業との健全な関係があってこそ、良い仕事ができます。
そして四つ目が「地域社会良し」です。私たちの拠点である神戸市西区を中心としたコミュニティ全体が豊かになることを目指しています。
この「四方良し」を実現することで、「地域を守り次世代に継なげる事業」を展開していく。それが私たちの使命だと考えています。
創業からの歩み―理念に辿り着くまでの26年
「四方良し」という理念は、突然生まれたものではありません。1994年に「大工集団 高橋組」として創業してから、長年にわたる試行錯誤の中で形作られてきたものです。
創業当初は、職人としての技術を活かした仕事を中心に行っていました。そして2002年、法人組織として「有限会社すみれ建築工房」を設立しました。
2003年にはリフォーム事業に本格的に進出しました。職人による直接施工が多くのお客様から反響をいただき、元請中心の営業体制へと転換していきました。この経験は、お客様と直接向き合うことの大切さを私たちに教えてくれました。
2007年には、規格化注文住宅「sumika(スミカ)」を開発しました。さらに店舗設計の研究も兼ねて飲食事業部を設立するなど、事業の幅を広げていきました。
そして2009年、私たちは「すべてのお客様に生活の安心・安全を」という合言葉のもと、無料巡回メンテナンスサービスを本格化させました。神戸近郊にお住まいのお客様を対象に、定期的に住まいの状態をチェックし、必要なメンテナンスをご提案するサービスです。
このメンテナンスサービスは、現在まで十数年にわたって継続しています。この長期的なアフターフォローの取り組みが、お客様との深い信頼関係を築く基盤となりました。
さらに2012年には、高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO」が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。環境性能の高い住まいづくりへの取り組みが、公的に評価された瞬間でした。
同じく2012年からは、電磁波への対策にも取り組み始めました。目に見えないリスクにも配慮し、住まい手の健康と安心を長期にわたって守りたいという想いからです。
このように、創業から26年間の歩みの中で、私たちは常にお客様と地域社会のことを考え、事業を展開してきました。その集大成として、2020年の社名変更と「四方良し」の理念が生まれたのです。
「人」と「文化」を継ぐ―作り手の育成への挑戦
「四方良し」の実現において、私たちが特に力を入れているのが「人」と「文化」の継承です。具体的には、技術と倫理観を持った職人を育成し、建築文化を次世代に継なげることです。
現在、建設業界は深刻な職人不足に直面しています。技術を持った職人の高齢化が進み、若い世代への技術継承が大きな課題となっているのです。
この課題に対して、私たちは2013年から「職人起業塾」という取り組みを始めました。当初は社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的としていましたが、2016年には一般社団法人として法人化し、全国展開にまで発展しました。
職人起業塾の目的は、単なる独立開業支援ではありません。「イントラプレナーシップ」という社内起業家精神の醸成を目指しています。イントラプレナーシップとは、組織に所属しながらも起業家のような高い当事者意識と経営的視点を持って働くことです。
職人が経営的な視点を持つことで、技術の継承と組織の専門性の維持を両立できると私たちは考えています。実際、この取り組みは多くの職人の成長につながり、業界全体の活性化にも貢献しています。
さらに2023年4月には、「マイスター高等学院」を設立・開校しました。これは通信制の高校で、高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における職人としての技術を身につけることができる、全国でも類を見ない教育システムです。
マイスター高等学院のコンセプトは「職人不足の世の中、通常の高校では隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる学校」です。学力試験だけでは測れない、ものづくりの才能を持った若者たちに、新しい道を提供したいという想いから生まれました。
また、私たちが継承したいのは技術だけではありません。職人の美意識や倫理観も、大切な「文化」として次世代に伝えていきたいと考えています。
例えば、愛知県の歯科クリニックの現場で見られた「木摺り(きずり)」という左官の下地作業があります。この木摺りは、最終的に左官の土で隠れてしまう部分ですが、その仕上がりは「隠れてしまうのがもったいないくらい」美しいものでした。
見えなくなる部分にも手を抜かない。この姿勢こそが、私たちが継ぎたい「文化」としての職人の心なのです。
また、お客様のワークデスク製作の際には、3×6判の合板1枚から、なるべく無駄のないように部材を取る「木取り」の技術を活かしました。これは資源を大切に使い、効率と品質を両立させる職人の知恵です。
このような技術と心を、次の世代に確実に継なげていくこと。それが私たちの「作り手良し」の取り組みです。
「暮らし」を継ぐ―世代を超えた安心の提供
「住み手良し」と「協力会社良し」の実現、これらは「暮らし」の継承につながります。お客様の生活の安心を保証し、その安心を支えるパートナー企業全体が健全であることが大切だと考えています。
私たちが提供する住まいは、単に今を快適に暮らせるだけでなく、将来にわたって安心して暮らし続けられることを重視しています。
例えば、現在私たちが推進している「GX志向型住宅」は、温室効果ガス排出削減と経済成長の両立を目指すものです。環境に配慮しながら、住まい手の生活の質も向上させる。これが持続可能な「暮らし」の基本だと考えています。
住宅プランにおいても、長期的な視点を大切にしています。最近では、老後を見据えた平屋が人気です。階段の上り下りがない生活は、年齢を重ねても快適に暮らし続けられる大きなメリットがあります。
また、共働き世帯が増える中で、日々の家事にかかる時間を減らすことも重要です。例えば、室内干しをメインとした間取りを推奨しています。天候に左右されず洗濯物を干せることで、日々の生活ストレスを大きく軽減できます。
このような設計の工夫は、単なる利便性の追求ではありません。長期的な生活の質を考え、何十年後も快適に暮らせる住まいを提供したいという、私たちの「暮らしを継ぐ」という責任感から生まれています。
さらに、「協力会社良し」の実現にも力を入れています。建築は多くの専門業者の協力があって初めて成り立つものです。協力会社との関係が健全でなければ、良い建築は生まれません。
私たちは偶数月に「継塾(つぐじゅく)」という研修会を開催しています。ここでは、ホットシート形式で参加者のビジネスモデルの刷新やブラッシュアップを行います。
例えば、令和7年6月の継塾では、ゴミ収集運搬業を営む企業にプレゼンを依頼しました。テーマは「今の時代に合わせたCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)に焦点を合わせる」ことでした。建築業界の枠を超えて、持続可能な社会づくりに貢献する知見を深める機会となりました。
また、令和7年3月の継塾では、「『常態』全ての成果の元になる理にじっくりと向き合ってみる」というテーマで、企業経営の持続可能性の基盤について探求しました。
このような取り組みを通じて、協力会社との関係は単なる取引関係を超え、共に「地域を守り次世代に継なげる事業」を担うパートナーシップへと発展しています。
「街」を継ぐ―地域活動拠点「つない堂」の役割
「四方良し」の中で最も広範な責任が「地域社会良し」です。私たちは、地域コミュニティを活性化し、未来の世代が安心して暮らせる環境を整えることを目指しています。
その中心的な役割を果たしているのが、地域活動拠点「つない堂」です。社名変更の理念を受けて、私たちは「つない堂」の活動を本格化させました。
「つない堂」のビジョンは、「あらゆる分野で卓越した知見を持つ『人』『事業所』『サービス』を発掘し、リアルなネットワークを構築する」ことです。そして「インターネット検索を必要としない安心安全な循環地域型社会のハブ」となることを目指しています。
現代は情報があふれる時代です。インターネットで検索すれば、あらゆる情報が手に入ります。しかし、その情報が本当に信頼できるものなのか、自分に合ったものなのかを判断するのは難しいものです。
「つない堂」では、実際に顔の見える関係の中で、信頼できる人や事業所、サービスをご紹介できる環境を作りたいと考えています。
具体的な活動として、情報誌「つないどう?」を発行しています。この情報誌を通じて、地域の様々な情報を発信・共有しています。
例えば、「能登半島輪島市黒島地区 伝統的建築物 修復レポート」という特集では、大工が泊まり込みで行った専門的な社会貢献活動を詳しくお伝えしました。このような活動を地域に共有することで、建築の仕事の意義や価値を知っていただく機会になります。
また、地域行政との連携も積極的に進めています。2025年9月には、「伊川リバーフェスタ」や「西区もくいく」に、西区役所の方からお声掛けをいただき参加しました。さらに、西区役所主催の「エニシミーツ」(E-NISHIと縁を掛けたネーミング)にも参加するなど、公的な場での活動も増えています。
次世代育成にも力を入れています。地域の子どもたちへの学習支援である「しずく学習塾」は、水曜日の授業日には募集人数いっぱいになるほどの人気です。子どもたちの学びを支援することで、地域の未来を育てています。
さらに「ちびっこ応援!木工教室」も定期的に開催しています。子どもたちに実際に木に触れ、ものづくりの楽しさを体験してもらう機会です。この取り組みには、「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすることを目指す」というビジョンが込められています。
これらの活動は、建築業の枠を超えて、地域の「街」「暮らし」「文化」を次世代へ確実に継承していくという、私たちの深いコミットメントを示すものです。
「未来創造企業」としての責任
2022年、私たち株式会社四方継は、一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されました。
この認定は、「地域を守り次世代に継なげる事業」という理念に基づき、職人育成、地域活性化、高性能住宅の提供といった多岐にわたる事業が、社会に持続的な価値を提供していることが評価されたものです。
私たちにとって、この認定は大きな励みであると同時に、より一層の責任を感じる出来事でもありました。「未来創造企業」という名に恥じない活動を続けていかなければならないという、新たな決意を抱きました。
会社概要においても、私たちの事業内容を「建築×地域活性化」と明確に定義しています。これは、建築(住み手、作り手、協力会社)と地域活動(地域社会)が、車の両輪として機能するという、理念に基づく事業構造そのものを表しています。
建築の仕事だけをしているのではない。地域活動だけをしているのでもない。その両方が一体となって、初めて「四方良し」が実現できる。そう私たちは考えています。
おわりに―社名に込めた永遠の約束
「株式会社四方継」という社名には、私たちの未来への約束が込められています。
「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」。この理念は、私たちが提供する建築が、世代を超えて受け継がれる価値を持つものであることを示しています。そして、私たちが地域社会の未来を担う一員であることを、永遠に約束するものです。
1994年の創業から30年以上、私たちは地域と共に歩んできました。多くのお客様との出会い、職人たちとの協働、地域の皆様とのつながり。その一つひとつが、今の私たちを形作っています。
これからも、私たちは「四方良し」の理念のもと、地域社会と共に成長し、豊かな未来を次世代に継なげるために邁進してまいります。
建築を通じて、そして地域活動を通じて、私たちにできることを一つひとつ積み重ねていく。それが、社名「四方継」に込めた私たちの決意です。
神戸市西区を拠点に、これからも地域の皆様と共に歩んでいきたいと考えています。私たち株式会社四方継の取り組みに、今後ともご注目いただければ幸いです。