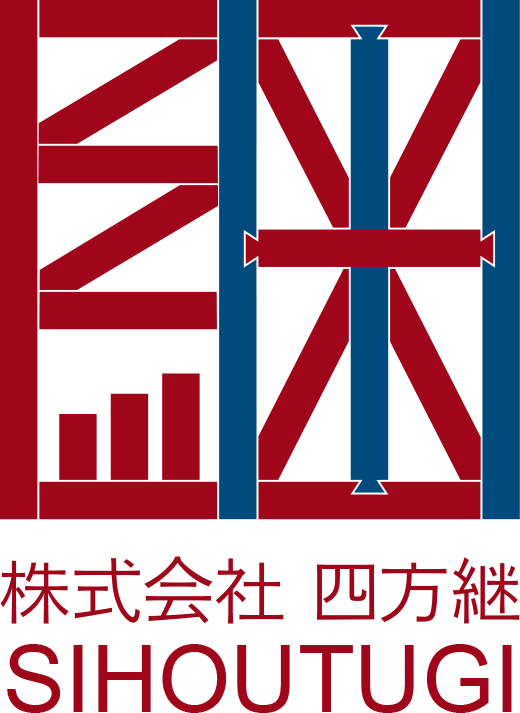こんにちは。株式会社四方継です。
2025年3月の継塾では「全ての成果の元になる理、『常態』にじっくりと向き合う」というテーマで、深い議論を重ねました。今回は、この「常態」という考え方について、私たちの事業活動と共にご紹介させていただきます。
「常態」とは何か?なぜ今、この概念に注目するのか
「常態」という言葉は、日常生活ではあまり使われないかもしれません。しかし私たちにとって、この概念こそが「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という経営理念の核心をなすものなのです。
一般的に「常態」とは「いつも通りの、安定した状態」を意味します。しかし当社が重視する「常態」には、より深い意味が込められています。それは「成果を生み出し続けるために必要な、揺るぎない基本的な状態や仕組み」を指しています。
たとえば、毎日ランニングを続けている人が健康を維持できるのは、偶然ではありません。日々走るという「常態」があるからこそ、健康という「成果」が継続的に生まれるのです。
当社の事業も同じです。優れた建築や地域貢献という「成果」は、偶然や一時的な努力から生まれるものではありません。日々の業務、考え方、仕組みが「常態」として整っているからこそ、継続的に良い結果を生み出すことができるのです。
2020年の社名変更以降、私たちは「継承」という使命を果たすため、一時的な成功や目先の利益に左右されることなく、持続的な価値創造を目指してきました。その実践の中で気づいたのが、この「常態」の重要性でした。
なぜ今、「常態」に注目するのか。それは、現代社会が「非常態」に陥りやすい環境だからです。情報が氾濫し、変化が激しく、短期的な結果ばかりが求められる時代。そんな中で、本当に価値のあるものを継続的に生み出すためには、しっかりとした「常態」の土台が不可欠なのです。
四方良しを実現する「常態」の実践
当社が目指す「四方良し」とは、作り手(職人)、住み手(お客様)、協力会社、地域社会の四者すべてが満たされる状態を指します。この四方良しを「常態」として維持することが、私たちの最大の目標です。
作り手の常態を整える
まず、作り手である職人の皆さんが、常に高い技術と誇りを持って働ける環境を整えることが重要です。
建築業界では「職人不足」が深刻な問題となっています。これは単に人数が足りないという問題ではなく、技術と文化の断絶を生む「非常態」です。
この課題に対し、当社は2013年から「職人起業塾」を開講しています。この塾は、職人の皆さんが単なる技術者ではなく、イントラプレナーシップ(社内起業家精神)を持った人材へと成長するための研修です。独立開業を促進するものではなく、既存の職人や社員大工のキャリアアップと、地域の職人の活性化を目的としています。技術だけでなく、経営的視点を身につけることで、職人の皆さんが自分の技術に誇りを持ち、適正な対価を得られる環境づくりを支援しているのです。
2016年には、この取り組みを一般社団法人職人起業塾として全国展開しました。当社の育成モデルが、地域社会全体、ひいては業界全体の「常態」を変革する力を持つことを示す試みです。
さらに2023年には「マイスター高等学院」という通信制高校を設立しました。ここでは、高校卒業の資格を取得しながら、大工など建設業における職人としての技術を身につけることができます。若い世代に職人という職業の魅力を伝え、高い技術を持つ職人の安定的な供給を「常態」とするための、教育インフラへの投資です。
代表の高橋が「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」を目指しているのも、職人という職業の地位を「常態」として向上させたいという強い思いの表れです。
住み手の安心を常態化する
次に、住み手であるお客様が、世代を超えて安心・安全に暮らせる環境を提供することも、重要な「常態」の一つです。
当社のサービス部門である「つむぎ建築舎」では、世代を超えて受け継がれる価値ある建築を実現しています。
ここで大切にしているのが「見える化」です。建築のプロセスを透明にし、お客様に分かりやすく説明することで、安心感を提供しています。専門家としての提案・計画から施工プロセスまで、すべてを可視化することで、曖昧さや手抜きを許さない「常態」を確立しています。女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションも、お客様のニーズを深く理解し、まだ気づいていない望みまで形にするための基盤となっています。
また、2009年からは無料巡回メンテナンスサービスを本格化しています。これは「すべてのお客様に生活の安心・安全を」という合言葉のもと、建築後のサポートを一時的なものではなく、「常態」のサービスとして提供しているものです。
2012年には、高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。これは、当社が環境性能と快適性を「常態」として提供できる技術力を持つことの証明でもあります。
地域社会との信頼関係を常態化する
四方良しの実現には、地域社会や協力会社との信頼関係も欠かせません。
この役割を担うのが「つない堂」です。つない堂のビジョンは「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
現代社会では、インターネットで何でも検索できる便利さがある一方で、本当に信頼できる情報や人を見つけるのが難しくなっています。これは、ある意味「非常態」と言えるでしょう。
つない堂では、あらゆる分野で卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築しています。そして、積極的な情報発信や共有を行うメディアとなり、信頼を軸に人と人を繋ぎ、ご縁を紡いでいます。
2020年の社名変更を機に、それまでの「すみれ暮らしの学校」の活動は、このつない堂に引き継がれました。地域との関わり方をさらに発展させ、より広範囲な信頼のネットワークを構築する体制へと進化したのです。
このネットワークが機能することで、地域社会は検索を必要としない安心な循環型社会のハブとなり、「いい街を次世代に継ぐ」という「常態」を確立できると考えています。
継塾で探求する持続可能なビジネスモデル
当社が運営する「継塾」は、持続可能なビジネスモデルを探求する場です。ここでも「常態」にじっくり向き合うことを大切にしています。
CSVモデルという新しい考え方
継塾では、特にCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)に焦点を当てて議論を行っています。
CSVとは「Creating Shared Value(共有価値の創造)」の略で、企業が社会的な課題解決を事業の核に据えることで、持続的な成長と社会貢献を両立させるという考え方です。
これは、まさに当社が実践している「理」に基づいたビジネスモデルです。職人育成による職人不足の解決、地域ネットワーク構築による地域の安心安全の実現など、当社の事業はすべてCSVの実践と言えます。
外部事例から学ぶ姿勢
令和7年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏にプレゼンをしていただきました。
ここでは「ホットシート」という手法を使って、ビジネスモデルを刷新・ブラッシュアップさせるためのダイアログ(対話)を行いました。社会課題解決と事業成長の両立について、参加者全員で深く議論することができました。
このように、外部の事例に学び、自社の「常態」を常にブラッシュアップする姿勢も、未来創造企業として認定された当社の重要な特徴です。
継続的な内省と対話の文化
「常態」にじっくり向き合うことは、単なる業務改善ではありません。全ての成果の元になる「理」を深く理解し、その理から外れないように行動する経営文化を確立することなのです。
理にかなった「常態」を築くには、自社の成功体験や既存のやり方に固執せず、常に批判的かつ建設的な対話を続ける必要があります。
継塾では、偶数月にホットシートを設けるなど、継続的な内省と外部との対話を「常態」として組み込んでいます。これにより、常に新鮮な視点を保ち、時代の変化に対応できる柔軟性を維持しているのです。
人材育成に込める想い
当社が特に力を入れているのが人材育成です。なぜなら、すべての成果の元になる「常態」は、それを実現する「人」の質によって大きく左右されるからです。
職人起業塾では、技術だけでなく、経営者としての視点も身につけられます。イントラプレナーシップを醸成することで、職人の皆さんが自分の技術に誇りを持ち、組織の中で主体的に価値を創造できるようになることを目指しています。
マイスター高等学院は、将来建築業界を担う人材の育成を目的とした通信制高校です。若い世代に職人という職業の魅力を伝え、高い技術を持つ職人の安定的な供給を「常態」とするための、長期的な投資です。
つむぎ建築舎での「見える化」の実践も、人材育成の一環です。プロセスにおける曖昧さを排除し、お客様に安心感を提供する文化を「常態」化することで、職人一人ひとりが責任と誇りを持って仕事に取り組む環境を作り上げています。
このような取り組みを通じて、職人という「人」が常に成長し、誇りを持って働ける環境を「常態」化することで、結果として最高の建築品質という「成果」が継続的に生まれる「理」を実現しているのです。
まとめ:常態の追求が未来を創る
当社が追求する「常態」は、単なる業務の標準化や効率化とは異なります。それは、作り手、住み手、協力会社、地域社会の四者すべてが、理にかなった状態で共存共栄し続けること、すなわち「四方良し」そのものなのです。
この「常態」を維持し、次世代に手渡すことこそが、未来創造企業としての当社の終わりのない使命だと考えています。
現代社会は変化が激しく、短期的な結果が求められがちです。しかし、本当に価値のあるものを継続的に生み出すためには、しっかりとした「常態」の土台が必要です。
当社は今後も、職人起業塾やマイスター高等学院による人材育成、つない堂による地域ネットワークの構築、そして継塾による持続可能なビジネスモデルの探求を通じて、この「常態」を磨き続けてまいります。
そして、「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という理念のもと、次世代に受け継がれる価値ある仕事を続けていく所存です。
皆様も、ご自身の仕事や生活の中で、どのような「常態」を大切にされているでしょうか。一度じっくりと向き合ってみることで、新たな発見があるかもしれません。