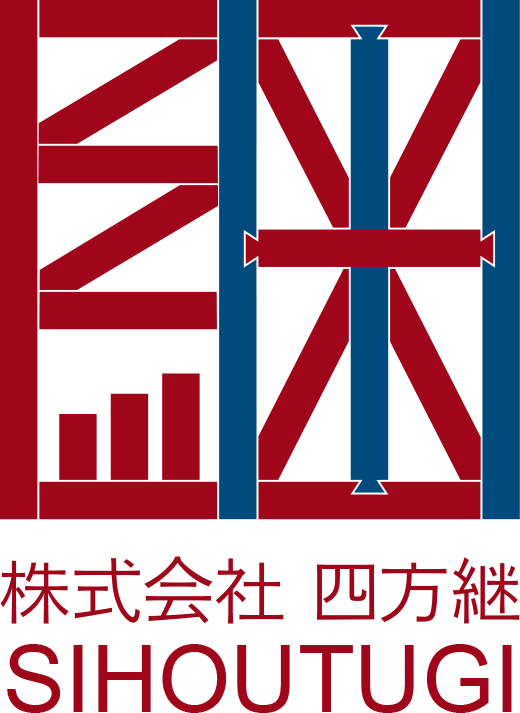はじめに:なぜ今、CSVモデルが注目されるのか
現代の企業経営において、「利益だけを追求すればよい」という考え方は、もはや通用しません。消費者は企業の社会的責任を重視し、投資家はESG(環境・社会・企業統治)を評価基準に含めるようになりました。
そんな中で私たち株式会社四方継が注目しているのが、CSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)モデルです。これは、社会課題の解決と企業の利益創出を同時に実現する経営手法のことです。
当社は創業当初からこのCSVモデルを実践してきました。「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」という理念のもと、すべてのステークホルダーが恩恵を受ける経営を目指しています。
2020年の社名変更は、地域を守り次世代に継なげる事業への強いコミットメントを表明したものでした。そして2022年には、一般社団法人日本未来企業研究所より未来創造企業として認定されました。
本記事では、当社がどのようにCSVモデルを経営に組み込み、「四方良し」を実現しているのか、その具体的な取り組みをご紹介します。建設業界に留まらず、あらゆる業界でCSVモデルの導入を検討されている経営者の方々にとって、参考になる内容をお届けできれば幸いです。
CSVモデルの基本概念と当社の「四方良し」思想
CSVモデルとは何か
従来のCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)が「利益を上げた後に社会貢献をする」という考え方だったのに対し、CSVは「社会課題を解決することで利益を生み出す」という発想の転換を意味します。
つまり、社会貢献と利益創出が対立するものではなく、むしろ両立し、相乗効果を生み出すものとして捉えるのです。これは単なる理想論ではなく、実際に多くの企業で成果を上げている実践的なビジネスモデルです。
四方継が考える「四方良し」とは
当社では、CSVモデルを「四方良し」という独自の概念で実践しています。ここでいう「四方」とは、以下の四者を指します。
- 作り手:職人や技術者など、モノづくりに携わる私たちの仲間
- 住み手:私たちのサービスを利用してくださるお客様
- 協力会社:共に事業を推進するパートナー企業
- 地域社会:私たちが事業活動を行う地域コミュニティ
この四者すべてが満たされ、持続的に恩恵を受ける状態を「四方良し」と定義しています。一辺倒な利益追求ではなく、すべての関係者がwin-winの関係を築くことで、長期的な成長と価値創造を実現するのです。
例えば、職人の技術向上支援は「作り手」の満足度を高め、それが品質向上につながって「住み手」の満足度も向上します。同時に、地域の雇用創出や技術継承により「地域社会」にも貢献し、結果として「協力会社」との関係も強化されるという循環が生まれます。
なぜ「継ぐ」ことが重要なのか
当社の社名には、「継ぐ」という文字が含まれています。これは単に事業を引き継ぐという意味だけでなく、価値ある文化や技術、人材を未来に継承するという深い意味が込められています。
建設業界では、熟練職人の高齢化と後継者不足が深刻な社会問題となっています。この課題を放置すれば、日本の優れた建築技術や文化が失われてしまう可能性があります。私たちは、この危機感から「継ぐ」ことの重要性を強く認識し、CSVモデルを通じて解決に取り組んでいるのです。
継塾:CSVモデルを深める学びの場
継塾の設立背景と目的
当社では、CSVモデルへの理解を深め、実践力を向上させるために「継塾」という学びの場を運営しています。これは単なる社内研修ではなく、地域の事業者や関係者も参加できるオープンな勉強会です。
継塾の背景には、「すべての成果の元になる理(ことわり)に、じっくりと向き合う」という私たちの哲学があります。短期的な成果を追求するのではなく、長期的に持続可能な「常態」を作り上げることが重要だと考えているからです。
CSVモデルは一度確立すれば終わりではありません。社会課題は常に変化しており、それに対応するためにビジネスモデルも継続的に刷新していく必要があります。継塾は、この継続的な探求と改善のためのプラットフォームとして機能しています。
ホットシートによる実践的な議論
継塾の特徴的な取り組みの一つが、偶数月に実施される「ホットシート」です。これは、参加者の中から一人が「熱い席」に座り、自社のビジネスモデルについてプレゼンテーションを行い、参加者全員でそのモデルの刷新やブラッシュアップについて議論するものです。
例えば、令和7年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏にご登壇いただきました。一見、建設業とは異なる分野のように思えますが、ゴミ収集運搬も地域社会にとって不可欠な社会課題解決サービスです。
この事例を通じて、私たちは以下のようなことを学びました。
- 地域密着型事業におけるCSVモデルの可能性
- 社会インフラを担う事業の価値再定義
- 時代の変化に対応したサービスモデルの進化
このように、異業種の事例を学ぶことで、自社の「四方良し」追求のヒントを得ることができるのです。
地域全体の事業モデル進化への貢献
継塾は、当社の社内教育に留まりません。地域社会全体のビジネスモデルがCSVモデルへと進化することを支援する「文化継承」の役割も担っています。
参加者それぞれが自社でCSVモデルを実践し、それがネットワーク効果を生んで地域全体の活性化につながる。このような好循環を創り出すことが、継塾の最終的な目標です。
実際に、継塾に参加した地域の事業者の中には、自社の事業モデルを見直し、社会課題解決の要素を取り入れるようになった企業も複数あります。これこそが、CSVモデルの真の価値と言えるでしょう。
職人不足という社会課題への挑戦
建設業界が直面する深刻な問題
建設業界が直面する最も深刻な社会課題の一つが、職人不足の加速です。国土交通省の調査によると、建設業就業者の約3割が55歳以上で、29歳以下は約1割に過ぎません。このままでは、日本の優れた建築技術や文化が失われてしまう危険性があります。
この問題は単純な労働力不足ではありません。熟練職人が持つ技術や知識、そして「モノづくり」への誇りといった無形の価値も同時に失われる可能性があるのです。私たちは、この危機感から職人育成事業に本格的に取り組むことを決めました。
職人不足は、建設業界だけの問題ではありません。住宅の品質低下、建設コストの上昇、工期の遅延など、社会全体に影響を与える問題なのです。だからこそ、この課題解決は典型的なCSVモデルの対象と言えます。
職人起業塾:イントラプレナーシップの醸成
2013年、当社は社員大工のキャリアアップと地域の職人活性化を目的に「職人起業塾」を開講しました。この取り組みは、職人を単なる労働力として扱うのではなく、社内起業家精神(イントラプレナーシップ)を持った自律的な人材として育てることを目指した画期的なものでした。
従来の建設業界では、職人は指示された仕事をこなすことが求められがちでしたが、当社では職人一人ひとりが経営者視点を持ち、自ら考え行動できる人材になることを重視しています。職人起業塾は、この理念を実現するための重要な取り組みです。
塾では以下のようなカリキュラムを提供しています。
- 経営の基礎知識(財務、マーケティング、法務など)
- 職人技術の体系化と指導法
- 顧客との関係構築スキル
- プロジェクトマネジメント能力
この取り組みにより、職人たちは技術力だけでなく、ビジネスパーソンとしての総合力を身につけることができます。結果として、当社の職人は単なる作業者ではなく、お客様の課題を解決するパートナーとして成長しています。
2016年には、この取り組みが評価され、一般社団法人職人起業塾として全国展開を開始しました。現在では、全国各地で同様の取り組みが広がっています。
マイスター高等学院:教育システムの革新
2023年4月、当社は「マイスター高等学院」を開校しました。これは、高校卒業資格を取得しながら、大工などの職人技術を身につけることができる画期的な通信制高校です。
従来の教育システムでは、職人を目指す若者は高校卒業後に専門学校や職業訓練校に進むか、直接現場に入るかの選択肢しかありませんでした。マイスター高等学院は、この常識を覆し、高校教育と職人教育を統合した新しいモデルを提示しています。
学院の特徴は以下の通りです。
- 実践的な技術習得:現役の当社職人が直接指導
- 理論と実技の融合:建築の原理から実際の施工まで体系的に学習
- キャリア設計支援:個々の適性に応じた進路指導
- 地域との連携:地元企業でのインターンシップ機会
開校からまだ短い期間ですが、すでに多くの生徒が入学し、その中には将来の職人リーダーとなる可能性を秘めた人材も数多くいます。
この取り組みは、「職人不足の世の中で、通常の高校では隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる」という社会的価値と、「当社事業の核となる優秀な人材を確保する」という経済的価値を両立させた、まさにCSVモデルの実践例です。
地域社会の信頼創造:つない堂の取り組み
現代社会における信頼の課題
現代社会では、情報の氾濫と匿名性の拡大により、信頼関係の構築が困難になっています。インターネットで検索すれば膨大な情報が得られる一方で、その情報の信頼性を判断することは非常に難しくなっています。
特に地域社会においては、この信頼の問題は深刻です。近隣住民同士の関係が希薄化し、地域の事業者についても「どこに頼めばよいかわからない」という状況が生まれています。これは、地域経済の活性化にとって大きな障害となっています。
私たちは、この現代的な課題に対して「つない堂」という事業を通じて取り組んでいます。これは、地域の信頼ネットワークを再構築し、「検索不要の安心安全な地域社会」を作ることを目指した取り組みです。
つない堂のビジョンと仕組み
つない堂のビジョンは、「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。2020年の社名変更を機に、それまで「すみれ暮らしの学校」で展開していた活動もつない堂に統合し、より包括的な地域支援活動を展開しています。
つない堂では以下のような活動を行っています。
優良事業者の発掘と紹介 地域には優れた技術や知識を持つ「人」「事業所」「サービス」が数多く存在しますが、それらが十分に知られていないことがあります。つない堂では、これらの隠れた宝を発掘し、適切に評価・紹介する役割を担っています。
リアルなネットワーク構築 インターネット上の情報に頼るのではなく、実際に顔を合わせ、対話を重ねることで信頼関係を構築します。定期的な交流会や勉強会を開催し、事業者同士、そして事業者と利用者の間に確かなつながりを作り上げています。
暮らしを豊かにする学びの提供 かつての「すみれ暮らしの学校」の理念を引き継ぎ、料理教室、ガーデニング教室、DIY教室など、暮らしに関わる様々な学びの機会も提供しています。これらの活動を通じて、地域住民同士の交流も促進されています。
品質保証システム つない堂で紹介する事業者については、一定の基準を設けて厳選しています。技術力はもちろん、顧客対応や倫理観なども含めて総合的に評価し、安心して利用できる事業者のみを紹介しています。
成功事例と地域への影響
つない堂の取り組みにより、実際に多くの成功事例が生まれています。
例えば、ある地域の高齢者夫婦が自宅のリフォームを検討していた際、つない堂の紹介で地域の優良工務店と出会うことができました。工務店は高齢者の生活様式を十分に理解し、バリアフリー化だけでなく、日常の困りごとも解決できる提案を行いました。結果として、夫婦は安心して老後を過ごせる住環境を手に入れることができました。
この事例では、以下のような価値が創造されています。
- 住み手への価値:安心安全な住環境の獲得
- 協力会社への価値:信頼に基づく継続的な取引関係
- 地域社会への価値:高齢者が住み続けられる地域の実現
- 作り手への価値:技術を正当に評価される機会の獲得
つない堂は、このような好循環を数多く生み出し、地域全体の活性化に貢献しています。現在では、つない堂のネットワークに参加する事業者は100社を超え、年間の紹介件数も着実に増加しています。
環境と暮らしの質向上への取り組み
高性能ゼロエネルギー住宅への挑戦
環境問題への対応は、現代企業にとって避けて通れない課題です。当社では、2012年に高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」を開発し、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
SUMIKA-ZEROは、以下の特徴を持つ革新的な住宅です。
高い断熱性能 外壁、屋根、基礎すべてに高性能断熱材を使用し、熱橋(ヒートブリッジ)を徹底的に排除。これにより、冬暖かく夏涼しい快適な住環境を実現しています。
効率的な設備システム 高効率給湯器、LED照明、省エネ家電などを標準装備。さらに、太陽光発電システムとの組み合わせにより、年間のエネルギー収支をゼロ以下にすることが可能です。
自然素材の活用 化学物質を極力使わない自然素材を積極的に採用。住む人の健康と地球環境の両方に配慮した素材選択を行っています。
SUMIKA-ZEROに住むお客様からは、「光熱費が大幅に削減された」「一年中快適に過ごせる」「子供のアレルギー症状が改善した」といった喜びの声をいただいています。
長期メンテナンスサービスの提供
建物は完成してからが本当のスタートです。当社では、2009年から「無料巡回メンテナンスサービス」を本格化し、「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、長期にわたる住まいの安全性を保証しています。
このサービスの特徴は以下の通りです。
- 定期的な専門家による点検:建築の専門知識を持つ当社スタッフが定期的にお客様の住まいを訪問し、構造的な問題や設備の不具合がないかをチェックします。
- 予防保全の考え方:問題が起きてから対応するのではなく、問題が起きる前に予防することを重視。長期的な視点で建物の価値を維持・向上させます。
- 迅速な対応体制:緊急時には24時間365日対応可能な体制を整備。お客様の安心・安全を最優先に考えたサービスを提供しています。
※無料巡回エリアは神戸近郊に限定されていますが、エリア外のお客様についても、可能な限りサポートを行っています。
健康住宅への取り組み
2012年より、当社では電磁波への対策にも取り組んでいます。現代の住宅には多くの電気設備が導入されており、それらから発生する電磁波が人体に与える影響が懸念されています。
当社では、以下のような対策を実施しています。
- オールアース住宅の提案
- 電磁波測定サービスの実施
- 適切な配線計画による電磁波低減
- 電磁波対策建材の活用
これらの取り組みにより、住む人の健康を最優先に考えた住環境を提供しています。特に、妊婦さんや小さなお子さんがいるご家庭からは高い評価をいただいています。
技術者集団「つむぎ建築舎」の役割
世代を超えて受け継がれる建築の実現
当社の技術的な中核を担うのが「つむぎ建築舎」です。これは、世代を超えて受け継がれる価値ある建築を実現するための技術者集団です。
つむぎ建築舎のメンバーは、それぞれが高い専門性を持ちながら、同時に「四方良し」の理念を深く理解している技術者たちです。彼らは単に技術的に優れた建物を作るだけでなく、その建物が長期にわたって住む人に愛され、地域社会に貢献できるかを常に考えて設計・施工を行っています。
技術継承と革新の両立
つむぎ建築舎では、伝統的な建築技術の継承と、最新技術の導入の両立を図っています。
伝統技術の継承 日本の木造建築には、何百年にもわたって受け継がれてきた優れた技術があります。これらの技術は、現代の科学技術で検証しても非常に合理的で優秀なものが多く、私たちは積極的に現代の建築に活用しています。
最新技術の導入 一方で、断熱技術、耐震技術、省エネ技術など、現代科学の成果も積極的に取り入れています。伝統と革新の最適な組み合わせにより、現代のニーズに応える高性能な建築を実現しています。
技術の見える化 技術は属人的なものになりがちですが、つむぎ建築舎では技術の標準化と見える化に取り組んでいます。これにより、技術の継承と品質の均一化を実現しています。
お客様との協創関係
つむぎ建築舎では、お客様を単なる依頼者ではなく、共に理想の住まいを創り上げるパートナーと考えています。
設計段階から施工、そしてアフターメンテナンスに至るまで、お客様との密なコミュニケーションを重視し、お客様の想いを形にするための最適な提案を行っています。
まとめ:CSVモデルが切り拓く持続可能な未来
四方継が実現する四つのCSV価値
当社が実践するCSVモデルは、「人、街、暮らし、文化を継ぐ」という使命を具現化するものです。私たちは以下の四つの側面で共有価値を創造しています。
「人」へのCSV 職人起業塾やマイスター高等学院を通じて、職人不足という社会課題を解決し、モノづくりの担い手を憧れの職業にする取り組みを進めています。これにより、技術継承と雇用創出を同時に実現しています。
「街」へのCSV つない堂を通じて、地域社会の信頼低下という現代的課題を解決し、安心安全な循環地域型社会を構築しています。地域経済の活性化と住民の安心向上を両立させています。
「暮らし」へのCSV SUMIKA-ZEROなどの技術を通じて、環境負荷と住み手の不安という二つの課題を同時に解決し、世代を超えた長期的な安心を提供しています。
「文化」へのCSV 継塾を通じて、持続可能性への視点という経営文化を創造・継承し、地域全体の事業モデル向上に貢献しています。
未来への展望
当社は、これからも未来創造企業として、事業を通じて社会と価値を共有し、全てのステークホルダーが豊かになる「四方良し」の常態を追求し続けます。
建設業界だけでなく、あらゆる業界でCSVモデルの導入が進むことで、持続可能で豊かな社会を実現できると確信しています。
私たちの取り組みが、一つのモデルケースとなり、多くの企業がCSVモデルを導入するきっかけになることを願っています。そして、それぞれの企業が自社なりの「四方良し」を実現することで、社会全体がより良い方向に向かうことを期待しています。
CSVモデルは決して理想論ではありません。適切に実践すれば、確実に成果を上げることができる実践的なビジネスモデルです。当社の事例が、その可能性を示す一助となれば幸いです。
最後に、私たちは常に学び続け、改善し続けることを大切にしています。読者の皆様からのご意見やご質問もお待ちしております。共に、持続可能で豊かな未来を創造していきましょう。