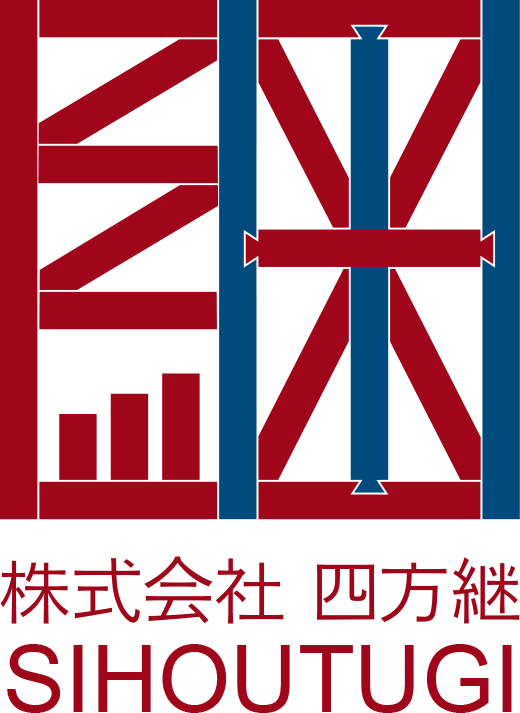はじめに:なぜ今「継承される建築」なのか
現代の住宅建設では、10年、20年で建て替えが必要になる家が少なくありません。しかし、本当に価値のある家とは、親から子へ、子から孫へと世代を超えて受け継がれていくものではないでしょうか。
株式会社四方継の建築サービス部門「つむぎ建築舎」は、まさにそうした「世代を超えて受け継がれる価値ある建築」の実現を目指しています。当社は単なる住宅建設会社ではありません。「木と暮らしをデザイン、実現する技術者集団」として、住まう人の人生を豊かにし、未来の世代まで価値を持ち続ける建築を創造しています。
では、どのようにして「受け継がれる価値」を建築に込めるのでしょうか。その答えは、当社が掲げる「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」という理念の中にあります。この理念を建築という形で具現化するのが、つむぎ建築舎の使命なのです。
潜在的価値を見つけ出す設計哲学
住まい手が気づいていない本当の望みを形にする
多くのお客様が家を建てる際、「リビングは20畳欲しい」「キッチンは対面式で」といった具体的な要望をお持ちです。もちろん、こうした要望も大切です。しかし、当社ではそれ以上に重要なことがあると考えています。
それは「住まい手がまだ気づいていない、知らない望みを形にする」ことです。
例えば、ある家族がリビングを広くしたいとおっしゃったとします。しかし詳しくお話を伺うと、実は「家族が自然に集まる空間が欲しい」という本当の望みが見えてきました。この場合、単にリビングを広くするよりも、キッチンから家族の気配を感じられる設計や、子どもたちが勉強しながらでも家族とつながりを感じられるスペースの配置が重要になります。
このような本質的な望みを引き出すために、当社では女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションを大切にしています。女性設計士は暮らしの細部にわたる感性を活かし、家事動線や家族間の心地よい距離感など、生活文化に関わる潜在的なニーズを掘り起こします。
一方、大工(作り手)との密接な連携により、デザインされた「暮らし」を確実に「実現」する技術的な解決策を組み込みます。この対話こそが、設計段階で最高の品質と、後の世代まで耐えうる構造を担保するのです。
木を活かす日本の建築文化の継承
つむぎ建築舎は「木と暮らしをデザイン」することを大切にしています。なぜ木なのでしょうか。
木という素材は、日本の風土に最も適した建材です。湿気の多い日本の気候に対応し、時を経るごとに味わいを増し、構造材としても優れた性能を発揮します。さらに重要なのは、木を使った建築は年月が経つにつれて価値が減じるどころか、むしろ増していくということです。
適切に手入れされた木造建築は、50年、100年と時を重ねるごとに独特の風合いを醸し出します。これは、単なる素材選定を超えた、日本の建築文化そのものを「継ぐ」という深い意味を持っています。
実際に、当社が手がけた住宅では、10年経過した頃から「家に愛着がさらに深まった」というお声をいただくことが多くあります。新築時の美しさとは異なる、時間が育てた美しさが住まう方の心を豊かにしているのです。
品質と信頼を「常態」とする取り組み
専門家としての「理」に基づいた提案
住宅建築において、お客様のご要望を聞くことは当然重要です。しかし、当社はそれだけでは十分ではないと考えています。専門家として、構造的な安全性、エネルギー効率、法的な適合性、そして経済的な合理性という「理」(ことわり)に基づいた最適な解を提示することが使命です。
例えば、お客様から「開放的な大きな窓が欲しい」というご要望があったとします。当社は単にその通りに設計するのではなく、以下のような観点から最適解を導き出します。
- 構造上の安全性は保たれるか
- 断熱性能への影響はどうか
- プライバシーの確保は十分か
- 将来的なメンテナンス性はどうか
このような多角的な検討を経て、お客様の真の望みを叶えながら、長期的な価値を保つ設計を提案します。こうした専門的な提案・計画能力の重要性を認識し、当社では2005年に2級建築士設計事務所登録を行い、確認申請業務や設計業務の充実を図りました。
施工プロセスの「見える化」で信頼を築く
どんなに優れた設計図があっても、それが現場で忠実に、高い品質で実現されなければ意味がありません。つむぎ建築舎では、施工プロセスの「見える化」を徹底することで、品質への信頼を確保しています。
具体的には、建築過程の重要なポイントで写真撮影を行い、お客様に進捗状況をご報告します。基礎工事、構造材の組み上げ、断熱材の施工など、完成後は見えなくなる部分こそ、しっかりとお見せします。
この「見える化」には二つの効果があります。一つは、お客様が安心して建築過程を見守ることができること。もう一つは、職人(作り手)自身が常に高い緊張感と責任感を持って作業に臨むことです。
2003年に「職人による直接施工が反響を呼び、元請中心の営業に転換」した際の哲学、すなわち「作り手の技術力と信頼性が事業の核である」という原点を、現代的なプロセス管理によって高度に実現しているのです。
このプロセスが「常態」として機能することで、施工品質が個人の技量に左右されることなく、常に高いレベルで維持されます。お客様からは「安心して任せることができた」「完成後も品質に対する信頼感が違う」といったお声をいただいています。
未来責任を果たすサステナブルな設計
環境とエネルギーへの責任:ゼロエネルギー設計
「世代を超えて受け継がれる」建築には、未来の社会環境の変化やリスクに対応できる性能が不可欠です。特に重要なのが、エネルギー効率の高さです。
当社では、早くからこの課題に取り組んできました。2012年には、高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」が国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されています。
SUMIKA-ZEROは、単に省エネ基準を満たすだけでなく、その先の「ゼロエネルギー」を目標とした設計です。これにより、住まい手の将来のエネルギーコストを大幅に削減し、地球環境への負荷を最小限に抑えます。
具体的には、以下のような技術を組み合わせています。
- 高性能断熱材による熱損失の最小化
- 太陽光発電システムの効率的な配置
- 省エネ型設備機器の最適な選定
- 自然通風や採光を活かした設計
実際にSUMIKA-ZEROにお住まいのご家族からは、「光熱費がほぼゼロになった」「夏も冬も快適に過ごせる」といったお声をいただいています。これは、環境CSV(社会課題解決)の視点を取り込んだ設計思想の成果です。
未知のリスクへの対策と長期的な安心
建築設計は、既知の課題だけでなく、未来に顕在化する可能性のあるリスクにも対応していなければなりません。
例えば、当社では2012年から電磁波への対策の取り組みを開始しました。当時はまだ一般的ではありませんでしたが、スマートフォンやWi-Fi機器の普及を見据え、住環境における電磁波の影響を考慮した設計を導入したのです。
こうした先見性のある対策が、住まい手の健康と安心を長期にわたって守ります。
さらに重要なのは、建築後も「受け継がれる価値」を維持することです。2009年には「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しました(※無料巡回エリアは神戸近郊に限られます)。
このサービスでは、定期的にお宅を訪問し、建物の状況をチェックします。小さな不具合も早期に発見・対応することで、大きな修繕を防ぎ、建物の価値を長期にわたり維持します。建築物をただの「モノ」として扱うのではなく、住み手の生活と未来を保証する「資産」として捉える、当社の設計思想の現れです。
「四方良し」を実現する建築エコシステム
「作り手」の質が設計の実現力を決める
どんなに優秀な設計図があっても、それを実現する「作り手」(職人)の技術と意欲が低ければ、設計思想は絵に描いた餅となってしまいます。つまり、「作り手」の質の確保は、設計の品質を担保するための最も重要な要素なのです。
当社では、この重要性を深く理解し、職人の育成に長年取り組んできました。2013年には職人起業塾を開講しました。これは社内起業家精神(イントラプレナーシップ)を醸成する研修であり、技術だけでなく経営感覚も身につけた職人を育成する取り組みです。職人一人ひとりが自律的に考え、行動できる人材となることで、当社全体の技術力と提案力が向上しています。
さらに2023年には、マイスター高等学院を設立しました。この学院では、高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における「職人」としての技術を身につけることができます。
これは単なる職業訓練ではありません。日本の伝統的な職人技術を現代に継承し、同時に起業家精神を持った次世代の職人を育成する取り組みです。こうした「人」を継続的に育成する「常態」が、つむぎ建築舎の設計の実現可能性と品質を支えているのです。
「街」の安心が建築の価値を支える
建築物が世代を超えて価値を持つためには、その建物が存在する「街」(地域社会)が安全で豊かでなければなりません。どんなに素晴らしい家でも、周辺環境が荒廃していては、その価値は維持できないからです。
当社の事業部門である「つない堂」は、この「街」の健全性を担っています。つない堂は、「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことを目指し、地域内の優れた「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築しています。
例えば、新しく家を建てたお客様には、信頼できる地域の商店や医院、教育機関などをご紹介します。また、地域のイベントや活動にも積極的に参加し、コミュニティの絆を深める取り組みを行っています。
つむぎ建築舎の設計思想は、この安心な循環地域型社会のハブとなることで、建物のハード面だけでなく、地域コミュニティというソフト面からも「継承される価値」を強化しているのです。
絶え間ない学びによる文化の継承
設計思想は一度確立したら終わりではありません。社会課題や技術は常に変化しており、それに対応して設計思想も進化し続ける必要があります。
当社では、定期的に「継塾」を開催しています。この継塾では、持続可能なビジネスモデル探求をテーマとし、特にCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)に焦点を合わせた議論を行っています。
2025年3月の継塾のテーマは「『常態』全ての成果の元になる理にじっくりと向き合ってみませんか?」でした。このように、つむぎ建築舎の設計者や技術者は、継続的な学びの文化を通じて、自らの設計思想を常に理にかなった、未来志向のものへと刷新し続けているのです。
継塾では、最新の建築技術だけでなく、社会情勢の変化、お客様のライフスタイルの変遷、環境問題への対応など、幅広いテーマが扱われます。参加者同士の活発な議論を通じて、新しいアイデアや解決策が生まれ、それが実際の設計に反映されています。
まとめ:暮らしの継承という未来への誓い
株式会社四方継「つむぎ建築舎」が実現する「世代を超えて受け継がれる価値ある建築」は、1994年の創業時から受け継がれる大工集団の技術と誇りを源流とし、現代の未来志向の理念によって体系化された設計思想の結晶です。
当社の設計思想は、以下の要素を統合することで、建築物を未来への責任を果たす手段としています。
深い対話に基づく本質的なデザインでは、女性設計士と大工の連携により、住まい手が真に求める「暮らし」を形にします。表面的な要望を超えて、潜在的な望みを引き出し、それを木という素材を活かしながら実現します。
高性能と環境への配慮では、SUMIKA-ZERO認定技術や電磁波対策など、未来の課題に対応した安全・快適性を「常態化」しています。これにより、住まい手の将来にわたる安心と、地球環境への責任を両立しています。
長期的な安心の保証では、無料巡回メンテナンスサービスと施工プロセスの透明化により、建物の価値維持にコミットしています。建築後も続くサポート体制が、真の意味での「継承される建築」を可能にしています。
社会システムの組み込みでは、職人育成(人)と地域ネットワーク(街)の強化により、建築物を支える社会的な基盤そのものを継承しています。マイスター高等学院やつない堂の取り組みが、建築の価値を社会全体で支える仕組みを作り上げています。
つむぎ建築舎の設計は、単なる住宅設計を超えて、「人、街、暮らし、文化を継ぎ」という当社の壮大な使命を、住まい手の生活空間という最も身近な場所で具現化する、未来への確固たる誓いなのです。
当社が目指すのは、お客様が「この家を子どもたちに残したい」と心から思える建築です。そして、その子どもたちもまた「この家を大切に受け継ぎたい」と感じる建築です。それこそが、真に「世代を超えて受け継がれる価値ある建築」の姿だと確信しています。