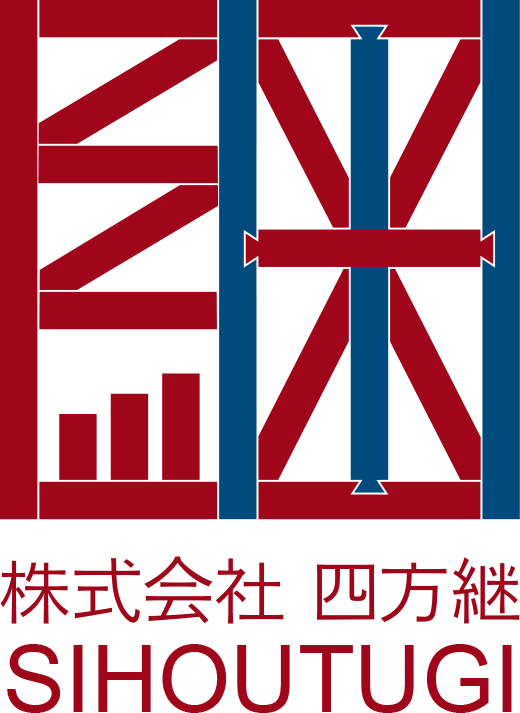はじめに:なぜ私たちは「四方良し」を大切にするのか
こんにちは。株式会社四方継(しほうつぎ)です。
私たちは神戸市西区を拠点に、ものづくり工務店「つむぎ建築舎」と地域活動のハブ「つない堂」を運営しています。
社名に込められた「四方継」という言葉。これには深い意味があります。私たちが掲げる企業理念は「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」ことです。
「四方良し」とは、近江商人の経営哲学である「三方良し」をさらに発展させた考え方です。三方良しは「売り手良し、買い手良し、世間良し」という、すべての関係者が幸せになることを目指す理念でした。私たちはこれを現代の建設業と地域社会に適用し、四つの「良し」として再定義しました。
その四つとは、作り手である私たちと職人、住み手であるお客様、協力会社のパートナー企業、そして地域社会です。
2020年、創立20周年を迎えた際に、私たちは「有限会社すみれ建築工房」から「株式会社四方継」へ社名を変更しました。この決断は、単に箱としての家を提供するのではなく、地域を守り次世代に継なげる事業を目指すという、私たちの覚悟の表れです。
この記事では、私たちの「四方良し」の理念が、日々の活動の中でどのように実践されているのか、具体的な事例とともにご紹介します。
第一の柱:住み手良し——世代を超えて受け継がれる価値ある家づくり
未来を見据えた高性能住宅への取り組み
住み手にとっての「良し」とは何でしょうか。それは、今だけでなく、子や孫の世代まで安心して住み続けられる家を提供することだと私たちは考えています。
世界的な課題となっている環境問題に対して、私たちは「GX志向型住宅」の実現に力を入れています。GXとはグリーントランスフォーメーションの略で、温室効果ガスの排出を削減しながら経済成長も実現する取り組みです。具体的には、高い断熱性能と高効率設備を導入し、一次エネルギー消費量を大幅に削減する住宅を指します。
実は私たちがこの分野に取り組み始めたのは、今から10年以上前のことです。2012年に開発した高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」は、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。この公的な認定は、私たちが長年にわたって環境性能と省エネルギーを追求してきた証です。
同じく2012年には、住む人の健康を守るため、電磁波対策の取り組みも開始しました。目に見えないリスクに対しても、私たちは真摯に向き合っています。
先端技術への挑戦
真の専門性とは、新しい技術や希少な技術にも果敢に挑戦し、それを高いレベルで実現できる能力だと考えています。
現在、私たちが取り組んでいる新しいプロジェクトの中には、日本国内でもまだ3棟目となる特殊な構法を用いた計画があります。正直に言えば、私たち自身も「始めてのことだらけで、手探りで少しずつ進めている状態」です。それでも、たくさんの方々の協力をいただきながら、一歩ずつ前に進んでいます。
また、KANSO構法プロジェクトでは、もるくす建築社の佐藤さんや、スイスのN11 Architektenといった国際的なパートナーとも連携しています。世界の最先端技術を学びながら、それを地域の風土に合わせた丁寧なものづくりに落とし込む。この経験は、私たちの大きな財産となっています。
見えない部分にこそ、私たちのこだわりがある
住宅建築において最も大切なのは、完成後には見えなくなってしまう部分の品質です。私たちは、プロセスを見える化し、細部にわたる「丁寧なものづくり」を実践しています。
例えば、スキップの家というプロジェクトでは、上棟前にお施主様と一緒に、材木を製材・プレカットしてくださる「しそうの森の木」さんへ見学に行きました。材料がどこから来て、どのように加工されるのか。その透明性を確保することが、信頼の第一歩だと考えています。
建設中の同じ現場では、断熱気密工事の段階で、すき間から空気が漏れないようにしっかり丁寧に施工する技術が求められます。この見えない部分の品質が、住まいの快適性を何十年にもわたって左右するのです。
愛知県の歯科クリニックの現場では、天然乾燥の愛知県産杉材に囲まれた心地よい空間を作りました。自然素材を活かした設計は、私たちの得意分野です。この現場では、左官の下地である「木摺り(きずり)」という伝統技術も使用しています。柱の両側に細い木を細かいピッチで留めるこの技術は、最終的に左官の土で覆われてしまいます。完成すると見えなくなってしまう美しい仕事。でも、「隠れてしまうのがもったいない」と私たちが感じるほど丁寧に仕上げます。これこそが、私たちの「見て安心、さわって安心」という品質へのこだわりです。
また、お客様のご要望で作製したコンパクトなワークデスクでは、シナの共芯合板を使用しました。3×6判(910ミリ×1820ミリ)の合板1枚から、なるべく無駄のないように部材を取る「木取り」の技術を活かし、効率と環境への配慮を両立させています。
私たちの強みは、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションです。住まい手の具体的なニーズを丁寧に汲み取り、専門家としての最適な提案と計画を行い、施工プロセスを見える化する。この一連の流れが、お客様との深い信頼関係を築きます。
第二の柱:作り手・協力会社良し——次世代の担い手を育て、共に成長する仕組み
深刻な職人不足に立ち向かう
建設業界は今、深刻な職人不足という課題に直面しています。しかし、私たちは待っているだけではありません。自ら次世代の担い手を育成する取り組みを、全国レベルで展開しています。
2013年、私たちは社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的に「職人起業塾」を開講しました。この研修事業は、2016年に一般社団法人として法人化され、全国展開に至っています。単なる一工務店から、業界全体をリードする存在へ。この実績は、私たちの取り組みが業界から認められた証だと自負しています。
職人起業塾が目指すのは、単なる独立開業の支援ではありません。「イントラプレナーシップ」という社内起業家精神を持った人材の育成です。組織内で高い当事者意識と技術を持って活躍できるプロフェッショナルを育てる。これが私たちの明確な哲学です。
若い世代に建設業の魅力を伝える
さらに2023年4月には、マイスター高等学院を設立し開校しました。
これは、通常の高校では「隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる学校」として、高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における職人としての技術を身につけることを可能にする通信制高校です。未来の建築業界を担う人材の育成に、私たちは本気で投資しています。
若い世代に建設業の魅力を伝え、技術を継承していく。これは私たちの使命だと考えています。
協力会社と共に学び、成長する
協力会社との関係は、単なる発注と受注の関係ではありません。共に学び、持続可能なビジネスモデルを追求するパートナーシップです。
私たちは企業経営者や専門家向けの研修会「継塾(つぐじゅく)」を偶数月に開催しています。参加者のビジネスモデルの刷新やブラッシュアップを目的とした、ホットシート形式のダイアログを行います。
例えば、令和7年6月の継塾では、兵庫県尼崎市でゴミの収集運搬業を営む有限会社森衛生の川内友太氏にプレゼンを依頼しました。テーマは「今の時代に合わせたCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)」です。建築業界の枠を超えた経営知識と社会貢献性の高い専門知識を追求する。これが継塾の特徴です。
令和7年3月の継塾では、持続可能なビジネスモデル探求のため「常態」をテーマとしました。全ての成果の元になる理に、じっくりと向き合う研修です。常に本質的な価値と、成果を生み出す仕組みを追求し続ける。この姿勢が、協力会社や業界全体からの信頼を得る源泉となっています。
第三の柱:地域社会良し——ご縁を紡ぎ、いい街を次世代に継ぐ
検索不要の安心を目指す「つない堂」
私たちの活動は、建築業の枠を超えています。地域活動拠点「つない堂」は、地域住民や次世代の子どもたちとの「ご縁を紡ぎ、いい街を継ぐ」というビジョンを具体化する場所です。
つない堂では、あらゆる分野で卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築しています。そして、積極的な情報発信を行うメディアとして機能し、「信頼を軸に人と人を繋ぎ、ご縁を紡ぐ」ことを目指しています。
私たちが目指す究極の地域社会の姿とは何か。それは「インターネット検索を必要としない安心安全な循環地域型社会のハブ」です。困ったときに誰に相談すればいいか分かる。信頼できる情報がすぐに手に入る。そんな安心感のある地域社会を作りたいのです。
このメディア活動の一環として、情報誌「つないどう?」を作成し、積極的に情報発信を行っています。現在は、能登半島輪島市黒島地区の重要伝統的建築物修復レポートを特集した号の折加工が順調に進んでおり、5月中には発送される予定です。これは、私たちの社員大工であるかーたー石田が現地に泊まり込んで行った専門的な修復活動の経験を、地域社会と共有する重要な取り組みです。
地域の子どもたちへの投資
次世代を担う地域の子どもたちの育成は、「いい街を継ぐ」ための最も重要な活動だと私たちは考えています。
私たちは地域の子どもたちへの学習支援として「しずく学習塾」を運営しています。水曜日の授業日には、新二年生、三年生の申し込みで募集人数いっぱいになるほどの盛況ぶりです。この反響は、地域からの高い信頼を物語っていると感じています。
運営スタッフは、卒業生、在校生、ボランティア総勢18名を集めた卒業パーティーをテラスで開催するなど、精力的に活動しています。学習塾の運営継続のため、「ご支援のお願い」というページも作成し、銀行振込やカード決済での支援を受け付けています。透明性を保ちつつ地域からの協力を求める。これも信頼関係を築く大切なステップです。
年度末には学習塾のお引越しや新年度対応など、スタッフが「てんやわんや」な状況もありました。それでも、子どもたちの学びを支援したいという熱意が、私たちを動かし続けています。
2025年8月には「ちびっこ応援!木工教室」を開催しました。午前の部では3家族が参加し、「インテリア棚」や「キーフック」を作成しました。子供たちにものづくりの喜びを提供する。この経験を通じて、モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にしたい。それが私たちの願いです。
地域行政との連携
地域社会への貢献は、イベント参加や行政との連携によっても実現されます。
西区役所の方からの声掛けを受け、2025年9月には「伊川リバーフェスタ」や「西区もくいく」に参加し、地域でのデビューを果たしました。また、2025年1月には西区役所主催の「エニシミーツ」(E-NISHIと縁をかけたネーミング)にも参加しました。地域とのご縁を大切にし、積極的に交流を図る。これが私たちのスタイルです。
建てた後も、ずっと安心を
私たちの責任は、家を建てて終わりではありません。地域のお客様に長期的な安心を提供するために、2009年より「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化させています(神戸近郊に限る)。
この十数年にわたる継続的なアフターサービスは、私たちが建てた家と地域住民への深い責任感の現れです。建てて終わりではない。住み続ける限り、私たちはお客様に寄り添い続けます。
私たちの歩みと、これから
株式会社四方継の歴史は、1994年の「大工集団 高橋組」としての創業に始まります。以来、一貫してものづくりに携わりながら、常に未来を見据えてきました。
2022年には、一般社団法人日本未来企業研究所より未来創造企業として認定されました。これは、私たちが社会的な責任を果たす企業として成長してきた証だと考えています。
2020年の社名変更から5年。「四方良し」の理念は、私たちの日々の活動の中に確実に根付いています。住み手のための高性能住宅と丁寧なものづくり。作り手と協力会社のための人材育成と知識共有。地域社会のための教育支援とコミュニティ形成。そして、すべてを繋ぐ長期的なメンテナンスとアフターサービス。
これらの活動は、個別に存在するのではありません。すべてが「人、街、暮らし、文化を継ぐ」という一つの目的に向かって、有機的に結びついているのです。
「四方良し」の実現は、決して終わりのない挑戦です。時代は変わり、技術は進化し、社会のニーズも変化していきます。しかし、私たちの理念は変わりません。
建築を通じて人々の生活を豊かにし、地域社会に深く貢献し続ける。すべての関係者が幸せになる、誠実な家づくりとまちづくりを追求し続ける。これが、株式会社四方継の約束です。
私たちは今日も、神戸市西区から、この理念を実践し続けています。そして、次の世代へ、確かな技術と温かい心を継いでいきます。