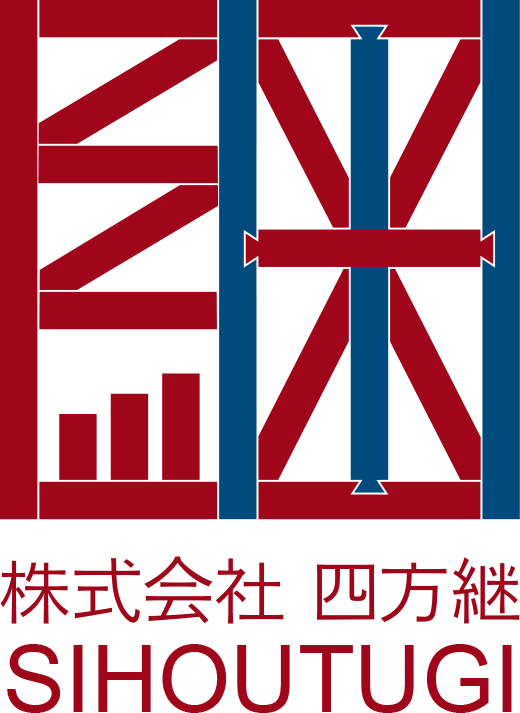はじめに:情報があふれる時代だからこそ、人と人の繋がりを
私たち株式会社四方継は、神戸市西区を拠点に「つむぎ建築舎」というものづくり工務店と、地域活動拠点「つない堂」を運営しています。創業は1994年。当初は「有限会社すみれ建築工房」としてスタートし、地域の皆様に支えられながら、丁寧なものづくりを続けてきました。
2020年、創立20周年を機に「株式会社四方継」へと社名を変更しました。この社名には「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という強い思いが込められています。四方良しとは、作り手、住み手、協力会社、そして地域社会の四者すべてが利益を得るという、持続可能な事業モデルのことです。
現代社会では、何か困ったことがあれば、まずインターネットで検索します。「この業者は信頼できるのか」「本当に良いサービスなのか」と、レビューを読み漁り、比較サイトを見比べる。便利な時代になった一方で、情報が多すぎて何が正しいのか分からなくなることも増えました。
そんな中、私たちが「つない堂」を通じて目指しているのが、「インターネット検索を必要としない安心安全な循環地域型社会」の構築です。人から人へ、顔の見える関係の中で信頼が繋がっていく。そんな温かいコミュニティを、もう一度この地域に作りたい。それが私たちの願いです。
「つない堂」が担う役割:地域の信頼できるハブになる
「つない堂」の最も大切な役割は、地域における「ハブ」となることです。ハブとは、自転車の車輪の中心にある部品のことで、ここから放射状にスポークが伸びて車輪全体を支えています。私たちは、地域社会の中心となって、さまざまな人や情報を繋ぐ存在でありたいと考えています。
具体的には、地域に存在する「あらゆる分野で優れた知識や技術を持つ人」「信頼できる事業所」「質の高いサービス」を発掘し、それらを結びつけるリアルなネットワークを構築しています。たとえば、「子どもの教育について相談したい」という方がいれば、信頼できる先生を紹介する。「リフォームを考えているけれど、どこに頼めばいいか分からない」という方には、適切な職人さんを繋ぐ。そういった、人と人を繋ぐ架け橋になることが私たちの使命です。
なぜ私たちにそれができるのか。それは、1994年の創業以来、地域で「受け継がれる価値のある丁寧なものづくり」を続けてきたという、長年の信頼の積み重ねがあるからです。建築という、地域住民の生活の根幹に関わる事業を通じて培った安心感が、このネットワークの基盤となっています。
また、「つない堂」は情報発信の場としても機能しています。私たちは情報誌「つないどう?」を定期的に発行し、地域の暮らしに役立つ情報や、専門的な知識を分かりやすく共有しています。単に情報を流すのではなく、その情報が本当に信頼できるものかを精査し、地域社会の安心安全な循環を支える中心地となることを目指しています。
実際の活動から見える「つない堂」の姿
理念を掲げるだけでは意味がありません。私たちは実際に地域に深く入り込み、さまざまな活動を通じて信頼関係を築いています。ここでは、具体的な活動事例をいくつかご紹介します。
情報誌「つないどう?」で地域と繋がる
「つないどう?」は、私たちが発行している情報誌です。地域の皆様に役立つ情報を届けるため、定期的に制作・発行しています。
2025年5月に発送予定の最新号では、「能登半島輪島市黒島地区・重要伝統的建築物修復レポート」を特集しました。この取り組みは、弊社の大工である石田が現地に泊まり込んで行った専門的な修復活動を、地域の皆様に報告するものです。
能登半島地震からの復興支援として、私たちは単に地元神戸で家を建てるだけでなく、日本の伝統的建築物の保全という社会的な責任も果たしています。こうした活動を通じて、私たちの技術力と地域への思いを感じていただければと思います。
情報誌の制作は、企画から印刷、折加工、発送まで、スタッフが丁寧に作業を進めています。最新号も「絶賛折加工中」という段階を経て、皆様のお手元に届けられました。こうした地道な作業の一つ一つが、地域との繋がりを深めることに繋がっています。
地域行政や団体との連携
信頼されるネットワークを築くためには、地域行政との連携も欠かせません。私たちは、西区役所をはじめとする行政機関とも密に連携しながら、地域のイベントに積極的に参加しています。
2025年9月には、「伊川リバーフェスタ」と「西区もくいく」に参加しました。これらのイベントは、西区役所の方からお声掛けをいただき、私たちのデビューとなった記念すべき機会でした。行政の方々から信頼していただけているということは、私たちにとって大きな励みとなっています。
また、2025年1月には、西区役所主催のイベント「エニシミーツ」にも参加しました。「E-NISHI(いい西)」と「縁(エニシ)」を掛けたネーミングで、まさに私たちが大切にしている「ご縁を紡ぐ」という考え方と重なります。こうした機会を通じて、地域の方々と顔の見える関係を築いていくことができています。
子どもたちの未来を育む「しずく学習塾」
「いい街を次世代に継ぐ」というビジョンを実現するため、私たちは地域の子どもたちの育成にも力を入れています。その一つが「しずく学習塾」の運営です。
この学習塾は、地域の子どもたちに学びの場を提供することを目的としています。毎週水曜日に授業を行っており、地域のご家庭から厚い信頼をいただいています。三年生が卒業したばかりですが、すぐに新二年生、三年生の申し込みがあり、募集人数がいっぱいになるほどの盛況ぶりです。
学習塾の運営には多くの費用がかかります。そのため、私たちは「ご支援のお願い」ページを作成し、銀行振込やカード決済での支援を募っています。運営の透明性を確保しながら、地域の皆様のご協力をいただきながら活動を続けています。
子どもたちが安心して学べる場所を提供することは、未来の地域社会を支える人材を育てることに繋がります。私たちは、この活動を通じて地域の未来に投資しているのです。
ものづくりの楽しさを伝える「木工教室」
2025年8月には、「ちびっこ応援!木工教室」を開催しました。午前の部には3家族様にご参加いただき、インテリア棚やキーフックづくりに挑戦していただきました。
猛暑の中での開催でしたが、子どもたちの安全を第一に考え、冷風機を導入するなど環境面にも配慮しました。木に触れ、自分の手で何かを作り上げる喜びを感じてもらうこと。それが、この教室の大きな目的です。
私たちは「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」を目指しています。職人という仕事の素晴らしさ、ものづくりの楽しさを子どもたちに伝えることで、未来の作り手を地域で育んでいきたいと考えています。
職人を育て、技術を継ぐ:教育事業への取り組み
「つない堂」が発掘し繋ぐ「優れた知識や技術を持つ人」とは、私たち自身が育成しているプロフェッショナルたちでもあります。私たちは建築業という枠を超えて、職人の育成にも力を入れています。
マイスター高等学院:新しい教育の形
2023年4月、私たちは「マイスター高等学院」を設立し、開校しました。これは、職人不足という社会課題に対する私たちなりの答えです。
通常の高校では、座学中心の授業に馴染めない子どもたちもいます。しかし、そうした子どもたちの中には、手を動かすことや、ものづくりに優れた才能を持つ子が数多くいます。マイスター高等学院は、そうした才能を見つけ、開花させる学校です。
ここでは、高校卒業の資格を取りながら、同時に大工などの技術を身につけることができます。通信制高校という形態を取ることで、生徒たちは自分のペースで学習を進めながら、実践的な技術も習得できるのです。
この教育プログラムは全国的にも珍しく、多くの注目を集めています。私たちは、この学校を通じて、次世代の職人たちを育て、日本のものづくり文化を継いでいきたいと考えています。
職人起業塾:技術者を経営者へ
2013年に開講した「職人起業塾」は、2016年には一般社団法人として法人化され、全国展開に至っています。この塾が推進しているのは、イントラプレナーシップという考え方です。
イントラプレナーシップとは、社内起業家精神のこと。つまり、技術者が単に技術を持つだけでなく、経営的な視点を持ったプロフェッショナルになることを目指しています。優れた技術を持っていても、それをビジネスとして成立させる力がなければ、持続可能な事業にはなりません。
この塾を通じて育った職人たちは、全国各地で活躍しています。「つない堂」で繋がる「人」や「サービス」は、こうした高度な教育を受けた人材によって提供されるため、その質は非常に高いものとなっています。
継塾:学び続ける組織文化
私たちは偶数月に、企業経営者や専門家向けの研修会「継塾」を開催しています。ここでは、CSVモデル(社会課題解決型ビジネス)といった現代的なテーマを取り上げ、議論を深めています。
CSVモデルとは、Creating Shared Valueの略で、企業が社会課題を解決しながら経済的価値も生み出すというビジネスモデルのことです。私たちの「四方良し」の考え方とも重なる概念です。
この継続的な学びの姿勢が、私たちが提供するすべての事業の質を高め、持続可能性を保証しています。時代は常に変化していきます。その変化に対応し、常により良いサービスを提供するためには、学び続けることが欠かせません。
建築技術者集団としての専門性
私たちが「信頼の輪」を広げることができるのは、単なる情報仲介者ではなく、「木と暮らしをデザインし、実現する技術者集団」だからです。建築という専門分野での確かな実績が、すべての活動の基盤となっています。
女性建築設計士と大工によるきめ細やかな対応
私たちの強みの一つは、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションです。住まい手の方々は、時に自分でも気づいていない望みを抱えています。私たちは対話を重ねることで、そうした潜在的なニーズを形にしていきます。
また、専門家としての提案から計画、そして施工プロセスまで、すべてを見える化することを徹底しています。何をどのように進めているのか、お客様に常に分かりやすくお伝えすることで、信頼関係を築いています。
高性能住宅への取り組み
私たちの技術力は、公的にも認められています。2012年には、高性能ゼロエネルギー住宅SUMIKA-ZEROが国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
ゼロエネルギー住宅とは、太陽光発電などでエネルギーを創り出すことで、年間のエネルギー消費量を実質的にゼロにする住宅のことです。環境に優しく、光熱費も抑えられるという、これからの時代に求められる住まいの形です。
こうした技術的な裏付けがあるからこそ、私たちは自信を持って地域の皆様にサービスを提供できるのです。
スタッフの日々の努力が支える「つない堂」
大きなビジョンを実現するためには、日々の地道な努力が欠かせません。私たちのスタッフは、常に全力で活動に取り組んでいます。
10月のワークショップマルシェを控えた時期には、正直なところ「胃が痛い」ほどのプレッシャーを感じることもあります。それでも「今の自分の全力を出し切ろう」という強い気持ちで、大詰めの準備に取り組んでいます。
また、年度末には助成金の報告や申請、学習塾の引越しなど、さまざまな業務が重なり、「なんとなくてんやわんや」な状況になることもあります。それでも、地域活動を止めることなく、継続的に努力を続けています。
こうした日々の積み重ねが、地域の皆様からの信頼に繋がっていると信じています。完璧ではないかもしれませんが、誠実に、一生懸命に取り組む姿勢を大切にしています。
2022年「未来創造企業」認定:社会的な評価
私たちの取り組みは、外部からも高く評価されています。2022年には、一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されました。
この認定は、私たちの事業が社会に持続的な価値を提供していることが認められたものです。第三者機関からの評価は、私たちが推進する「つない堂」の活動が、単なる地域活動ではなく、社会的な意義を持つ事業モデルであることの裏付けとなっています。
この認定を励みに、私たちはさらに活動を加速させています。地域社会への貢献と、事業としての持続可能性。この両立を実現することが、私たちの目指す「四方良し」の形です。
これからの「つない堂」:継なげる未来へ
「インターネット検索を必要としない安心安全な循環地域型社会」の実現。それは私たちが掲げる「四方良し」の理念の具現化そのものです。
この「信頼の輪」は、単なるデジタル情報の代替ではありません。長年にわたる地域への貢献、業界を牽引する専門教育、そして建築業として培った確かな技術力。これらすべてを結集して築かれる、人、街、暮らし、文化を継ぐための社会基盤なのです。
神戸市西区を中心とした地域社会が、世代を超えて安心して暮らせる「いい街」であり続けるように。私たちは「つない堂」の活動を、これからも強力に推進してまいります。
インターネットで検索しなくても、「あの人に聞けば大丈夫」「つない堂に相談すれば、きっと良い人を紹介してくれる」。そう思っていただける存在になること。それが私たちの目標です。
地域の皆様と一緒に、温かく、信頼に満ちたコミュニティを作っていく。その一員として、私たちはこれからも歩み続けます。