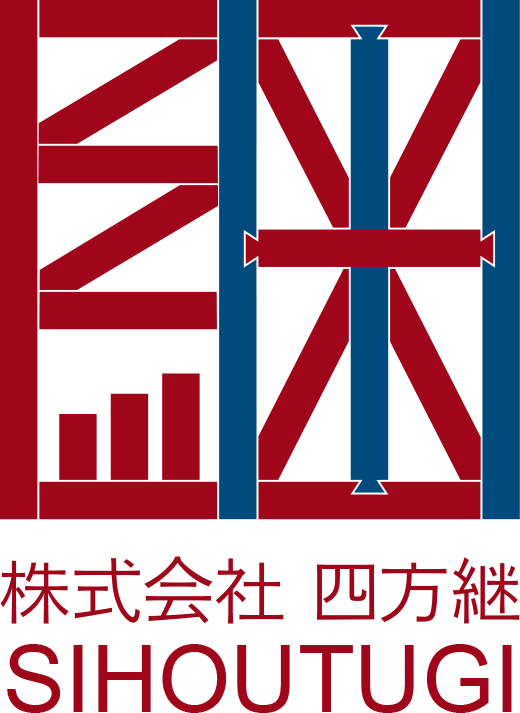はじめに – 学びと責任のバランス
神戸市西区で「つむぎ建築舎」と地域活動拠点「つない堂」を運営する私たち株式会社四方継は、「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という企業理念のもと、日々活動しています。
2025年3月22日、つない堂のスタッフが西神中央で開催された「こどもまんなか講演会」に参加しました。子どもたちの未来を考えるという重要なテーマでしたが、スタッフは「内容が私の必要としているものとはちょっと違う。仕事が忙しいので途中で失礼させて頂きました」と報告してきました。
この一見すると失礼にも思える行動には、実は私たちが大切にしているプロフェッショナルな時間管理の考え方が詰まっています。今回は、この出来事を通じて、私たちがどのように学びと仕事への責任のバランスを取っているのかをお伝えします。
建築業と地域活動という二つの軸で事業を展開する私たちにとって、時間は最も貴重な資源です。限られた時間の中で、お客様、地域社会、そして未来への責任を果たすために、常に優先順位を明確にする必要があります。
私たちが「こどもまんなか」にこだわる理由
まず、なぜスタッフがこの講演会に参加したのかをご説明します。それは私たちが地域の子どもたちの育成に本気で取り組んでいるからです。
しずく学習塾での実践
つない堂では「しずく学習塾」を運営し、毎週水曜日に地域の子どもたちに学びの場を提供しています。この学習塾は、三年生が卒業した後も、すぐに新二年生・三年生からの申し込みが殺到し、募集人数がいっぱいになりました。
この盛況ぶりは、私たちが地域のご家庭から厚い信頼をいただいている証だと考えています。保護者の方々が安心してお子さんを預けてくださる環境を、これからも守り続けていきたいと思っています。
ものづくりを通じた教育活動
私たちは「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすることを目指す」というビジョンを掲げています。2025年8月には「ちびっこ応援・木工教室」を開催し、子どもたちが実際に木材に触れ、ものづくりの楽しさを体験できる機会を作りました。
このような活動を継続し、さらに発展させるために、スタッフが自ら関連する講演会に足を運び、最新の知見を得ようとする姿勢は、私たちの事業にとって不可欠なものです。学びへの積極性がなければ、質の高いサービスは提供できません。
地域行政との強固な連携
私たちは西区役所が主催するイベントにも積極的に参加しています。2025年1月には「エニシミーツ」に参加し、同年9月には「伊川リバーフェスタ」や「西区もくいく」にも西区役所からのお声掛けをいただきデビューしました。
これらのイベント参加を通じて、地域のニーズや社会的なトレンドを常に把握し、自社の活動に反映させる努力を続けています。地域に根差した企業として、行政との連携は私たちの活動の基盤となっています。
なぜ途中で失礼したのか – その真意
さて、本題です。スタッフが講演会を途中で退席したという判断について、詳しくご説明します。これは決して軽率な行動ではなく、プロフェッショナルとしての強い責任感から生まれた決断でした。
年度末・年度初めの多忙さ
スタッフが「仕事が忙しい」と報告した背景には、年度末から新年度にかけての尋常ではない多忙さがありました。2025年4月頃、スタッフは「春だというのに仕事も私生活もてんやわんや」という状況に置かれていました。
具体的には、年度末の助成金報告、しずく学習塾の新年度対応とお引越し、そして2025年度の助成金申請など、地域活動を継続するために欠かせない重要業務が同時進行で進んでいたのです。
助成金申請は書類作成だけでも膨大な時間がかかります。活動実績の整理、収支報告の作成、次年度の活動計画の策定など、細かい作業が山積みでした。また、学習塾のお引越しでは、新しい環境の準備、保護者への案内、ホームページの更新など、やるべきことが次々と発生していました。
時間の価値を最大化する判断
講演会の内容を聞いているうちに、スタッフは「この内容は今の自分が必要としている情報とは違う」と判断しました。そこで、残りの時間を有効活用するために退席し、すぐに別の行動に移りました。
スタッフは駐車場代を節約するために本屋に立ち寄り、自分が本当に必要とする知識や情報を得るための時間に充てました。これは、単なる費用節約ではなく、限られた時間の中で最大の価値を生み出そうとする姿勢の表れです。
私たちは別のイベントの準備の際にも「今の自分の全力を出し切れ」という強い決意のもと業務に取り組んできました。このプロ意識は、無駄な時間を排除し、本当に価値を生む活動に集中するという時間管理の哲学につながっています。
お客様と地域への責任を優先
講演会を最後まで聞くことよりも、目の前の仕事を確実にこなすこと。それが結果的に、しずく学習塾に通う子どもたちや保護者の方々、そして地域社会への責任を果たすことになると判断したのです。
学びは大切です。しかし、その学びを活かす現場がなければ意味がありません。今目の前にある仕事、今必要としている人たちへの対応を優先することこそが、真のプロフェッショナルだと私たちは考えています。
私たちの専門性と仕事への誇り
スタッフが「仕事」を優先した背景には、その仕事が社会から期待されている高い専門性を持つものだという自覚があります。
建築における専門技術の追求
建築の現場では、例えば「スキップの家」の断熱気密工事では、すき間から空気が漏れないようしっかり丁寧に施工するという高度な技術が求められます。この技術は、GX志向型住宅の実現や、老後を見据えた平屋の設計など、お客様の未来の暮らしの快適性に直結します。
一つひとつの施工が、お客様の何十年もの暮らしを左右します。だからこそ、私たちは現場での作業に妥協を許しません。断熱材の隙間一つ、気密テープの貼り方一つにも、職人の技術と責任が込められています。
未来の職人を育てる取り組み
私たちが運営する「マイスター高等学院」は、高校卒業の資格を取りながら大工など建設業における職人としての技術を身につけることができる、業界でも珍しい取り組みです。また「職人起業塾」では、イントラプレナーシップという社内起業家精神の醸成を研修しています。
イントラプレナーシップとは、企業内で起業家のように主体的に行動し、新しい価値を生み出す精神のことです。従来の「言われたことをやる」職人像から、自ら考え、提案し、実行できる職人へと成長してもらうことを目指しています。
これらの人材育成プログラムは、建設業界全体の未来を担う重要な活動です。スタッフは、自分たちの日常業務がこうした社会的意義の高い活動を支えていることを深く理解しているからこそ、時間の優先順位を厳しく設定できるのです。
効率化の価値を提供する
私たちが設計する住宅では、共働き世帯の増加を踏まえ、家事効率を最優先に考えています。「ラク家事は共働きママにとって時短をかなえるサバイバルツールとして優先度が増大している」という認識のもと、室内干しメインの間取りや、効率的な動線を持つ設計を提案しています。
例えば、洗濯機から室内干しスペース、そしてクローゼットまでの動線を一直線にすることで、洗濯物を運ぶ手間を大幅に削減できます。キッチンからパントリー、そして冷蔵庫までの配置を工夫することで、料理の効率が飛躍的に向上します。
また、お客様からの要望で作ったコンパクトなワークデスクの製作では、3×6判の合板1枚から、なるべく無駄のないように部材を取る「木取り」の技術を駆使しました。木取りとは、一枚の板材から必要な部材を効率的に切り出す計画のことで、材料の無駄を最小限に抑える職人の知恵です。
このように、お客様の暮らしに提供する「無駄の排除と効率化」という価値観を、私たち自身の仕事への姿勢でも実践しています。講演会を途中で退席するという判断も、この価値観の延長線上にあるのです。
企業理念に基づく長期的な信頼構築
スタッフが仕事への責任を優先する姿勢は、株式会社四方継が長年にわたって培ってきた企業理念と倫理観によって支えられています。
未来創造企業としての使命
私たちは2022年に一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されました。これは、私たちの理念「地域を守り次世代に継なげる事業を目指す」が、持続可能であり、社会的な意義を持っていることの公的な証明です。
この認定は単なる名誉ではありません。地域社会に対する責任、環境への配慮、従業員の育成、そして長期的な事業の持続可能性など、多角的な評価を受けた結果です。私たちはこの認定に恥じない企業活動を続けていく責任があります。
透明性のある情報発信
講演会を途中で退席したという事実を、正直に、そして具体的に報告することも、私たちの透明性へのこだわりです。表面的に取り繕うのではなく、その判断に至った理由と背景を包み隠さず伝えることで、お客様や地域の皆様との信頼関係を築いていきたいと考えています。
失敗や判断ミスがあれば、それも正直に報告します。なぜそうなったのか、どう改善するのかを明確にすることで、かえって信頼は深まると私たちは信じています。
長年の実績が裏付ける責任感
私たちは2009年より、「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化させています。神戸近郊に限られますが、この十数年にわたる継続的なサービスは、私たちがお客様の暮らしに対して長期的な責任を負い続けている証です。
建物は建てて終わりではありません。むしろ、建てた後のメンテナンスこそが、お客様との本当のお付き合いの始まりです。定期的に訪問し、小さな不具合も見逃さず、必要に応じて補修や改善提案を行うことで、建物の寿命を延ばし、お客様の暮らしを守り続けています。
信頼を軸にした人との繋がり
西区役所との連携にも見られるように、私たちは「信頼を軸に人と人を繋ぎ、ご縁を紡ぐ」ことを最優先しています。一時的な学びよりも、この「ご縁」と「信頼」を損なわない仕事への責任を優先する判断こそが、真のプロフェッショナリズムだと考えています。
地域のイベントに参加し、行政と連携し、お客様と長期的な関係を築く。これらすべてが、一朝一夕にできることではありません。日々の小さな約束を守り、期待に応え、時には期待を超える提案をすることで、少しずつ信頼の輪が広がっていくのです。
私たちが大切にする時間管理の哲学
今回のスタッフの行動から見えてくるのは、私たち株式会社四方継が大切にしている時間管理の哲学です。
学びは手段、実践が目的
学びの機会は大切です。しかし、学びはあくまでも手段であり、目的ではありません。学んだことを実践し、お客様や地域社会に価値を提供することこそが、私たちの存在意義です。
だからこそ、「この学びが今の自分に必要か」「この時間を他のことに使った方が価値を生むのではないか」と常に自問自答する姿勢が求められます。すべての学びの機会に参加することはできません。選択と集中が必要なのです。
優先順位を明確にする勇気
何かを選ぶということは、何かを捨てることでもあります。講演会を途中で退席するという判断は、一見すると失礼に映るかもしれません。しかし、目の前の仕事、待っている人たちへの責任を優先するという明確な判断基準があれば、その決断に迷いはありません。
優先順位を明確にすることは、時に厳しい決断を伴います。しかし、その決断から逃げていては、本当に大切なものを守ることはできません。私たちは、お客様、地域社会、そして未来への責任という軸をぶらさずに、日々判断を積み重ねています。
全力を出し切る文化
私たちの組織には「全力を出し切る」という文化が根付いています。中途半端な仕事はしない。やると決めたことは、最後までやり抜く。この姿勢があるからこそ、時間の使い方にも妥協がないのです。
全力を出し切るためには、集中力が必要です。あれもこれもと手を広げていては、どれも中途半端になってしまいます。今、この瞬間に何に全力を注ぐべきかを見極め、そこに全エネルギーを投入する。そのための時間管理なのです。
おわりに – これからも学び続け、実践し続ける
2025年3月22日の「こどもまんなか講演会」への参加と、途中で失礼するというスタッフの行動は、「常に学びの姿勢を持ちつつも、仕事への責任を優先する」という私たち株式会社四方継のプロフェッショナルな姿勢を象徴するものでした。
年度末の多忙な時期、募集人数いっぱいになったしずく学習塾の新年度対応、助成金申請など、地域社会への継続的な貢献に必要な業務を確実に遂行するという強い責任感が、その判断の背景にありました。
私たちは、未来創造企業として認定された使命感と、職人起業塾やマイスター高等学院で培われた専門性を背景に、これからもお客様、協力会社、そして地域社会の未来のために、常に時間を有効活用し、最高の価値を創造し続けてまいります。
学びは続けます。しかし、学びのための学びではなく、実践のための学びを。地域の子どもたちの笑顔のために、お客様の快適な暮らしのために、そして次世代に継承すべき技術と文化のために。私たちは今日も、一つひとつの仕事に全力で向き合っています。