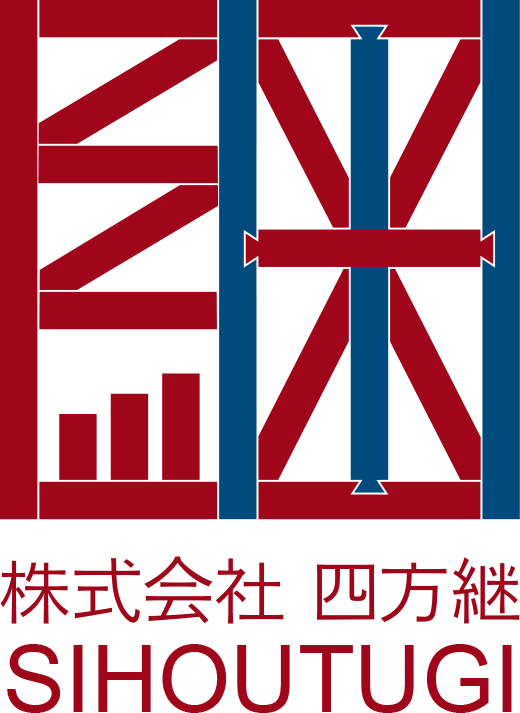はじめに:ものづくりの楽しさを次世代へ
こんにちは。神戸市西区でものづくり工務店「つむぎ建築舎」と地域活動拠点「つない堂」を運営している株式会社四方継です。
私たちは「人、街、暮らし、文化を継ぎ、四方良しを実現する」という理念のもと、日々活動しています。この四方良しとは、住み手、協力会社、作り手、そして地域社会の四者すべてが幸せになることを目指すものです。
特に地域社会への貢献として、次世代を担う子どもたちにものづくりの楽しさを伝えることを大切にしています。なぜなら、私たちは「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にすること」をビジョンの一つとして掲げているからです。
2025年8月2日、夏休み最後の週末に、地域の子どもたちとそのご家族を作業場にお招きして『ちびっこ応援!木工教室』を開催しました。今回はその様子を詳しくご報告します。
猛暑の中での開催:快適な環境づくりへの工夫
真夏の作業場という挑戦
8月2日は晴れ晴れとしたお天道様に恵まれた一日でした。しかし裏を返せば、作業場は猛暑となることが予想されました。木工作業は集中力を必要とします。特に子どもたちにとって、暑さは作業の妨げになります。
そこで今年は特別に冷風機を導入しました。これは大きな決断でした。なぜなら、通常の作業場では扇風機程度で対応することが多いからです。しかし参加してくださるご家族の快適さと、子どもたちが楽しく集中してものづくりに取り組める環境を整えることを最優先に考えました。
プロの現場を体験する価値
午前の部には3家族様にご参加いただきました。私たちの作業場は、普段から住宅建築の現場で使用する本物の工具や機材が並ぶ、プロフェッショナルな空間です。
ホームセンターの工作室とは違い、木材の香りが漂い、職人が実際に使う道具が整然と並び、安全管理の意識が徹底された環境。この「本物」の空間で作業することは、子どもたちにとって特別な経験になります。
実際、参加した子どもたちの目は輝いていました。「これがプロの大工さんが使う金槌なんだ」「木の匂いってこんなに良い香りなんだ」といった発見が、至るところにありました。
製作体験:インテリア棚とキーフックづくり
今回の製作物について
今回の木工教室では「インテリア棚」2つと「キーフック」の製作に取り組みました。これらは単なる工作キットではありません。実際にご家庭で使える実用的なサイズと設計になっています。
インテリア棚は、お部屋に飾れる小物や本を置くのにちょうど良いサイズです。キーフックは玄関で鍵や小物を掛けるのに便利な実用品です。つまり、作ったものが「作品」として飾られるだけでなく、日常生活の中で実際に使われることを想定しています。
子どもたちの真剣な取り組み
参加した子どもたちは、普段の生活では触れることのない作業に挑戦しました。
まずは部材の組み立てです。どの板とどの板を組み合わせるのか、設計図を見ながら考えます。これは空間認識能力を養う良い訓練になります。
次に釘打ちです。小さな手で金槌を握り、狙った場所に正確に釘を打つ。最初はうまくいかなくても、何度か繰り返すうちにコツをつかんでいきます。「あ、まっすぐ入った!」という喜びの声が作業場に響きました。
ヤスリがけも重要な工程です。木材の角を丁寧に削り、滑らかに仕上げる作業は根気が必要です。しかし「自分が使うものだから、手触りを良くしたい」という気持ちが、子どもたちを集中させます。
プロの視点を伝える指導
私たちは単に「ここに釘を打ってください」という指示だけではなく、なぜその寸法なのか、どうすれば丈夫に仕上がるのかという「プロの視点」も伝えるよう心がけました。
例えば、板と板を組み合わせる際の接合方法。釘を打つ角度や本数によって、完成品の強度は大きく変わります。これは私たちが日々の住宅建築で実践している技術です。
また、資源を大切にするという意識も伝えました。私たちは普段、お客様からコンパクトなワークデスクのご要望をいただいた際、3×6判の合板1枚から無駄なく部材を取る「木取り」という技術を使います。木工教室でも、限られた材料から必要な部材を効率よく使うという考え方を、子どもたちに体験してもらいました。
世界に一つだけの作品が完成
完成したインテリア棚とキーフックは、それぞれのご家族の個性が光る一点ものとなりました。同じ設計図から作っても、色の塗り方や装飾の工夫で、まったく違う表情の作品になるのが木工の面白さです。
自分たちの手で作ったものが実際に暮らしの中で使われる。この経験は、子どもたちにとってものづくりのやりがいを深く理解する第一歩になります。お父さんお母さんも「これを作ったの?すごいね!」と、わが子の成長を実感されている様子でした。
地域とのつながり:つない堂が目指すもの
信頼を軸にした地域活動
今回の木工教室は、私たちの地域活動拠点「つない堂」の活動の一環です。つない堂は「インターネット検索を必要としない安心安全な循環地域型社会のハブ」となることを目指しています。
これはどういう意味でしょうか。現代社会では、困ったことがあればまずインターネットで検索します。しかし、画面の向こうの情報は本当に信頼できるのか、自分に合っているのか、判断が難しいこともあります。
つない堂が目指すのは「顔の見える関係」です。困ったときに相談できる人が近くにいる。信頼できる人からの紹介なら安心できる。そんな、昔ながらの地域のつながりを現代に再構築することが目標です。
行政との連携による活動の広がり
私たちの地域活動は、行政からも認められています。
2025年9月には、西区役所からお声がけいただき「伊川リバーフェスタ」や「西区もくいく」に参加しました。また2025年1月には西区役所主催の「エニシミーツ」(E-NISHIと縁をかけたネーミングです)にも参加しています。
これらのイベント参加は、私たちにとって地域社会への貢献を実践する重要な機会です。行政や地域団体と連携することで、より多くの方々に私たちの活動を知っていただけますし、地域全体の活性化にもつながります。
イベント運営の裏側
こうしたイベントの運営には、スタッフの多大な労力が投入されています。華やかに見えるイベントの裏側では、準備と調整に追われる日々があります。
例えば、10月13日に控えた「tunaido*ワークショップマルシェ」の準備期間中、担当スタッフは「胃が痛い」と言いながらも、参加者の皆さまに楽しんでいただけるよう奮闘していました。
また年度末には助成金報告や新年度の助成金申請、学習塾のお引越しと新年度対応など、まさに「なんとなくてんやわんや」な状況になります。それでも私たちが地域活動を止めないのは、この活動が私たちの理念そのものだからです。
こうした裏側の努力を知っていただくことで、私たちの地域への献身的な姿勢をご理解いただければ幸いです。
しずく学習塾:継続的な学びの場の提供
子どもたちの学習を支える取り組み
木工教室のような単発イベントに加えて、私たちは継続的な学習支援にも力を入れています。それが「しずく学習塾」です。
しずく学習塾は、つない堂の活動の一つとして運営している学習支援の場です。水曜日の授業日には、新二年生、三年生の申し込みで募集人数いっぱいになるほどの盛況ぶりです。
私たちは建築の専門家ですが、同時に地域の子どもたちの未来に深く関わる存在でありたいと考えています。学習塾の運営を通じて、子どもたちの成長を長期的に見守ることができます。
学習塾でのコミュニティづくり
最近では、運営スタッフ、ボランティア、卒業生、在校生の総勢18名で、テラスを利用した卒業パーティーを開催しました。この規模の集まりは、単なる学習塾の枠を超えたコミュニティが形成されている証拠です。
卒業生が後輩たちに勉強を教えたり、保護者同士が情報交換したり。学習塾は子どもたちだけでなく、地域の大人たちもつながる場所になっています。
透明性の高い運営
学習塾の運営を安定的に継続するため、私たちは「ご支援のお願い」というページを新たに作成しました。銀行振込やカード決済での支援を受け付けています。
こうした取り組みを通じて、運営の透明性を高め、地域の皆さまからのご協力をいただきやすい環境を整えています。支援してくださる方々に対して、活動報告を定期的に行うことも忘れません。
木工教室も学習塾も、私たちが目指す「いい街を継ぐ」というビジョンを具現化する重要な活動なのです。
未来の作り手を育てる:専門教育事業への取り組み
マイスター高等学院の挑戦
木工教室で子どもたちにものづくりを教えることは、私たちにとって単なるボランティア活動ではありません。それは未来の建築業界を担う人材を育成するという、より大きな使命の一部なのです。
その使命を体現する取り組みの一つが、2023年4月に開校した「マイスター高等学院」です。
マイスター高等学院は、職人不足の現代社会において「通常の高校では隠れてしまっている才能を見つけ、開花させる学校」として設立されました。この通信制高校では、高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における職人としての技術を身につけることができます。
従来の教育システムでは、学力試験の成績で評価されがちです。しかし実際には、手を動かすことが得意な子、空間を把握する能力に優れた子など、様々な才能があります。マイスター高等学院は、そうした多様な才能を評価し、伸ばす場所です。
職人起業塾による人材育成
もう一つの重要な取り組みが「職人起業塾」です。
職人起業塾は2013年に「社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化」を目的に開講しました。その成果が認められ、2016年には一般社団法人として全国展開するまでに成長しました。
この研修事業の特徴は、単に独立開業を勧めるものではないということです。目的は「イントラプレナーシップという社内起業家精神の醸成」にあります。
イントラプレナーシップとは、組織に所属しながら起業家のような高い意識と主体性を持って働くことを指します。協力会社や社内の職人が、組織内で高い意識を持って活躍できるプロフェッショナル集団を育成することが、この塾の真の目的です。
木工教室から始まる長い道のり
木工教室で「ものづくりって面白い」「大工さんってかっこいい」と感じた子どもたちの中から、将来マイスター高等学院の生徒が生まれるかもしれません。そして職人起業塾で学ぶ高度な職人へと成長するかもしれません。
木工教室は、その長い道のりの第一歩なのです。だからこそ私たちは、この活動に真剣に取り組んでいます。
プロの技術を伝える:現場からの学び
伝統技術への敬意
私たちの専門性は、日々の現場で培われています。その技術と知識を次世代に伝えることも、重要な使命です。
例えば、最近手がけた愛知県の歯科クリニックの現場では、左官の下地である「木摺り(きずり)」が施工されていました。
木摺りとは、柱の両側に細い木を細かいピッチで留めていく伝統技術です。やがて左官の土で隠れてしまう部分ですが、その施工の美しさは「隠れてしまうのがもったいない」と感じるほどでした。
こうした伝統技術は、効率だけを追求すれば失われてしまうかもしれません。しかし私たちは、先人たちが積み上げてきた技術に敬意を払い、その価値を理解し、次世代に継承する責任があると考えています。
自然素材の心地よさ
同じクリニックの内部は天然乾燥の愛知県産杉材に囲まれており、まるで自分が木の中に入ったような感覚になります。これは自然素材ならではの心地よさです。
木工教室で子どもたちが木材に触れるとき、その温かさや香り、手触りを感じます。これは人工的な素材では得られない感覚です。自然のマテリアルの良さを肌で感じることは、将来彼らが大人になったとき、住まいや暮らしを考える上での貴重な原体験になります。
資源を大切にする意識
私たちは普段の仕事で、限られた資源を無駄なく活用する「木取り」の技術を大切にしています。これは環境への配慮でもありますし、コスト管理でもあります。そして何より、素材への敬意の表れです。
木工教室でも、この意識を子どもたちに伝えています。一枚の板から必要な部材を無駄なく切り出す。端材も別の用途に活用する。こうした「もったいない」という日本の伝統的な価値観は、現代においてますます重要になっています。
おわりに:これからも続く、ご縁を紡ぐ活動
今回の『ちびっこ応援!木工教室』は、私たち株式会社四方継が目指す「四方良し」の理念を体現する活動でした。
猛暑の中、冷風機を導入して環境を整え、3家族のご参加を得て製作されたインテリア棚とキーフック。これらは単なる作品ではなく、工務店と地域社会との間に築かれた深い信頼関係の証です。
子どもたちの輝く目、集中して作業に取り組む姿、完成したときの達成感。これらすべてが、私たちにとってかけがえのない喜びです。
私たちはこれからも、建築技術者集団としての専門性を活かし、マイスター高等学院や職人起業塾で培った経験をもとに、木工教室やしずく学習塾などの地域活動を通じて、地域の子どもたちとのご縁を紡いでいきます。
彼らが未来の「作り手」として活躍できる。そんな「いい街を継ぐ」事業を、これからも力強く推進してまいります。
次回もまた、多くの子どもたちと共に、ものづくりの楽しさと奥深さを分かち合えることを心より楽しみにしています。
地域の皆さま、いつも私たちの活動を支えてくださり、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。