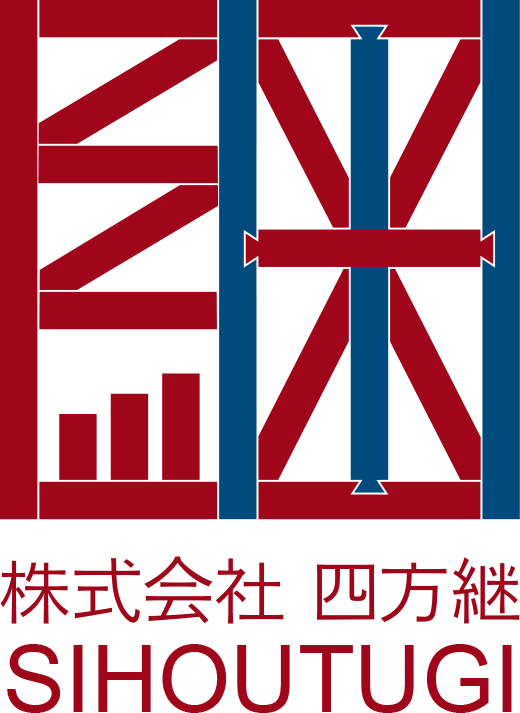はじめに:職人集団から生まれた信頼の物語
こんにちは。株式会社四方継(しほうつぎ)です。
今日は、当社にとって大きな転換点となった2003年のお話をさせていただきます。この年、私たちはリフォーム事業に進出し、「職人による直接施工」という取り組みで大きな反響をいただきました。
現在の四方継の理念である「人、街、暮らし、文化を継ぎ 四方良しを実現する」。この考え方の原点は、実は2003年の出来事にあります。
当時の私たちは、まだ有限会社すみれ建築工房という名前でした。大工集団として1994年に創業し、確かな技術力で実績を積み重ねてきました。しかし、2003年のリフォーム事業進出が、当社の運命を大きく変えることになったのです。
なぜ職人による直接施工がこれほど注目されたのか。そして、この成功がどのように現在の「四方良し」経営につながっているのか。その裏側を詳しくお話しします。
大工集団としての誇り:創業から2003年までの歩み
技術力が認められた創業時代
当社の物語は、1994年の神戸市西区大津和から始まります。「大工集団 高橋組」として創業した当初から、私たちには確固たる信念がありました。それは「技術で勝負する」ということです。
創業間もない頃から、大手住宅メーカーの特約工務店として実績を積むことができました。これは決して偶然ではありません。当社の技術力が外部から認められていた証拠です。
2002年に有限会社すみれ建築工房として法人化し、新築工事の受注を本格的に開始しました。しかし、この時点では、まだ下請け業者としての立場が中心でした。職人としての技術は高く評価されていましたが、お客様との直接的な関係は限られていたのです。
市場の課題を見つめて
当時のリフォーム市場には、大きな問題がありました。それは「信頼の欠如」です。
多くの場合、お客様の要望は複数の業者を経由して職人に伝わります。営業担当者がお客様から話を聞き、それを現場監督に伝え、さらに職人に指示が出る。この過程で、お客様の本当の想いが正確に伝わらないことが頻繁にありました。
また、中間業者が入ることで費用が不透明になり、お客様は「本当に適正な価格なのか」という不安を抱えていました。工事中も、実際に作業する職人と直接話ができないため、「要望通りに進んでいるのか」「品質は大丈夫なのか」といった心配が絶えませんでした。
私たち職人側も、お客様の真の想いを知らないまま作業することに、もどかしさを感じていました。「もっと良い方法があるのに」「こうすればお客様に喜んでもらえるのに」と思っても、それを直接伝える機会がなかったのです。
職人による直接施工:革命的なアプローチの始まり
2003年の大きな決断
2003年、私たちは思い切った決断をしました。リフォーム事業に進出し、「職人による直接施工」を実践することにしたのです。
これは当時としては珍しい取り組みでした。多くのリフォーム会社が営業担当者を前面に出す中、当社は職人自身がお客様と直接対話することを選択しました。
最初は不安もありました。「職人が営業をして大丈夫だろうか」「お客様に信頼してもらえるだろうか」という心配もあったのです。
直接対話がもたらした変化
しかし、実際に始めてみると、予想を上回る反響がありました。お客様からは次のような声をいただきました。
「実際に作業する人と直接話せるので安心です」 「要望を正確に理解してもらえて、期待以上の仕上がりでした」 「中間マージンがない分、予算内でより良い材料を使ってもらえました」
職人による直接施工には、三つの大きなメリットがありました。
直接的な対話による正確な意思疎通 職人が直接お客様と話すことで、要望の細部まで正確に把握できました。さらに、お客様自身が気づいていない潜在的なニーズも発見できるようになりました。
コストの透明性 中間業者を通さないことで、費用の内訳が明確になりました。お客様は何にいくらかかっているのかを正確に知ることができ、安心して工事を任せていただけました。
品質への責任感 職人自身が最初から最後まで責任を持つことで、より高い品質への意識が生まれました。自分の名前で工事を請け負う責任感が、さらなる技術向上への動機となりました。
元請中心への転換:信頼が生んだ経営改革
大きな反響が示した可能性
職人による直接施工の取り組みは、予想以上の反響を呼びました。お客様からの評価が口コミで広がり、紹介による新規依頼が増加しました。
この成功により、当社は重要な気づきを得ました。それは「職人の技術と人柄こそが、最高の営業力である」ということです。
従来の下請け中心の営業から、元請中心の営業へと軸足を移すことを決断しました。これは単なるビジネスモデルの変更ではありません。当社の職人精神を事業の中心に据える、経営哲学の転換でした。
現在の「つむぎ建築舎」につながる思想
この時の経験が、現在の当社の住宅事業部「つむぎ建築舎」の設計思想の基盤となっています。
つむぎ建築舎では、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションを重視しています。これは2003年に始まった「職人による直接施工」の進化形です。設計者と作り手が一体となってお客様と対話し、住まい手の潜在的な望みを形にする。この哲学は、20年前の成功体験から生まれたものなのです。
プロセスの見える化
元請として全責任を負うことで、専門家としての提案から施工プロセスまで、すべてを「見える化」することが可能になりました。
お客様にとって家づくりは、多くの場合、一生に一度の大きな買い物です。だからこそ、どのような工程で、どのような材料を使って、どのような技術で仕上げられるのかを、透明にお伝えすることが重要だと考えました。
この「見える化」により、お客様に安心をもたらし、品質に対する信頼を継続的に維持することができるようになりました。
専門性の拡張:技術力向上への継続的な取り組み
設計能力の強化
元請中心の営業に転換したことで、当社には新たな責任が生まれました。それは、設計から建築後のサポートまで、一貫して責任を負うということです。
2005年、元請転換のわずか2年後に、当社は2級建築士設計事務所登録を行いました。確認申請業務や設計業務の充実を図ったのです。これは、職人の技術力を最大限に活かすための、知的・専門的な基盤強化でした。
単に家を建てるだけでなく、お客様の暮らしをトータルでデザインする。そのためには、建築に関する幅広い知識と資格が必要でした。
長期サポートの責任
2009年には、「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しました。
これは非常に画期的な取り組みでした。多くの建設会社が完成後のアフターサービスを有料で提供する中、当社は無料でのメンテナンスを開始したのです。
ただし、このサービスは神戸近郊に限定させていただいています。なぜなら、責任を持って継続的にサービスを提供するためには、迅速に対応できる地理的範囲である必要があるからです。
2003年の直接施工で得たお客様からの信頼を、建築後も長期にわたって「継ぐ」。これが当社の責任に対する考え方です。
技術革新への挑戦
職人による直接施工で培った効率性と品質をさらに高めるため、当社は継続的な技術革新に取り組んでいます。
2007年には「すべての人に夢のマイホームを」を合言葉に、規格化注文住宅sumika(スミカ)の開発・販売事業をスタートしました。これは、2003年の直接施工のノウハウを活かし、高品質な住宅をより多くの方に届けるための取り組みでした。
さらに2012年には、sumikaの開発から派生した高性能ゼロエネルギー住宅SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)が、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。これは、環境負荷の低減と住まい手の経済的安心という未来の課題解決への挑戦でした。
同年、電磁波対策の取り組みも開始しました。住まい手が気づいていない潜在的な健康リスクにも、専門家として対応する姿勢を確立したのです。
暮らしの文化への拡張:建物を超えた価値提供
「暮らし」を豊かにする視点
2003年にリフォーム事業に進出した目的は、単に建物を直すことだけではありませんでした。当社が本当に目指していたのは、お客様の「暮らし」を豊かにすることでした。
この視点から、事業の多角化が始まりました。建築物というハードだけでなく、その中で営まれる「暮らしの文化」全体をデザインし、継承していく。これが当社の新たな使命となったのです。
飲食事業と学びの場の提供
2007年には飲食事業部を設立しました。これは単なる事業拡大ではありません。住環境と食環境は密接に関連しており、豊かな暮らしには両方が重要だと考えたからです。
2015年には「住環境に食、学びを通して日々の暮らしを豊かにしよう!」をコンセプトに、すみれ暮らしの学校を開講しました。ここでは、住まいに関する知識だけでなく、日々の暮らしを豊かにするための様々な学びを提供してきました。
その後、2020年の「四方継」への社名変更を機に、これらの活動は当社の事業部門「つない堂」の活動へと移行し、より広範な地域ネットワークの構築へと発展していきました。
これらの取り組みは、元請として建築を手がける責任感の表れです。建物を建てて終わりではなく、そこで営まれる暮らし全体に責任を持つ。この考え方が、当社の事業展開の根底にあります。
職人精神の継承:次世代への責任
職人の地位向上への取り組み
2003年の直接施工の成功が証明したのは、「職人」の価値でした。しかし、この価値を一時的なもので終わらせてはいけません。未来に「継ぐ」ことが、当社の最重要課題となりました。
2013年、当社は社員大工のキャリアアップと地域の職人の活性化を目的に、職人起業塾を開講しました。次世代を担う職人育成を本格的にスタートさせたのです。
この塾の狙いは、職人としての技術力向上だけではありません。イントラプレナーシップ、つまり社内起業家精神の醸成を目指した研修です。自ら考え、提案し、責任を持って行動できる職人を育成することで、2003年の元請転換で得た職人への信頼と誇りを次世代に継承しようとしたのです。
なお、この取り組みは職人の独立開業を促進するものではありません。当社の一員として、より高い視座と責任感を持って働く人材を育成することが目的です。
全国展開への発展
職人起業塾の取り組みは大きな反響を呼び、2016年には一般社団法人職人起業塾として法人化され、全国展開を開始しました。
当社の目標は明確です。「モノづくりの担い手を子どもの憧れの職業にする」こと。これは代表者高橋剛志の強い想いでもあります。
現代社会では、職人という職業に対する認知度や憧れが低下しています。しかし、当社の2003年の経験が示すように、職人の技術と人格は社会にとって非常に価値のあるものです。この価値を多くの人に理解してもらい、職人という職業の地位向上を図りたいと考えています。
マイスター高等学院の設立
建築業界の「職人不足」は深刻な問題です。この問題は、2003年に確立した「直接施工の品質」を将来維持できなくなるリスクを意味します。
このリスクに対処するため、2023年にマイスター高等学院を設立し、4月より開校しました。
この通信制高校は画期的な仕組みです。高校卒業の資格を取りながら、大工など建設業における「職人」としての技術を身につけることができます。
学生は一般的な高校教育を受けながら、実際の建築現場での実習も行います。座学と実技を組み合わせることで、理論と実践の両面から建築技術を習得できるのです。
これは、2003年に成功を収めた「作り手」の質と量を、未来にわたって保証するための最も重要な人材育成戦略です。
四方良しの実現:地域社会への責任拡張
つない堂による地域ネットワーク
2003年の元請中心への転換は、当社の責任範囲をさらに広げることになりました。「作り手」と「住み手」だけでなく、「協力会社」と「地域社会」を含めた広範なステークホルダーに責任を持つ。これが「四方良し」の使命です。
この使命を実現するのが、当社の事業部門「つない堂」です。
つない堂は「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことを目指しています。あらゆる分野で卓越した知見を持つ「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築する取り組みです。
信頼の循環システム
現代社会では、何かサービスを探すときにインターネット検索が一般的です。しかし、検索結果が必ずしも信頼できるとは限りません。
つない堂が目指すのは、インターネット検索を必要としない安心な循環地域型社会です。信頼できる人からの紹介により、安心してサービスを利用できる社会。2003年の成功が職人と顧客間の信頼を証明したように、地域社会全体の信頼という「常態」を構築することが目標です。
CSVモデルの実践
当社の多角的な責任を果たすための経営哲学は、「継塾」で継続的に探求されています。
継塾では、持続可能なビジネスモデルの探求をテーマとし、特にCSVモデル(社会課題解決型ビジネス)に焦点を合わせた議論を行っています。
CSVとは「Creating Shared Value」の略で、企業が社会課題の解決と企業価値の向上を同時に実現するビジネスモデルです。
2003年の転換によって得られた「職人による価値創造」という成功体験は、まさにCSVの実践そのものでした。職人の技術向上と顧客満足の向上を同時に実現し、さらに地域の建築文化の向上にも貢献したからです。
この哲学を深め、地域事業者に広げることで、地域を守り次世代に継承する事業を目指しています。
まとめ:2003年の決断が築いた未来への道筋
株式会社四方継にとって、2003年のリフォーム事業進出と、職人による直接施工が反響を呼んだ出来事は、現在のすべての理念の源流です。
この転換により、当社は以下の重要な価値観を確立しました。
「作り手」への信頼 職人の技術力と責任感が最も高い価値を生むことを証明し、その後の職人起業塾やマイスター高等学院という育成システムへの投資の正当性を示しました。
「暮らし」への責任 元請として建築後の長期的な安心を保証する責任を持つことで、無料巡回メンテナンスやSUMIKA-ZEROなどの取り組みにつながりました。
「四方良し」の基盤 作り手と住み手の信頼を軸に、協力会社や地域社会を含む四者すべてが満たされる経営へと視野が拡張しました。
2003年の成功は、大工集団の技術と誇りが時代を超えて通用する普遍的な価値を持つことを証明しました。そして、その価値を「継ぐ」ことが当社の揺るぎない使命であることを明確に示したのです。
2020年の「四方継」への社名変更、2022年の未来創造企業認定への道のりは、すべて2003年のあの決断から始まっています。
今後も当社は、職人精神を大切にしながら、お客様の暮らしを豊かにし、地域社会の発展に貢献していきます。それが、2003年に築いた信頼への恩返しであり、未来への責任でもあるのです。