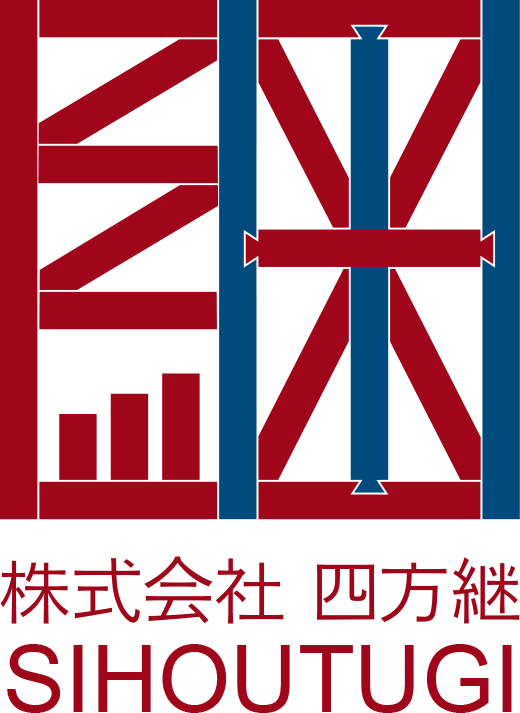はじめに:表面的な要望の奥にある「本当の望み」
「リビングをもっと広くしたい」「収納スペースをたくさん確保してほしい」
私たちつむぎ建築舎の打ち合わせでは、こうしたご要望を日々お聞きしています。しかし、長年の経験から確信していることがあります。それは、お客様が本当に求めているものは、言葉にされた要望の奥に隠れた「まだ気づいていない望み」だということです。
株式会社四方継の建築サービス部門である私たちつむぎ建築舎は、この見えない望みを形にすることを使命としています。「人、街、暮らし、文化を継ぎ四方良しを実現する」という企業理念のもと、単なる建物ではなく「受け継がれる価値のあるものづくり」を実践してきました。
では、「気づいていない望み」とは具体的に何を指すのでしょうか。それは表面的な要望の裏に隠された、住まい手の人生観、家族の絆、健康、そして将来の生活コストや環境負荷への潜在的なニーズです。
例えば「広いリビングがほしい」という要望の背景には「家族がもっと自然に集まれる空間で過ごしたい」という願いがあるかもしれません。また「収納を増やしたい」という声の奥には「すっきりとした暮らしで心の余裕を保ちたい」という想いが隠れていることもあります。
私たちは1994年の創業以来、大工集団として培った技術力と、お客様との信頼関係を大切にしながら、このような潜在的な望みを掘り起こし、形にしてきました。
見えない望みを掘り起こすコミュニケーション術
女性建築設計士だからこそ見えるもの
つむぎ建築舎では、女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションを何より重視しています。特に女性設計士の存在は、住まい手の潜在的なニーズを掘り起こす上で欠かせない要素です。
なぜ女性設計士が重要なのか。建築物は家族の毎日が営まれる場所です。間取りや光の入り方はもちろん、家事動線や家族間の心地よい距離感といった「暮らしの文化」に関わる要素こそが、長期的な満足度を左右するからです。
実際にあったケースをご紹介しましょう。あるお客様から「キッチンをもう少し広くしたい」というご要望をいただきました。一般的には面積を広げることを考えがちですが、私たちの女性設計士は「なぜ広くしたいのか」を深く聞き取りました。
すると、お客様が「料理をしながら子どもの宿題を見てあげたい」という想いを持っていることが分かったのです。この場合、単純に面積を広げるのではなく、キッチンとダイニングテーブルの位置関係を工夫し、料理をしながら自然に子どもとコミュニケーションが取れる空間を提案しました。
このような細やかな視点は、住まい手がまだ言葉にしていない、あるいは気づいてすらいない生活の課題や願望を、対話を通じて明らかにします。女性設計士のきめ細やかな視点こそが、真の望みを掘り起こす重要な鍵なのです。
大工が初期段階から参加する意味
掘り起こした「望み」を単なる理想論で終わらせないために、私たちは大工(作り手)を初期段階からコミュニケーションに参加させています。これは他の建築会社ではあまり見られない、つむぎ建築舎ならではの特徴です。
四方継のルーツは1994年創業の大工集団「高橋組」にあります。2003年には職人による直接施工が反響を呼び、元請中心の営業に転換しました。この歴史が示すように、私たちは職人の技術力と顧客との直接的な信頼関係を経営の核としてきました。
大工が設計段階から関わることで得られるメリットは大きく分けて二つあります。
一つ目は、設計士の細やかなデザイン意図を深く理解できることです。図面だけでは伝わらない微妙なニュアンスや、お客様の想いを直接聞くことで、より質の高い施工が可能になります。
二つ目は、長期的な耐久性や施工効率を考慮した専門家としての提案ができることです。例えば「将来的にメンテナンスしやすい構造にしておく」「地震に強い工法を選ぶ」といった、お客様が気づいていない重要な要素を提案できます。
この連携により、「作り手」と「住み手」という関係において、最高の品質と信頼を築く体制が整うのです。
専門家だからこそ提案できる未来への備え
数字で裏付けられた性能提案
私たちの専門家としての提案は、感情論ではなく「理」(ことわり)に基づいています。住まい手が将来直面するであろう課題を先取りし、解決策を設計に組み込むのです。
最も分かりやすい例が、エネルギーコストへの対策です。2012年に私たちが開発した高性能ゼロエネルギー住宅「SUMIKA-ZERO(スミカゼロ)」は、国土交通省のゼロエネルギー推進化住宅に認定されました。
この技術は、住まい手の長期的な光熱費抑制という「潜在的な経済的望み」を形にします。お客様は家を建てる時点では光熱費のことをそれほど深く考えていないかもしれません。しかし20年、30年と住み続ける中で、エネルギーコストは大きな負担となります。
実際に私たちが手がけた住宅では、一般的な住宅と比較して年間の光熱費が60%以上削減されたケースもあります。これは月々の家計負担を軽減するだけでなく、環境負荷低減という社会課題解決にもつながる「CSV(共有価値の創造)モデル」の実践でもあります。
目に見えないリスクへの先駆的対応
私たちは2012年から電磁波対策の取り組みを開始しました。これは当時としては非常に先駆的な取り組みでした。
電磁波は目に見えないため、多くの人が意識していません。しかし私たちは「22世紀の暮らしを見据える」という長期的な視点から、電磁波が健康に与える可能性のあるリスクに早期に着目しました。
具体的には、配線計画の工夫や電磁波を軽減する建材の採用など、住まい手の「潜在的な健康への望み」に応えるための対策を標準的に組み込んでいます。
このような取り組みは、2005年に2級建築士設計事務所登録を行い、確認申請業務や設計業務を充実させてきた技術的基盤があるからこそ実現できるものです。
建築後の安心を「当たり前」にする仕組み
本当に価値のある建築は、建てた時が最高点であってはいけません。建築後の長期的な安心こそが、住まい手の究極的な「望み」です。
2009年に私たちは「すべてのお客様に生活の安心・安全を」を合言葉に、無料巡回メンテナンスサービスを本格化しました(※無料巡回エリアは神戸近郊に限られます)。
このサービスは単なるアフターフォローではありません。設計段階でメンテナンスのしやすさや建物の耐久性を組み込むことと一体化した、未来への責任を果たす設計思想なのです。
例えば、外壁の材質選びでは見た目の美しさだけでなく、10年後、20年後のメンテナンスコストや手間も考慮します。屋根の形状も雨漏りのリスクを最小限に抑える設計にします。こうした配慮は、お客様が建築時には気づかない「将来の安心」という望みを形にしているのです。
信頼を可視化する透明な施工プロセス
「見える化」がもたらす安心感
どんなに素晴らしい設計がなされても、施工過程が不透明では住まい手は不安を感じてしまいます。私たちは「専門家としての提案・計画から施工プロセスの見える化」を徹底しています。
見える化とは具体的にどのようなことでしょうか。まず、施工の各段階で写真を撮影し、お客様に報告します。基礎工事の鉄筋配置から、断熱材の施工状況、配線・配管の様子まで、完成後には見えなくなる部分も含めて詳細に記録します。
また、使用する材料についても、どこでどのような基準で選んだものかを説明します。例えば構造材として使う木材なら、産地や乾燥方法、強度の等級まで詳しく報告します。
このような透明性は、住まい手と作り手(職人)の間に強固な信頼を築く土台となります。お客様は建築の複雑な過程を理解し、自分の家が最高の品質基準で造られていることを確認できるのです。
品質を支える「常態」への取り組み
透明性を確保することで、職人は常に高い倫理観と責任感を持って仕事に臨みます。これにより品質が個人の技量に左右されない「常態」を実現します。
私たちが毎年開催している「継塾」では、経営哲学やビジネスモデルを継続的に見直し、改善に取り組んでいます。2025年3月のテーマは「『常態』全ての成果の元になる理にじっくりと向き合ってみませんか?」でした。
このように、プロセスそのものの質の向上に継続的にコミットすることで、住まい手の「気づいていない望み」である「確実に品質の高い家を建ててもらいたい」という願いに応えています。
人材育成で支える持続可能なものづくり
職人の社内起業家精神の醸成
細やかな設計意図を実現できるのは、高い技術と誇りを持つ「作り手」だけです。私たちはこの人材の質を未来にわたって保証することで、住まい手の望みを形にする能力を維持しています。
2013年に開講し、2016年に一般社団法人職人起業塾として全国展開した「職人起業塾」は、イントラプレナーシップ、つまり社内起業家精神を醸成する研修プログラムです。これは職人の独立開業を促進するものではなく、組織内で自律的に考え、行動できる職人を育成することを目的としています。
なぜこのような取り組みが必要なのか。従来の建築業界では、職人は下請けの立場に置かれ、正当な評価を受けにくい構造がありました。しかし私たちは職人こそが建築の品質を決める重要な存在だと考えています。
職人起業塾を修了した職人たちは、設計士と対等に議論し、住まい手の望みを理解する高いコミュニケーション能力と専門的な提案能力を身につけます。社内起業家として、自ら考え、判断し、責任を持って行動することで、お客様が気づいていない細かなニーズまで汲み取れる体制が整うのです。
次世代への技術継承
建築業界では深刻な「職人不足」が問題となっています。この社会課題に歯止めをかけるため、2023年に「マイスター高等学院」を設立、開校しました。
この学院は高校卒業の資格を取りながら大工など建設業における「職人」としての技術を身につける通信制高校です。代表者高橋剛志の「モノづくりの担い手を子供の憧れの職業にする」という理念を具現化したものです。
従来の職業訓練とは異なり、技術だけでなく経営感覚も養うカリキュラムになっています。生徒たちは実際の現場で経験を積みながら、将来は職人として活躍できるスキルを身につけます。
質の高い人材が「常態」として存在することで、つむぎ建築舎は住まい手が気づいていない難易度の高い望みでも実現可能であることを保証できるのです。
街全体を良くする地域連携の取り組み
信頼のネットワーク構築
住まい手の「気づいていない望み」には「この街で安心して暮らし続けたい」という願いも含まれます。建築物が世代を超えて価値を持つためには、「いい街を継ぐ」ことが不可欠です。
私たちの事業部門「つない堂」は、この「街」の安心を創造します。つない堂のビジョンは「信頼の輪を広げ、検索不要の安心安全な地域社会を作る」ことです。
現代はインターネットで何でも調べられる時代ですが、情報があふれすぎて何を信頼すればよいか分からないという問題があります。つない堂では、実際に顔の見える関係で信頼できる「人」「事業所」「サービス」を発掘し、リアルなネットワークを構築しています。
例えば、家を建てた後に「信頼できる電気屋さんを知りたい」「子どもの習い事でいいところはないか」「高齢の親の介護で相談したい」といったニーズが生まれます。そんな時にインターネット検索ではなく、顔の見える信頼関係の中で最適なサービスを紹介できるのです。
暮らし全体への包括的な提案
住まい手の「望み」は建物内部の設計に留まりません。そこで営まれる生活全体に及びます。
2007年には店舗設計やマネジメント提案の研究も兼ねて飲食事業部を設立しました。また、2020年の株式会社四方継への社名変更を機に、つない堂の活動として「住環境に食、学びを通して日々の暮らしを豊かにしよう!」をコンセプトにした取り組みを展開しています。
この活動では、住まいの手入れ方法から季節の料理、子育てのコツまで、幅広いテーマで地域の皆様と交流しています。建物というハードだけでなく、そこで営まれる「暮らしの文化」というソフト面においても、住まい手がより豊かで持続可能な生活を送れるよう、専門家として多角的な提案を行っているのです。
この取り組みは住まい手の「暮らし」の望みを、地域社会という「四方」の健全な機能と連携させる、包括的なCSVモデルの実践です。良い職人、良い専門家、良いサービスが地域に根づくことで、街全体の住環境が向上します。これは結果的に、私たちが手がけた住宅の資産価値向上にもつながります。
未来創造企業としての責任
認定が示す社会的評価
2022年に一般社団法人日本未来企業研究所より「未来創造企業」として認定されたことは、私たちが「気づいていない望みを形にする」という使命を、未来を見据えた経営として実現していることの証明です。
この使命は2020年の株式会社四方継への社名変更の際に確立された理念「地域を守り次世代に継なげる事業を目指す」という決意と完全に一致しています。
「気づいていない望み」とは、まさに未来の世代にとって必要な価値のことです。私たちの設計思想は次の3つの要素で統合されています。
まず「長期的な視点」です。短期的な満足でなく、無料巡回メンテナンスや高性能ゼロエネルギー技術のように、数十年にわたり価値を維持・向上させる視点を提案します。
次に「社会課題解決」です。職人育成(人)や地域信頼構築(街)といった、建築を取り巻く社会環境の課題解決を事業に組み込み、住まい手の生活基盤を根本から強化します。
最後に「継続的な刷新」です。継塾を通じて常に経営哲学やビジネスモデルを見直し、「常態」の質を高め続ける文化を持ちます。
次世代への責任
私たちが「気づいていない望みを形にする」取り組みは、単なるサービスの差別化ではありません。それは未来への責任を果たす行動です。
地球環境の変化、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化など、私たちの社会は多くの課題を抱えています。これらの課題は、今すぐには深刻に感じられないかもしれませんが、確実に次世代に影響を与えます。
私たちは建築を通じて、エネルギー効率の良い住宅を普及させ、職人技術を次世代に継承し、信頼できる地域コミュニティを築くことで、これらの課題解決に貢献しています。
住まい手の「気づいていない望み」を形にすることは、実は未来の社会全体の望みを形にすることでもあるのです。
まとめ:望みを形にする総合力
株式会社四方継「つむぎ建築舎」が「住まい手がまだ気づいていない、知らない望みを形にします」という使命を果たすプロセスは、単なる設計技術の向上にとどまりません。
女性建築設計士と大工による細やかなコミュニケーションから始まり、専門家としての提案・計画、施工プロセスの見える化を通じて、住まい手の潜在的なニーズを具現化します。
それは環境負荷の低減、長期的な安心、生活の質の向上といった要素を、SUMIKA-ZEROや電磁波対策のような革新的な技術と、職人育成という人材保証によって実現する、未来への責任を果たす総合的なシステムです。
私たちは今後も、この「受け継がれる価値のあるものづくり」を通じて、住まい手の未来の生活と、その生活が営まれる「いい街」そのものを、次の世代に継承し続けてまいります。
一軒一軒の家づくりは、実は未来の社会づくりでもある。そんな想いを胸に、これからも住まい手の心の奥にある本当の望みを形にしていきます。